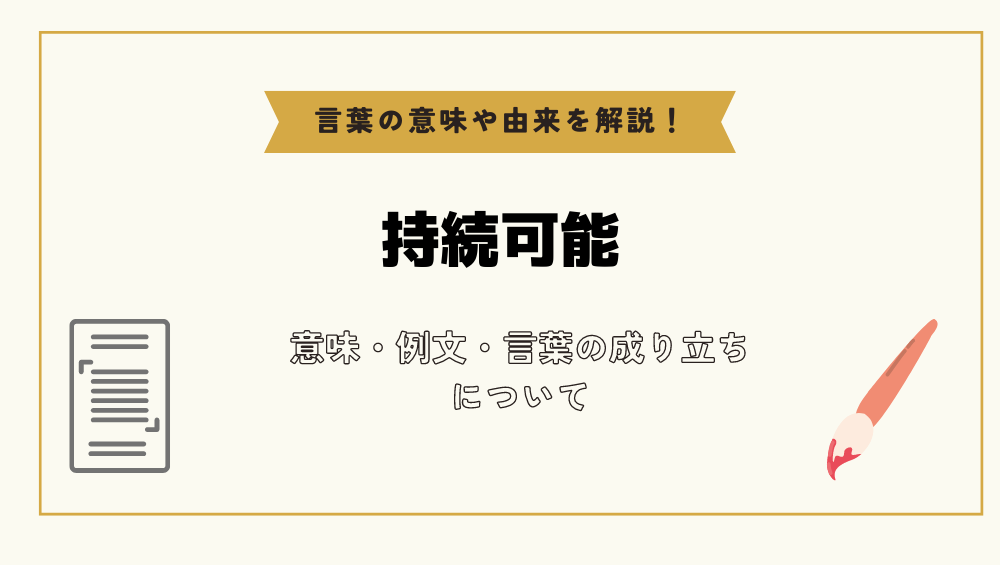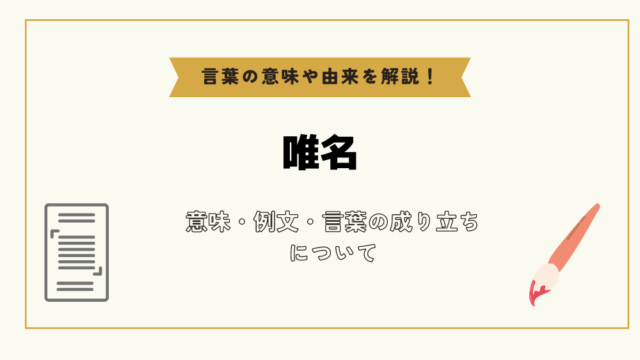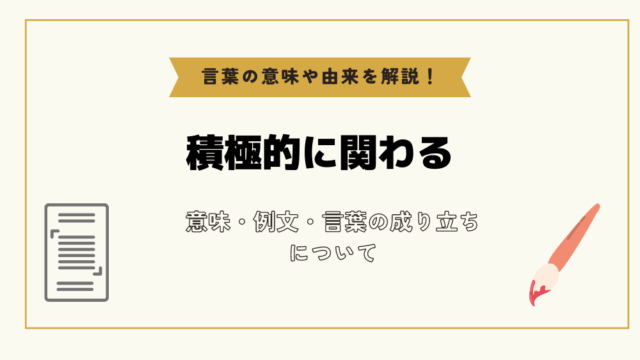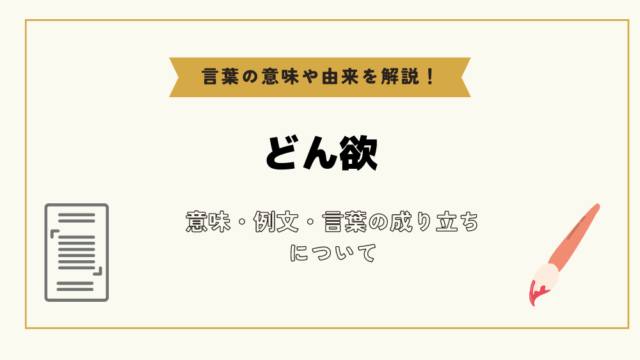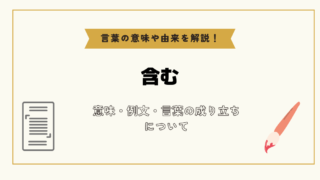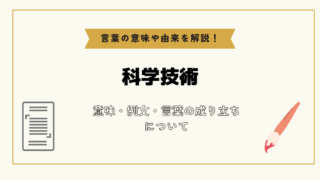Contents
「持続可能」という言葉の意味を解説!
「持続可能」とは、何かが継続的に続けられることを指します。
具体的には、自然環境や社会的なシステムが維持されることを意味しています。
持続可能な社会を築くためには、経済的な成長や発展が環境に与える悪影響を最小限に抑えることが重要です。
例えば、工業生産や大量消費によって環境が破壊されてしまったり、資源が枯渇したりすると、持続可能な社会を築くことは難しくなります。
持続可能性を考慮した行動や政策は、地球上の資源や環境への負荷を最小化することにつながります。
私たちの生活や社会が持続可能であれば、将来の世代も同様に豊かな環境や資源を享受することができます。
そのためには、「持続可能」という考え方が重要であり、さまざまな分野で取り組みが進められています。
「持続可能」の読み方はなんと読む?
「持続可能」は、「じぞくかのう」と読みます。
日本語の読み方なので、比較的簡単に覚えることができます。
この言葉は、近年ますます注目されているテーマであり、多くの人が理解しようとしています。
持続可能性への関心が高まる中、この言葉を正しく読み、意味を理解することは大切です。
持続可能な社会を築くためには、個々人が意識を持ち、行動を起こすことが必要です。
そして、そのためにはまず、言葉の意味を正しく理解することが第一歩となります。
「持続可能」という言葉の使い方や例文を解説!
「持続可能」という言葉は、さまざまな場面で使われます。
例えば、「持続可能な開発」「持続可能な経済」「持続可能な生活」などといった形で使われることがあります。
「持続可能な開発」とは、経済的な成長を追求しながら、地球上の資源や環境を維持することを目指す開発のことを指します。
例えば、再生可能エネルギーの利用やリサイクルの推進などが、持続可能な開発の一環として取り組まれています。
また、「持続可能な経済」とは、短期的な利益追求ではなく、中長期的に社会の持続的な発展を追求する経済のあり方を指します。
例えば、経済の成長が地域や社会全体に平等に還元されるような仕組みづくりや、環境負荷の最小化を重視する取り組みが求められています。
「持続可能」という言葉の成り立ちや由来について解説
「持続可能」という言葉は、1972年に国連の制定した「人間の環境に関するストックホルム宣言」で初めて使用されました。
この宣言では、「持続可能な開発」の概念が世界的に広まり、その後の環境政策や経済政策に大きな影響を与えました。
「持続可能」という言葉の成り立ちは、英語の「sustainable」に由来しています。
この言葉は、「sustain」(維持する)と「able」(できる)を組み合わせたものであり、継続的な状態を維持することが可能であるという意味を持ちます。
「持続可能」という言葉が世界中で使用されるようになった背景には、地球環境の悪化や資源の枯渇といった課題があると言えます。
この言葉は、地球の未来を考える上で欠かせない概念となっており、さまざまな分野で注目を集めています。
「持続可能」という言葉の歴史
「持続可能」という言葉は、1970年代から広まり始めましたが、その考え方自体は古くから存在していました。
人類が環境や資源を持続的に利用することの重要性は、昔から認識されていたのです。
19世紀には、アメリカの作家であるヘンリー・デイビッド・ソローが、「野生の評価」という著書で、自然と人間の調和と持続可能性について述べています。
彼は環境への配慮と持続可能性の考え方を提唱し、今日の環境保護運動へとつながるきっかけとなりました。
その後、世界的な環境問題が浮き彫りになり、1972年の国連ストックホルム会議で「持続可能な開発」が提唱されるなど、持続可能性に関する議論が広がっていきました。
現代では、持続可能性の重要性がますます認識されるようになり、様々な分野で取り組みが進められています。
「持続可能」という言葉についてまとめ
「持続可能」という言葉は、環境や資源を維持しながら社会を発展させることを目指す重要な概念です。
持続可能な社会を築くためには、個々人の意識と行動が求められます。
また、「持続可能」の言葉は、1972年の国連ストックホルム会議で初めて使用され、その後世界的に広まりました。
ただし、その考え方は古くから存在していたものであり、人類が環境との調和を追求してきた歴史があります。
持続可能性への関心はますます高まり、さまざまな取り組みが進められていますが、これからも私たちの生活や社会が持続可能であるためには、個々人が積極的な意識と行動を持つことが不可欠です。