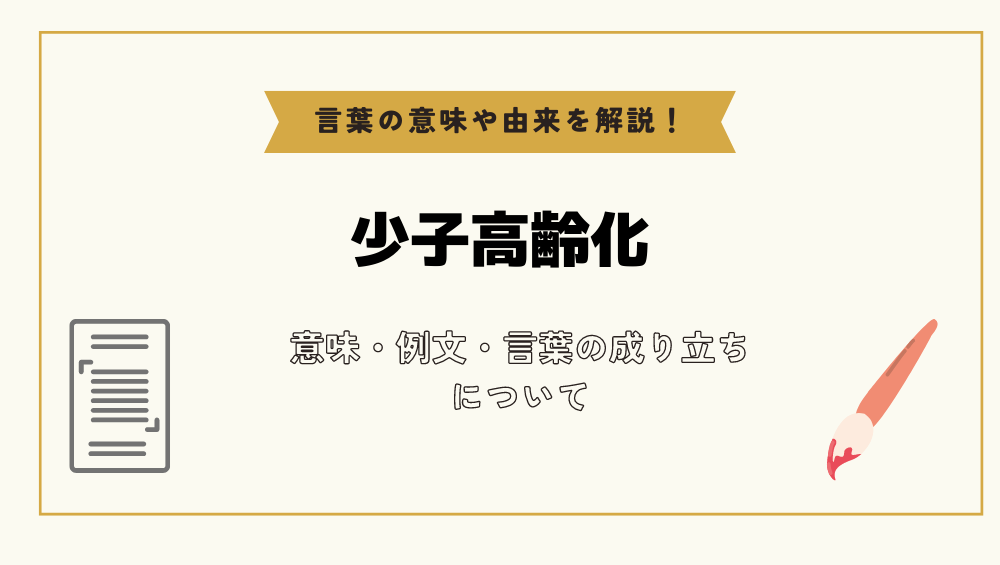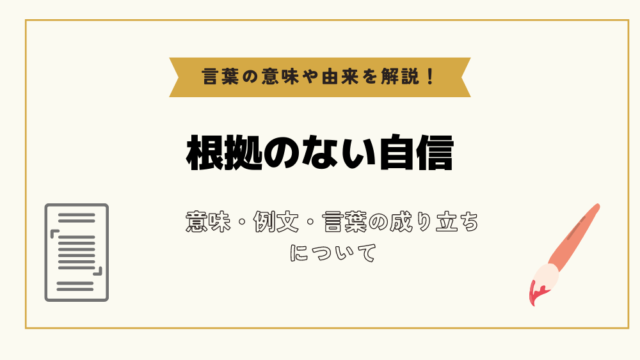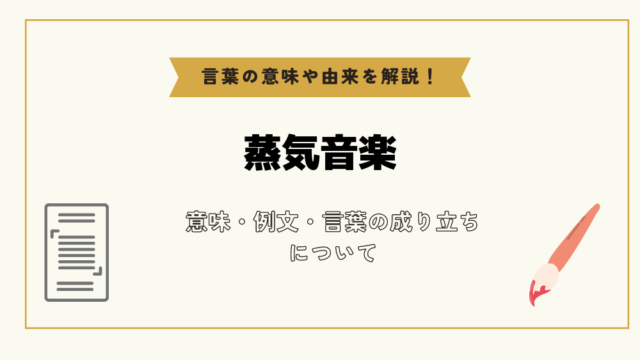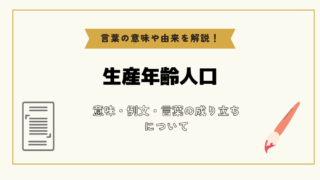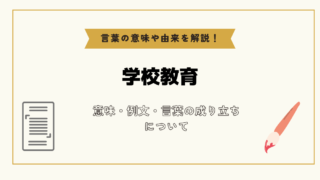Contents
「少子高齢化」という言葉の意味を解説!
。
「少子高齢化」とは、人口の中で子どもの数が減少し、高齢者の数が増えることを指します。
日本の21世紀における最大の社会問題であり、経済や社会の様々な領域に大きな影響を与えています。
少子高齢化が進むと、労働力不足や社会保障費の増加、地域の活力低下などの問題が生じることが懸念されています。
「少子高齢化」の読み方はなんと読む?
。
「少子高齢化」は、「しょうしこうれいか」と読みます。
この読み方は、ほとんどの人が認識しており、よく使われています。
しかし、読みにくさを避けたい場合や、特に漢字の読み方に不慣れな場合は、「しょうしこうれいか」とも読まれることがあります。
「少子高齢化」という言葉の使い方や例文を解説!
。
「少子高齢化」は、経済や社会政策に関する議論において頻繁に使われます。
例えば、政府は「少子高齢化対策」として、出産率向上や高齢者の支援策など様々な施策を実施しています。
また、企業も「少子高齢化に対応する」という意識から、柔軟な働き方や福利厚生の充実など、従業員のニーズに応える取り組みが進んでいます。
「少子高齢化」という言葉の成り立ちや由来について解説
。
「少子高齢化」という言葉は、1970年代頃に使われるようになりました。
その背景には、日本の出生率が低下し、高齢化社会の到来が予想されたことがあります。
人々は、子どもの数が減ることで将来の労働力や社会の安定性に懸念を抱き、この言葉を使うようになりました。
「少子高齢化」という言葉の歴史
。
「少子高齢化」という言葉は、1960年代後半から1970年代にかけてメディアや学術界で使われるようになりました。
当初は小規模な議論でしたが、1980年代に入ると少子高齢化が社会問題として認識されるようになり、政府や企業など社会全体での取り組みが進んできました。
「少子高齢化」という言葉についてまとめ
。
「少子高齢化」とは、子どもの数が減り、高齢者の数が増える現象を指します。
日本社会において最も重要な問題の一つであり、様々な領域での影響が懸念されています。
政府や企業などが対策を取りながら、社会全体での取り組みが求められています。