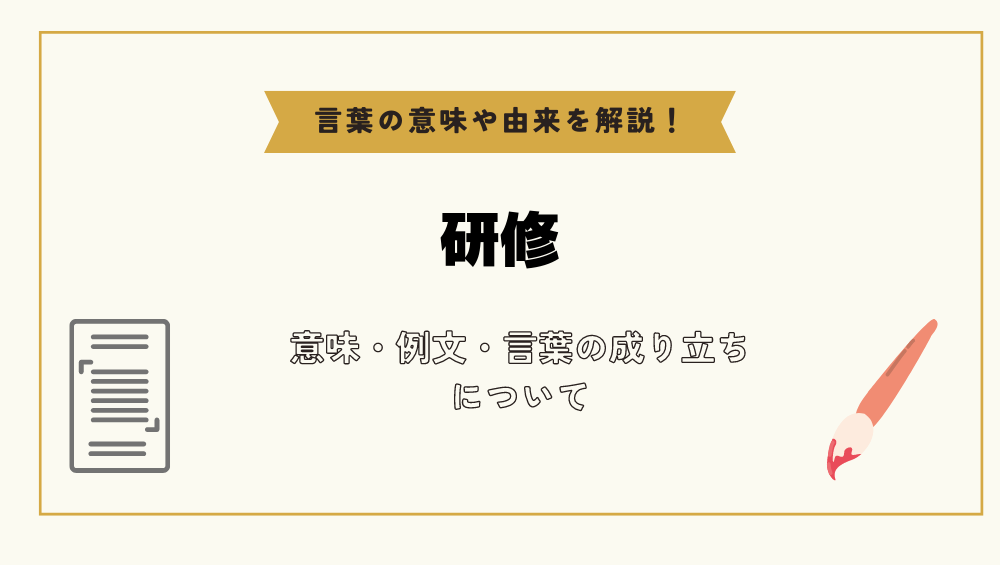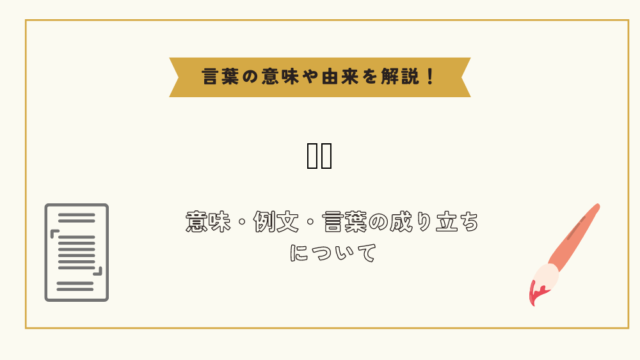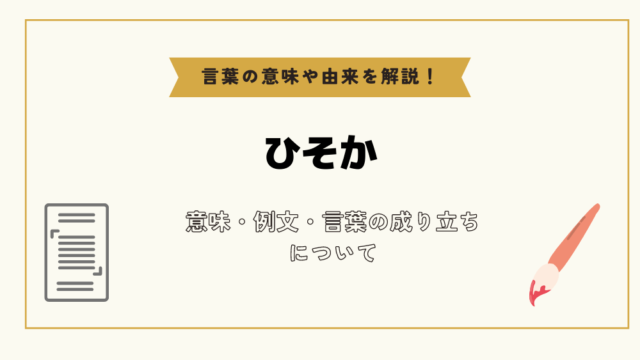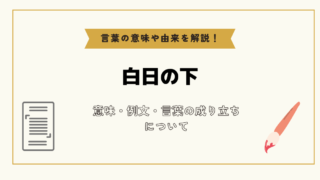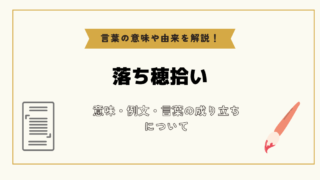Contents
「研修」という言葉の意味を解説!
。
「研修」という言葉は、専門的な知識や技術を身につけるための教育や訓練を指す言葉です。
具体的には、企業や団体が従業員やメンバーに対して行う継続的な教育プログラムや訓練のことを指します。
。
研修は、個々のスキルや専門知識を向上させるだけでなく、仕事に対する意識やチームワークの向上、コミュニケーション能力の向上など、社会人として必要とされる幅広いスキルを身につける機会となります。
。
研修は、新入社員の教育や組織の改善、業務の効率化など、企業や団体の成長と発展にも大きく関わる重要な要素です。
また、個人のキャリア形成や成長にも欠かせないものとなっています。
「研修」という言葉の読み方はなんと読む?
。
「研修」という言葉は、「けんしゅう」と読みます。
漢字の「研」は、「研ぐ」という意味があり、鋭利なものを使う前に、その刃を磨くという意味です。
また、「修」は、「磨く」という意味があり、何かを良くしようと努めることを意味します。
この2つの漢字が組み合わさり、「けんしゅう」と読まれるようになりました。
「研修」という言葉の使い方や例文を解説!
。
「研修」という言葉は、以下のような例文で使われます。
。
例文1:新入社員は入社後、2週間の研修を受けます。
。
例文2:研修の期間中は、基礎的な知識から専門的な技術まで幅広く学ぶことができます。
。
例文3:研修の成果を発表する場がありました。
自分の成長を実感できるいい機会でした。
。
このように、「研修」という言葉は、企業や団体の教育プログラムや訓練を指し、その過程や成果を表現する際に使われます。
「研修」という言葉の成り立ちや由来について解説
。
「研修」という言葉は、主に日本語で使用される言葉です。
この言葉の成り立ちは、漢字2文字が組み合わさることによって形成されています。
。
「研」という漢字は、本来は「石を研ぐ」という意味を表していました。
刃物や工具などを使う前に、その鋭利さを取り戻すために研ぐという行為は、品物の状態を良くするための工程であり、それを学ぶということが「研修」の語源になったと考えられます。
。
また、「修」という漢字は、物事を良くするために努力するという意味を持ちます。
これら2つの漢字が組み合わさり、「研修」という言葉が生まれました。
「研修」という言葉の歴史
。
「研修」という言葉は、江戸時代以前から存在していたと考えられています。
当時は、座学や実習などを通じて、人々が専門的な知識や技術を修得していました。
しかし、明治時代以降の近代化の流れと共に、より体系的かつ効率的な教育や訓練が求められるようになりました。
。
その結果、多くの企業や団体が独自の研修プログラムを設けるようになり、研修の需要が増えました。
現代では、様々な形態の研修が行われており、個々の分野に特化した研修も増えています。
「研修」という言葉についてまとめ
。
「研修」という言葉は、企業や団体が従業員やメンバーに対して行う教育や訓練を指します。
専門的な知識や技術を身につけるだけでなく、意識やチームワーク、コミュニケーション能力などを向上させる機会となります。
この言葉は、「けんしゅう」と読みます。
研修の期間中は、基礎的な知識から専門的な技術まで幅広く学ぶことができます。
言葉の成り立ちや由来は、漢字「研」と「修」が組み合わされています。
研修の需要は近代化と共に増え、様々な形態の研修が行われるようになりました。