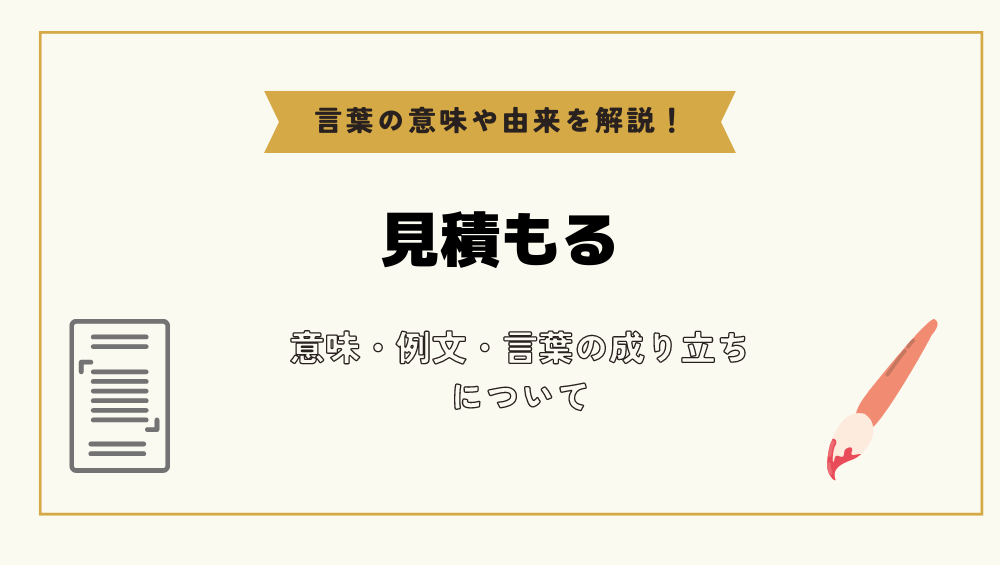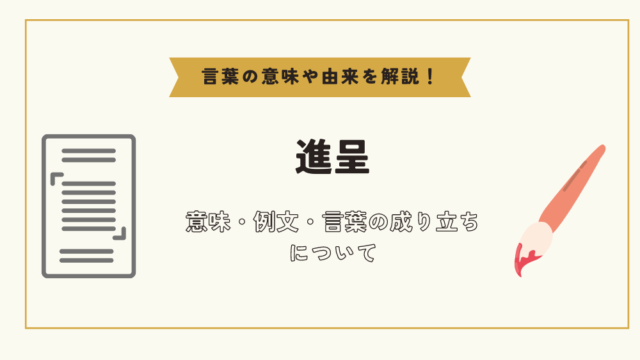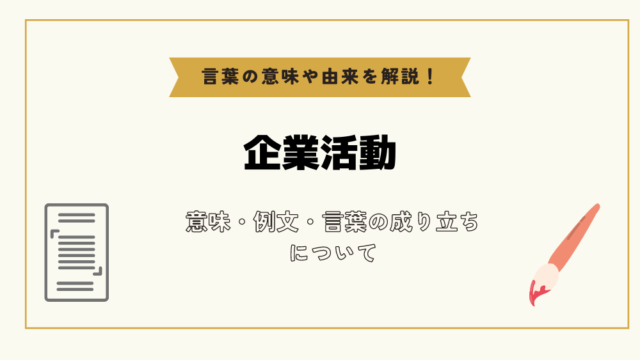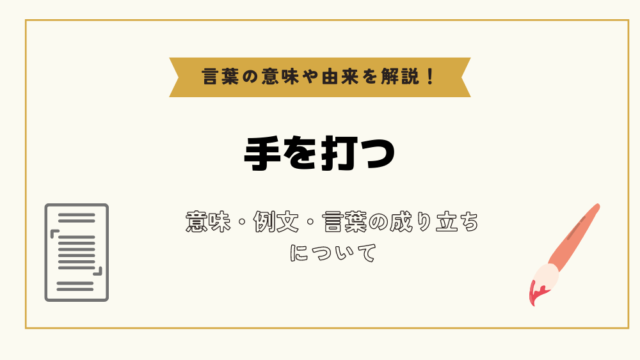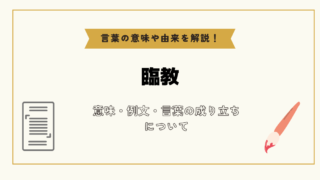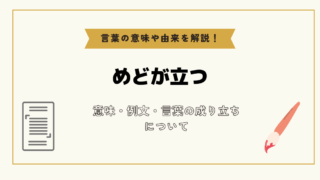Contents
「見積もる」という言葉の意味を解説!
「見積もる」という言葉は、物事の大まかな量や範囲などを推測したり、評価したりすることを意味します。
具体的には、何かの値段や数量、時間などを大まかに予想し、それを確定させるために行う行為です。
ものごとの見込みを立てる際に使われることが多く、ビジネスや工事、プロジェクト管理など様々な場面で活用されます。
「見積もる」の読み方はなんと読む?
「見積もる」は、ひらがなで「みつもる」と読みます。
まず「見積(みつ)」という基本的な言葉があり、それに「もる」という活用語尾が付いています。
読み方には、古語の「ものる」という動詞が語源とされており、推測する、評価するといった意味合いがあります。
「見積もる」という言葉の使い方や例文を解説!
「見積もる」は、具体的な事柄に関して予測を立てる際に使います。
例えば、ビジネスで新商品の開発を考える場合、市場の需要や売上予測を「見積もる」といいます。
また、工事現場で必要な資材や人員を見積もることもあります。
例文としては、「今後の需要を見積もり、生産計画を立てる必要があります」というように使われます。
「見積もる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「見積もる」は、古語の「ものる」という動詞が語源とされています。
「ものる」は、「見る」や「見詰める」という意味があり、ものごとを注視して判断や予測をするという意味が含まれていました。
後に活用語尾の「もる」が付け加えられ、現在の「見積もる」という形になりました。
「見積もる」という言葉の歴史
「見積もる」の歴史は古く、日本語の基礎を築いた古典文学にも使われていました。
日本書紀や古事記にも「見積」という言葉が出てくる場面があり、天皇の儀式や建物の工事などで使用されていたことがわかります。
その後、商業や産業の発展に伴い、ビジネスやプロジェクト管理などで「見積もる」が重要な要素として取り入れられるようになりました。
「見積もる」という言葉についてまとめ
「見積もる」という言葉は、物事の予測や評価をする際に使われる重要な言葉です。
ビジネスや工事、プロジェクト管理など、さまざまな場面で活用されています。
古語の「ものる」が語源とされ、日本の古典文学にも存在します。
多くの人々が日常的に使っている「見積もる」の意味や使い方を理解し、効果的に活用することが重要です。