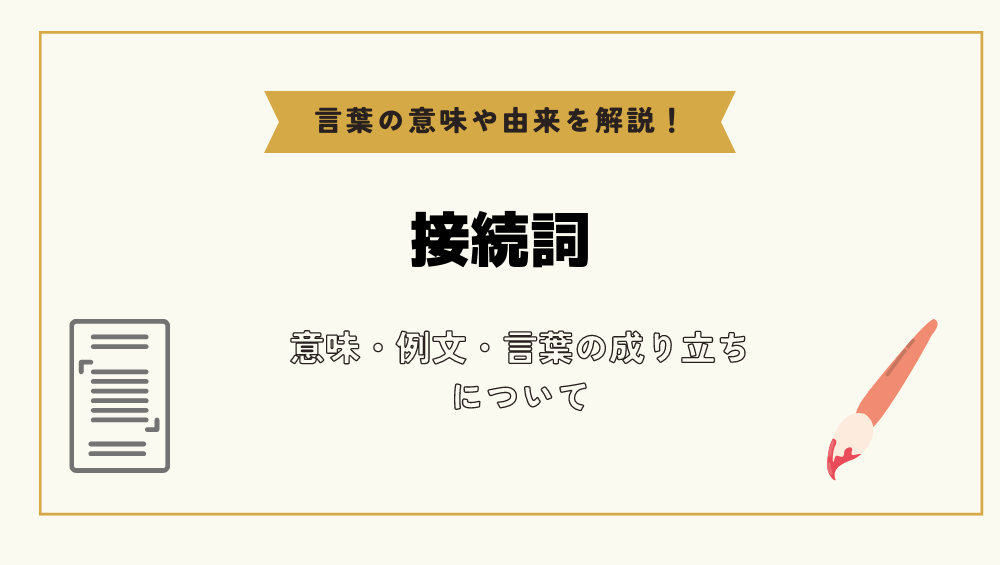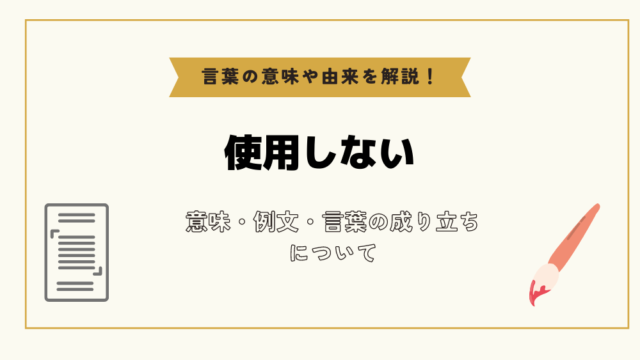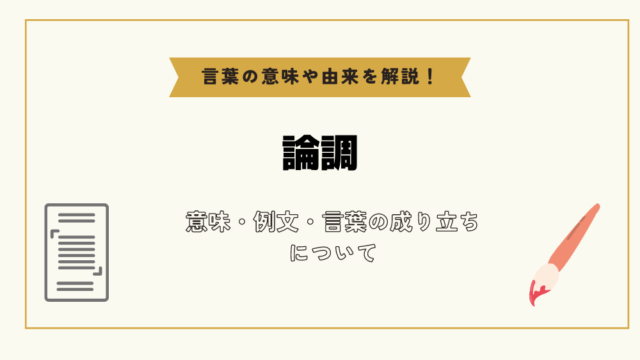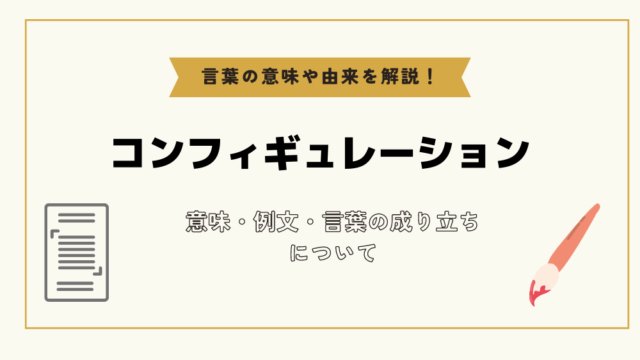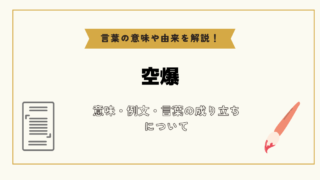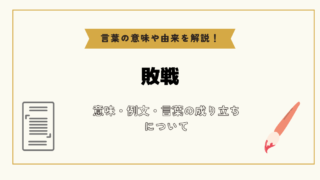Contents
「接続詞」という言葉の意味を解説!
皆さんは「接続詞」という言葉を聞いたことがありますか?接続詞は文章や文と文を繋ぐ役割を果たす言葉です。
「そして」「しかし」「また」「しかし」など、接続詞はさまざまな形で使われます。
接続詞は文同士をつないで、関係性や意味を明確にするために使われます。
文章をよりスムーズに読みやすくし、聞き手に伝える意図を明確にする重要な要素となっています。
「接続詞」は読む時は「せつぞくし」と読みます。
接続詞は日本語文法の一部として存在しており、文章の流れを整える役割を果たしています。
「接続詞」という言葉の使い方や例文を解説!
「接続詞」は文章をつなげる重要な役割を果たしています。
例えば、「そして」は後の文に続けて話を進める際に使われます。
「しかし」は前の文と対比して次の文に進む際に使われます。
使い方を覚えるために、いくつかの例文を挙げてみましょう。
例えば、「私は映画が好きです。
そして、週末によく映画館に行きます」という文では、前半と後半が接続詞「そして」でつながっています。
また、例えば「彼は頭がいいです。
しかし、勉強が苦手です」というように、接続詞「しかし」を使って対比を表現することもあります。
「接続詞」という言葉の成り立ちや由来について解説
「接続詞」という言葉は、「接続」と「詞」の2つの言葉から成り立っています。
接続は何かを繋ぐという意味であり、詞は単語や言葉を指す言葉です。
接続詞は文と文を繋げる役割を果たすために生まれました。
文同士をスムーズにつなげることで、文章を読みやすくし、意味を明確に伝えることができます。
「接続詞」という言葉の歴史
「接続詞」という言葉は、日本語文法の一部として古くから存在しています。
明治時代には、既に接続詞が文法書や教科書に記載されていたとされています。
現代の日本語では、接続詞は多様な使い方があり、表現の幅を広げる重要な要素となっています。
文法の変遷に伴い、接続詞の使い方も変化してきましたが、その基本的な役割は今も変わらず存在しています。
「接続詞」という言葉についてまとめ
「接続詞」とは、文章や文と文をつなげる役割を果たす言葉です。
文章をスムーズに読みやすくし、関係性や意味を明確にするために、接続詞は重要な要素となっています。
接続詞は「そして」「しかし」「また」「しかし」などさまざまな形で使われ、文のつながりや対比を表現することができます。
文法の一部として古くから存在し、日本語の表現力を豊かにする役割を果たしています。