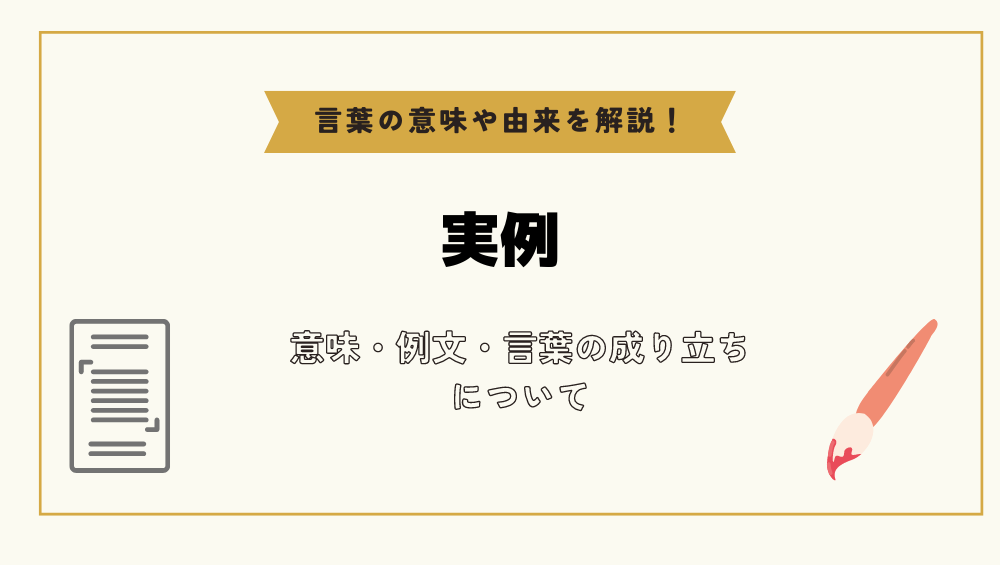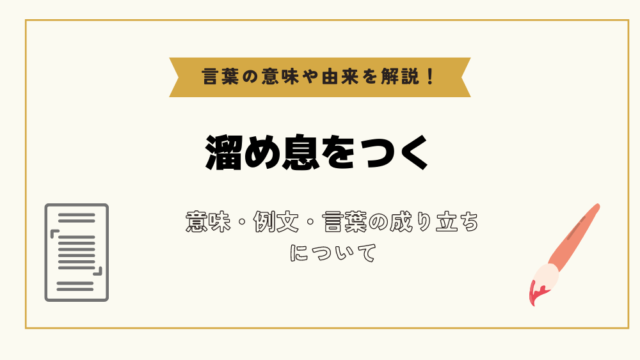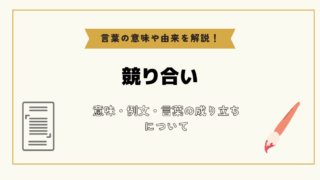Contents
「実例」という言葉の意味を解説!
実例という言葉は、具体的な事例や実際の例を指す言葉です。何かを説明する際に、抽象的な概念や理論だけではわかりにくい場合に、具体的な実例を挙げて説明することで、理解しやすくする役割を果たします。
例えば、新しい商品やサービスを紹介する際に、その商品やサービスの実例を挙げることで、具体的なイメージを持ってもらうことができます。また、学問や研究においても実例は重要です。仮説や理論を裏付けるためには、実際のデータや事実を示す実例が必要です。
実例は身近な生活や仕事の中でよく使われる言葉であり、私たちが日常的に関わる様々な場面で活用されます。
「実例」という言葉の読み方はなんと読む?
「実例」という言葉は、「じつれい」と読みます。漢字の「実」は「みのる」と読むこともありますが、この場合は「じつ」という読み方が一般的です。
「実例」という言葉は、日本語の教育や学問の分野でよく使われるため、多くの人が「じつれい」という読み方を知っています。
「実例」という言葉の使い方や例文を解説!
「実例」という言葉は、何かを説明する際に具体的な事例や例を挙げるために使われます。
例えば、
– 「この理論は抽象的でわかりにくいかもしれませんが、実例を挙げて説明します。
」。
– 「この商品は優れた機能を持っています。
実例を見てみましょう。
」。
などと使われます。
「実例」を使うことで、聞き手や読み手に具体的なイメージや事例を提供することができます。
「実例」という言葉の成り立ちや由来について解説
「実例」という言葉は、日本語の学問や教育の分野で用いられるようになった言葉です。成り立ちや由来には特別なエピソードや逸話はありませんが、言葉自体には「実」という字が使われており、「実際の事例や例」という意味が込められています。
「実例」という言葉は、日本の学校教育や研究の分野で重要な役割を果たしています。理論や抽象的な概念だけではなく、実際の現象や具体的なデータに基づいて学ぶことや説明することが重要視されているため、この言葉が多く使われるようになりました。
「実例」という言葉の歴史
「実例」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や法律の分野でも使われてきました。古代の法典や仏教の教えにおいても、実際の事例や例を示すことが重要視されていました。
また、江戸時代には「実例」という言葉を冠した書物も多く出版されました。これらの書物には、実際の出来事や人物の事例をまとめたものが含まれており、学問や教育の分野で活用されました。
現代でも「実例」という言葉は、学問や教育の分野だけでなく、様々な場面で使われ続けています。
「実例」という言葉についてまとめ
「実例」という言葉は、具体的な事例や実際の例を指す言葉です。「実例」を使うことで、説明が具体的になり、理解しやすくなります。
読み方は「じつれい」と読みます。日本語の教育や学問の分野でよく使われており、多くの人がその読み方を知っています。
「実例」という言葉は、何かを説明する際に具体的な事例や例を挙げるために使われます。また、日本の古典文学や法律の分野でも使用され、江戸時代以来長い歴史があります。
私たちが日常的に使用する「実例」という言葉は、学問や教育の分野だけでなく、様々な場面で活用されており、重要な役割を果たしています。