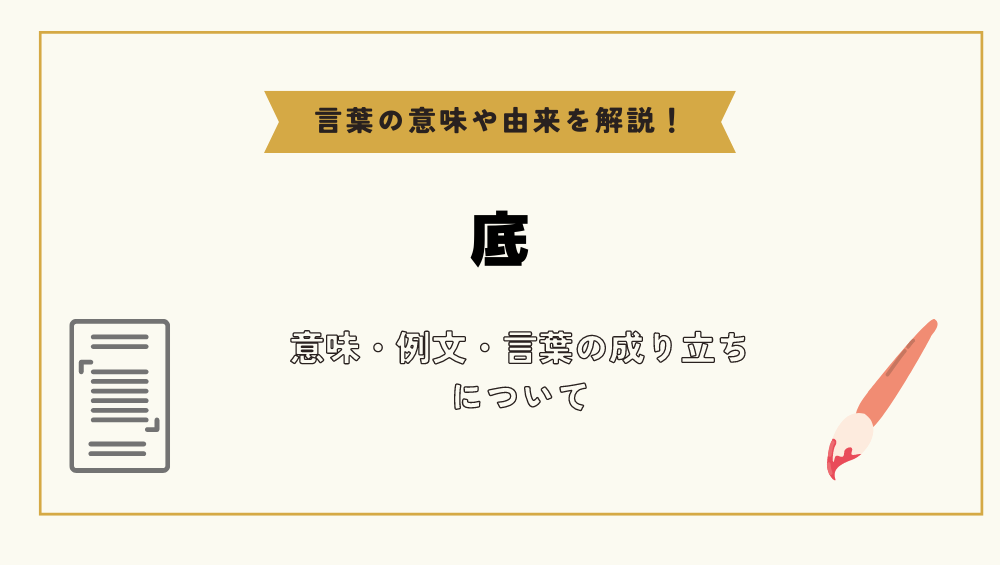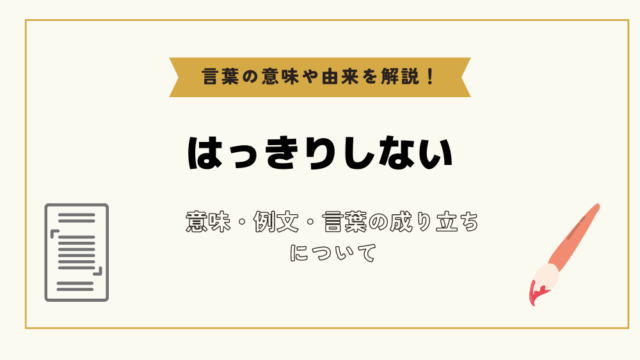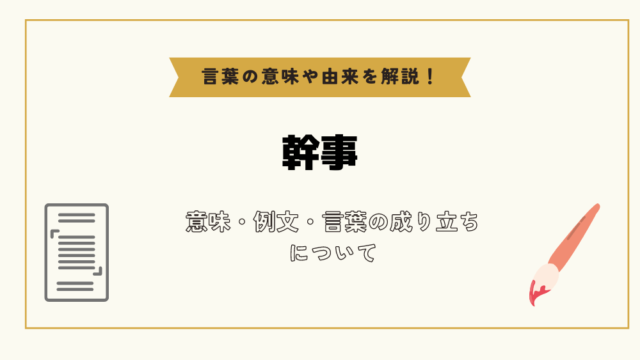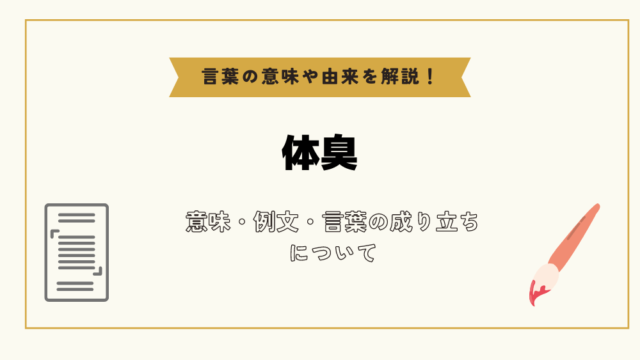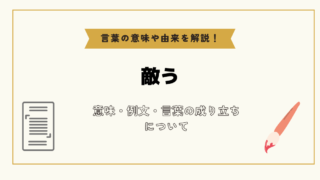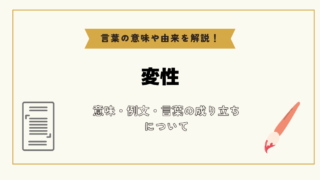Contents
「底」という言葉の意味を解説!
「底」という言葉は、物事や状況の一番下や最も下部を指す言葉です。
例えば、海の底やコップの底など、物理的な場所の一番下を指す場合に使います。
また、抽象的な意味でも使用され、最も低い地位や最悪の状態を表現することもあります。
例えば、人生の底を経験するなど、非常に困難な状況や感情的に低い状態を指すこともあります。
「底」という言葉の読み方はなんと読む?
「底」という言葉は、「そこ」と読みます。
この読み方は漢字の意味に基づいています。
「底」は、上に人(ひと)が立ち、下に止(と)があることから、上から下に向かうものを表し、その結果「そこ」と読まれるようになりました。
「底」という言葉の使い方や例文を解説!
「底」という言葉は、様々な場面で使われます。
例えば、コップの底が見えるという表現では、飲み物がほとんどなくなったことや、コップの中のものが最後まで残っていないことを意味します。
また、経済の底という表現では、景気が悪化し最悪の状態になったことを指します。
他にも、心の底に秘めた思いや、社会の底辺に生きる人々など、さまざまな用途で使われます。
「底」という言葉の成り立ちや由来について解説
「底」という言葉の成り立ちは、古代中国にさかのぼります。
元々は漢字の「冫」(氷)と「广」(広)の組み合わせで、氷の下や一番下を意味していました。
日本に伝わった後、「氷」の部分が「广」に変化し、「冫」が画数の多い「广」に置き換えられ、「底」という漢字として定着しました。
「底」という言葉の歴史
「底」という言葉は、中国で紀元前の時代から使用されていたと言われています。
当初は、物理的な意味で海の底や井戸の底などを指すことが一般的でした。
その後、抽象的な意味でも使用されるようになり、最悪の状態や絶望的な状況を表現する言葉として広く使われるようになりました。
「底」という言葉についてまとめ
「底」という言葉は、物事や状況の最も下部を指す言葉です。
海の底やコップの底など、物理的な意味から抽象的な意味まで、さまざまな場面で使われます。
また、「底」という言葉は、古代中国から伝わり、日本では漢字で表されるようになりました。
その歴史や由来を知ることで、より深く理解することができます。
底には人間の感情や困難な状況を表現する力があります。