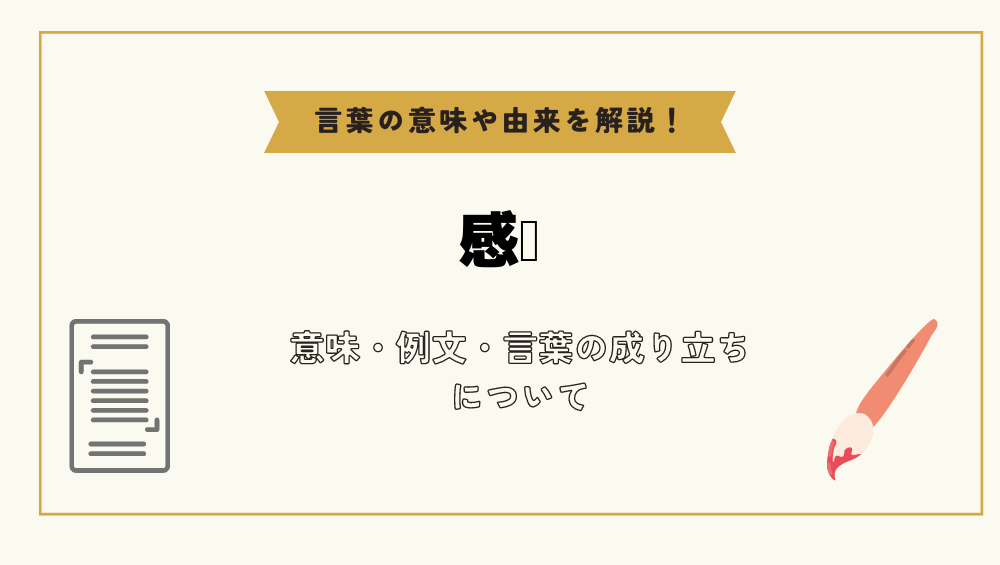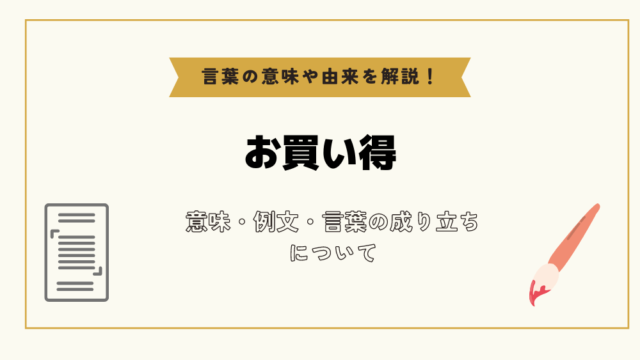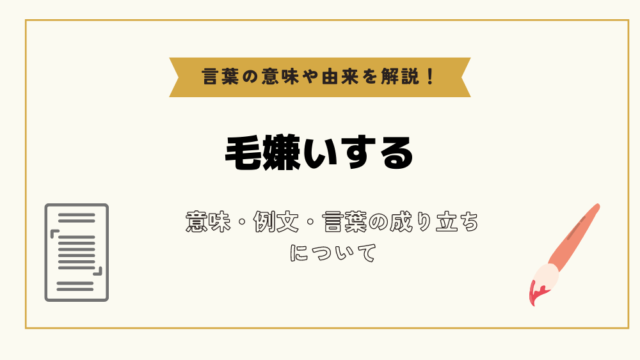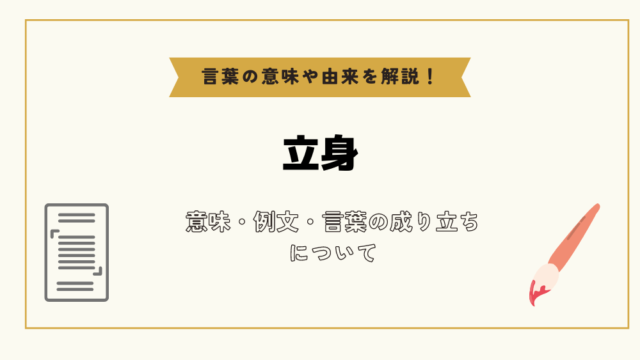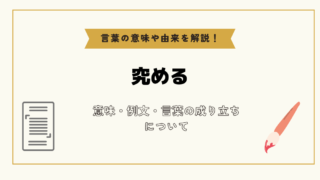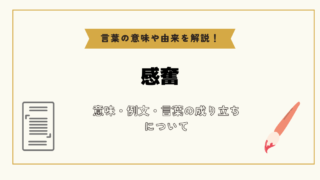Contents
「感酥」という言葉の意味を解説!
「感酥(かんそ)」という言葉は、日本の俳句や短歌などの詩歌において使われる表現です。
これは、「感動して心がふるえる」という意味を持っています。
何か美しい景色や心に響く出来事を経験した際に、心の中で感酥を感じることがあります。
感酥は、人間の感性や人間味を引き出し、作品に深みを与える大切な要素となります。
「感酥」という言葉の読み方はなんと読む?
「感酥」は、”かんそ”と読みます。
この言葉は中国語由来であり、日本の文学界や俳句界で広く使用されています。
日本の詩歌や文学において使われるため、一般的に「感酥」という読み方が広まっています。
「感酥」という言葉の使い方や例文を解説!
「感酥」という言葉は、詩歌を作る際や美しい風景を表現する際に使われます。
例えば、「秋の夕焼けに心が感酥した」というように、心が震えるような美しい光景や情景を表現する際に使用されます。
また、「彼の歌声は私の心に感酥を呼び起こした」というように、音楽や声によって感酥を感じることもあります。
「感酥」という言葉の成り立ちや由来について解説
「感酥」という言葉は、中国の詩歌や文学に由来します。
中国の詩歌では、心が震えるような美しい風景や出来事を表現する際に「感酥」という表現が使われてきました。
その後、日本の文学界に取り入れられ、「感酥」という言葉が広がっていきました。
日本の俳句や短歌などにおいても、心の震えを感じるような表現として使用されるようになりました。
「感酥」という言葉の歴史
「感酥」という言葉の歴史は、中国の詩歌の中に遡ることができます。
中国の詩人たちは心の震えを感じる美しい風景や情景を表現する際に、「感酥」という表現を用いてきました。
この表現は、日本の文学界でも受け入れられ、俳句や短歌などの詩歌においても広く使用されるようになりました。
そのため、「感酥」という言葉は日本の文学において重要な位置を占めています。
「感酥」という言葉についてまとめ
「感酥」という言葉は、日本の俳句や短歌などの詩歌において使われる表現です。
心の震えるような美しい風景や情景を表現する際に使用され、美しい詩や歌を作り上げるための重要な要素となります。
この言葉は中国語由来であり、日本の文学界で広く使用されています。
詩歌の世界で感酥を感じることは、人間味や感性を豊かにするものであり、作品に深みを与えることができます。