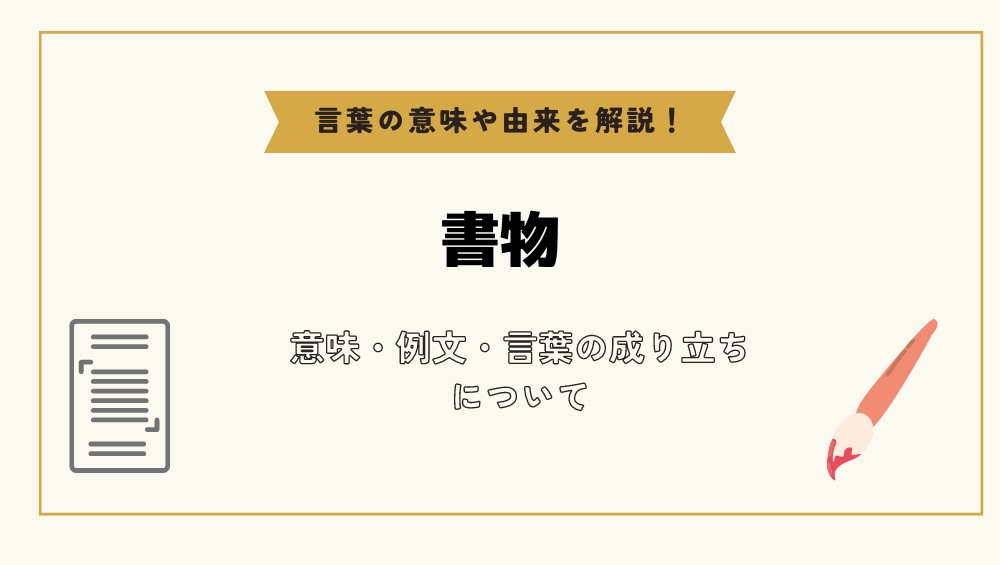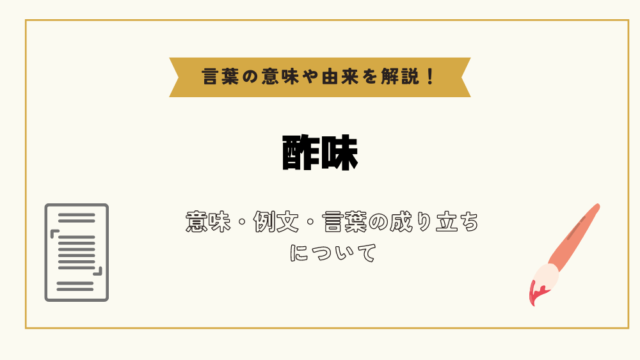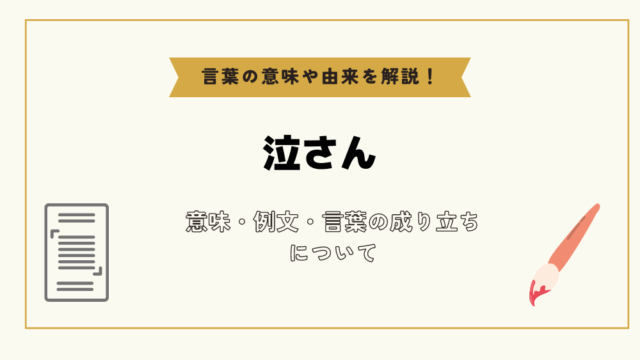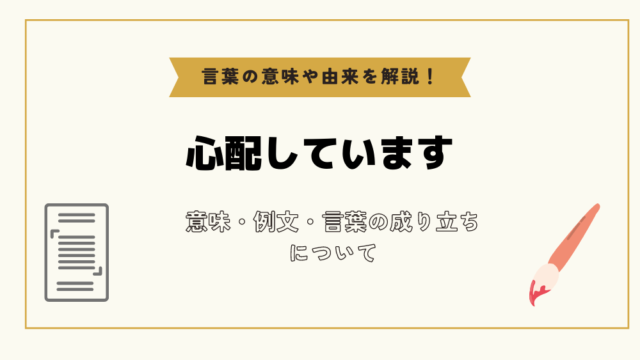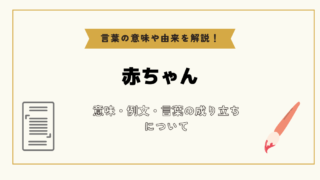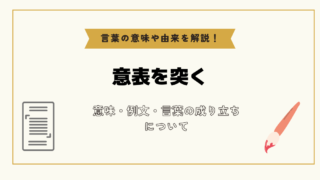Contents
「書物」という言葉の意味を解説!
「書物」とは、文字が書かれた本や資料を指す言葉です。
これには小説や詩集、教科書、辞書など様々な種類があります。
「書物」は知識や情報を伝える手段として、古くから重要な存在とされてきました。
基本的には紙に印刷されたものを指すことが一般的ですが、近年では電子書籍などのデジタルな形式も一般的になってきています。
「書物」の読み方はなんと読む?
「書物」は、日本語の読み方にルールや決まりがあるわけではありません。
一般的には「しょもつ」や「かきもの」と読まれることが多いですが、読み方には地域や個人の好みなどによって変化があります。
実際には「書物」を使う場面で、その場にふさわしい読み方を選ぶことが大切です。
意図が伝わるかどうかを考えつつ、自分の使い方に合わせた読み方を採用しましょう。
「書物」という言葉の使い方や例文を解説!
「書物」という言葉は、特定の本や資料を指し示すために使われます。
例えば、「図書館でたくさんの書物を借りることができる」というように使います。
また、「書物を読むことは知識を広げる良い方法です」といった使い方もあります。
単に「本」という言葉では表現しきれない、書物ならではの重みや質感を求める場合に使われることがあります。
「書物」という言葉の成り立ちや由来について解説
「書物」は、日本語の「書く」と「物」という言葉から成り立っています。
つまり、「文字を書いたもの」という意味になります。
古代から書籍が存在していたこともあり、非常に古い言葉です。
そのため、「書物」という言葉は、文字を書いた記録や文化の保管・伝播に寄与する大切な存在だったことが窺えます。
「書物」という言葉の歴史
「書物」という言葉は、古代から存在していた書籍や資料を指す言葉として使われてきました。
最初の書物は、竹や木の板に文字を刻んで作られたものでした。
時代が進むにつれて、紙の普及や印刷技術の発達により、書物はより一般的になっていきました。
現代では、出版業界や教育分野などで書物が広く利用されています。
「書物」という言葉についてまとめ
「書物」という言葉は、文字が書かれた本や資料を指す言葉です。
紙に印刷されたものだけでなく、電子書籍なども含まれます。
読み方は「しょもつ」や「かきもの」が一般的ですが、地域や個人によっても異なる場合があります。
使い方や例文は、特定の本や資料を指し示す際に使われます。
語源や由来は、「書く」と「物」という言葉から成り立っています。
古代から存在し、発展してきた歴史があります。
書物は、知識や文化の保管・伝播に重要な役割を果たしてきました。
現代でも、書物は私たちの知識や情報を広げる手段として欠かせません。