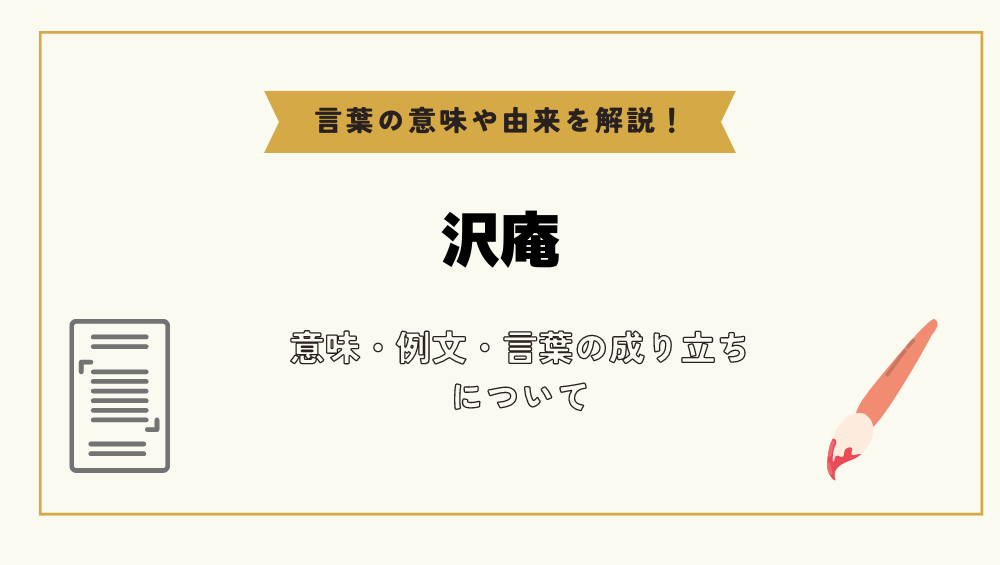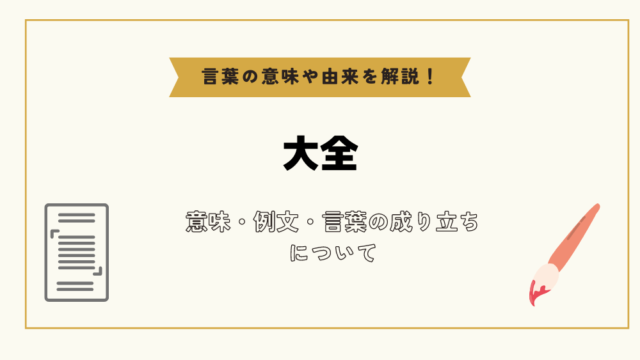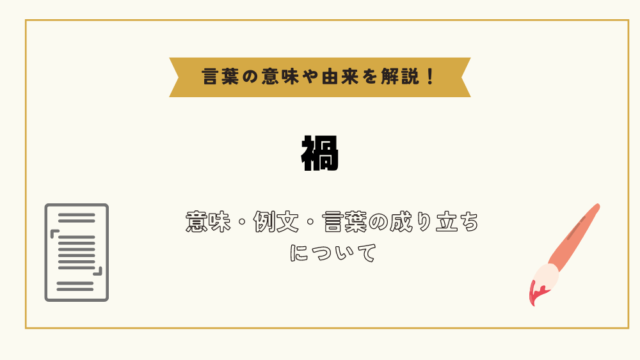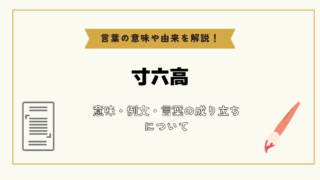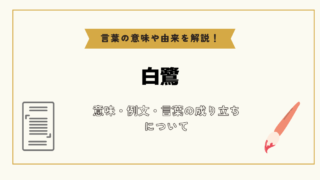Contents
「沢庵」という言葉の意味を解説!
「沢庵」という言葉は、日本の伝統的な漬物の一つで、主に大根を漬けたものを指します。
そのままでも食べられますが、ご飯と一緒に食べることが多いです。
甘酸っぱい味わいが特徴で、他の漬物とは一味違った風味を楽しむことができます。
「沢庵」という言葉の読み方はなんと読む?
「沢庵」という言葉は、読み方は「たくあん」となります。
「たくあん」と読むことで一般的に通じますが、地域によっては「さわあん」とも呼ばれることもあります。
「沢庵」という言葉の使い方や例文を解説!
「沢庵」という言葉は、食べ物の名称としてよく使われますが、他の意味でも使われることがあります。
例えば、「彼の言葉はまるで沢庵のように鋭く辛辣だ」と言った場合、彼の言葉が鋭いことを比喩的に表現しています。
「沢庵」という言葉の成り立ちや由来について解説
「沢庵」という言葉の成り立ちや由来は、江戸時代に遡ることができます。
元々は、中国から伝わった「懐石料理」に登場するようになり、その後、日本独自の漬物として定着しました。
字面から想像すると、大根を漬けるための「庵(あん)」という場所にいくつかの「沢(さわ)」があったことが由来とされています。
「沢庵」という言葉の歴史
「沢庵」という言葉の歴史は、江戸時代にまで遡ることができます。
当時は、庶民の間で親しまれるようになりました。
その後、明治時代以降には、広く一般的な漬物として全国で知られるようになりました。
現代でも、多くの家庭や料理店で愛される漬物として根強い人気を持っています。
「沢庵」という言葉についてまとめ
「沢庵」という言葉は、日本の伝統的な漬物であり、大根を主成分としています。
「たくあん」と読みますが、「さわあん」とも呼ばれることもあります。
食べ物の名称として使われるだけでなく、比喩表現としても使われることがあります。
その歴史は古く、江戸時代から庶民の間で親しまれてきました。
現代でも多くの人々に愛される美味しい漬物です。