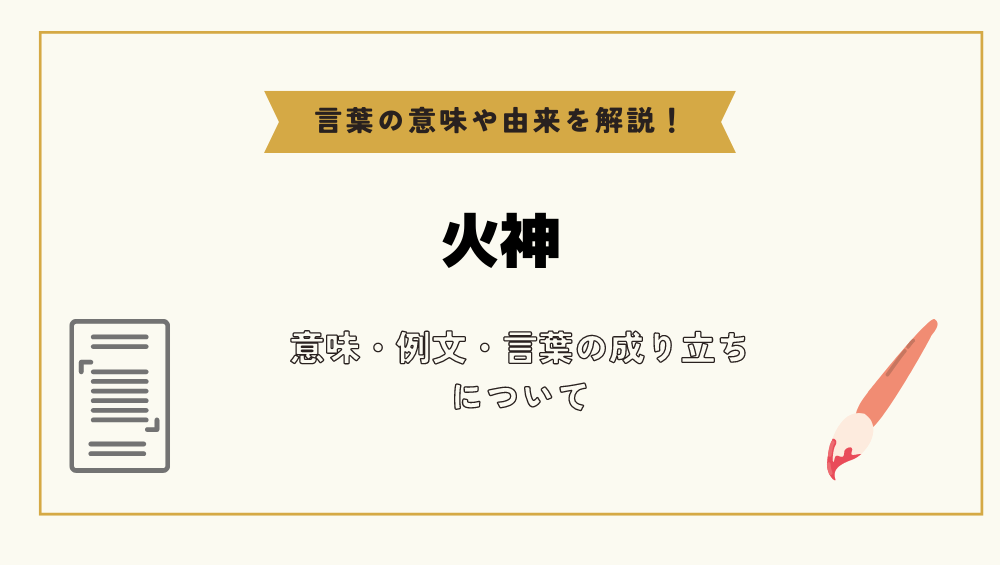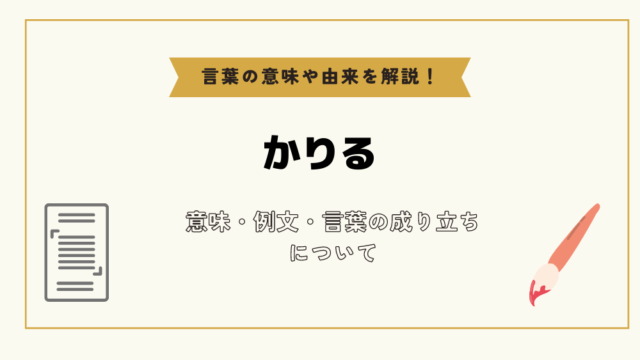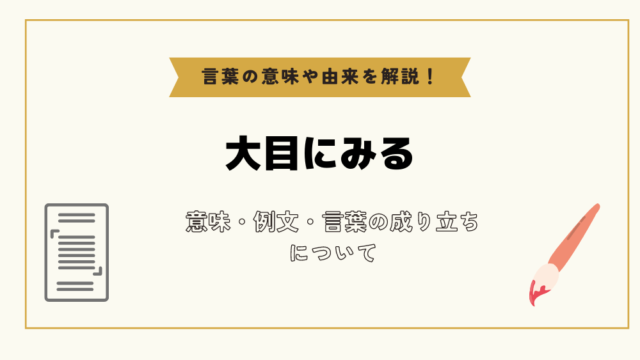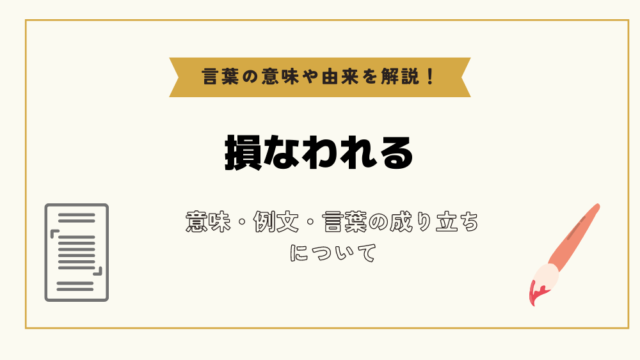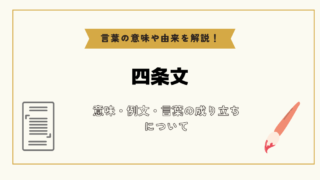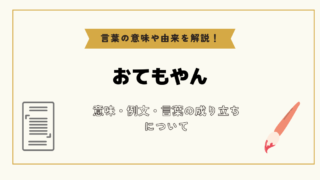Contents
「火神」という言葉の意味を解説!
「火神」という言葉は、文字通り「火を司る神」という意味を持ちます。
古代の信仰で、人々は火を神聖な存在として崇めていました。
火は人々の生活を支えるものであり、また暖かさや明かりをもたらすものでもありました。
そのため、「火神」という言葉は尊敬の念を含み、神聖視されていました。
「火神」という言葉の読み方はなんと読む?
「火神」という言葉は「かみつき」と読みます。
日本語の読み方として一般的なものです。
この読み方は古くから伝わり、神道における火神信仰をはじめ、様々な文化や信仰においても使用されています。
「火神」という言葉の使い方や例文を解説!
「火神」という言葉は、神話や伝説、文学作品などの表現に使われることがあります。
例えば、「彼はまるで火神のような情熱を持って仕事に取り組んでいる」というように使うことができます。
また、神社や寺院での祭りや儀式においても「火神」を祭り上げることがあります。
「火神」という言葉の成り立ちや由来について解説
「火神」という言葉の成り立ちや由来は多岐にわたります。
古代の日本では、火を大切な生命力や浄化の象徴と考えており、それが「火神」という言葉につながりました。
また、神道信仰や山岳信仰においても火を神聖視する考え方が広まり、さまざまな神話や伝説も「火神」という概念に結びついています。
「火神」という言葉の歴史
「火神」という言葉の歴史は古いものです。
日本の古代史や神話においても、「火神」は重要な存在であり、信仰や儀式において頻繁に登場します。
また、火を使った暖房や調理の技術が進化するにつれて、「火神」に対する関心や感謝の念も深まっていきました。
「火神」という言葉についてまとめ
「火神」という言葉は、火を司る神や火にまつわる神聖な存在を指します。
古代から人々は火を重要視し、それを神聖視してきました。
そのため、「火神」は尊敬や畏敬の念を込めて使われることがあります。
また、日本の伝説や神道信仰においても重要な役割を果たし、多くの人々に愛されてきました。