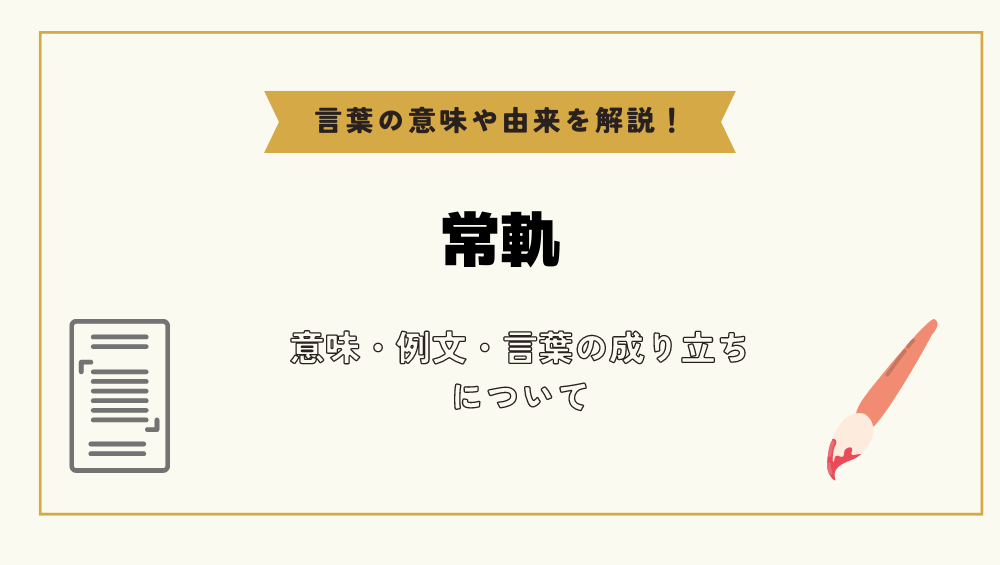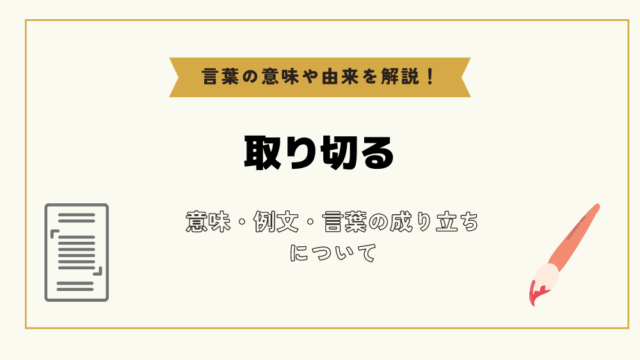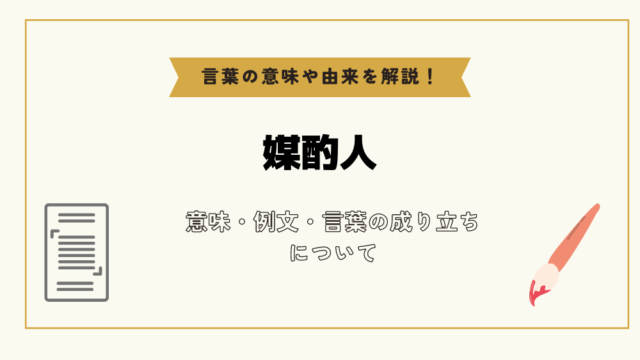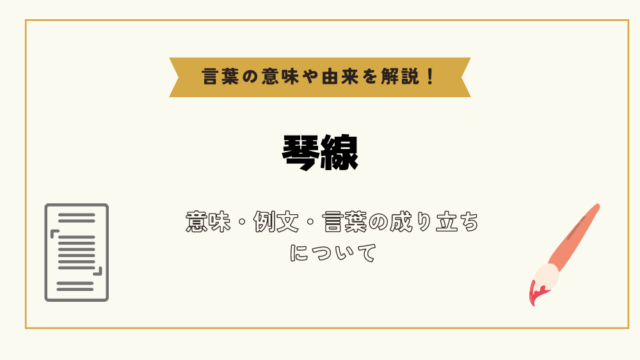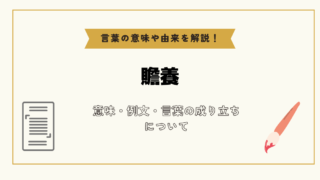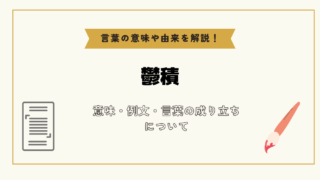Contents
「常軌」という言葉の意味を解説!
「常軌」という言葉は、普通や通常の基準や規範を指す言葉です。
何かしらの行動や状態が、一般的な基準や社会的なルールに合っているかどうかを判断するときに使用されます。
常軌から逸脱した行動や考え方は、社会的に非常に異常と見なされることがあります。
たとえば、法律に違反していたり、倫理や道徳に反するような行為は、常軌を逸脱しているといえるでしょう。
「常軌」という言葉の読み方はなんと読む?
「常軌」という言葉は、「じょうき」と読みます。
漢字の「常」は「つね」と読むことが一般的ですが、「常軌」の場合は「じょう」と読みます。
「軌」は「き」と読みます。
「常軌」という言葉の使い方や例文を解説!
「常軌」という言葉は、一般的に文章や話し言葉で使われます。
例えば、「彼の行為は常軌を逸脱している」と言うことで、その人の行動が普通ではなく、非常に異常であることを表現することができます。
また、「社会の常軌を守る」という表現では、社会的なルールや常識に従って行動することを意味します。
このように「常軌」は、一般的な基準や規範を守ることを強調する場合に使われます。
「常軌」という言葉の成り立ちや由来について解説
「常軌」という言葉は、中国の古典や仏教の教えから由来しています。
中国では「常軌」という概念は、人々が社会的な規範を守ることや普通の生活を送ることを重んじる価値観に関連しています。
日本においても、この中国由来の概念が継承され、使われるようになりました。
「常軌」という言葉の歴史
「常軌」という言葉の歴史は古く、江戸時代から存在しています。
当時の日本は、儒教の影響を強く受けており、儒教思想において「常軌」という概念は非常に重要視されました。
その後も、明治時代以降も「常軌」という言葉は使われ続け、現代に至ってもその意味や使われ方は変わっていません。
「常軌」という言葉についてまとめ
「常軌」という言葉は、社会的な基準や規範を表現するために使われます。
常軌を逸脱する行動や考え方は、一般的に異常と見なされます。
日本では儒教の影響を受けており、中国由来の概念として定着しています。
江戸時代から現代まで使われ続けており、その意味や使われ方は変わっていません。