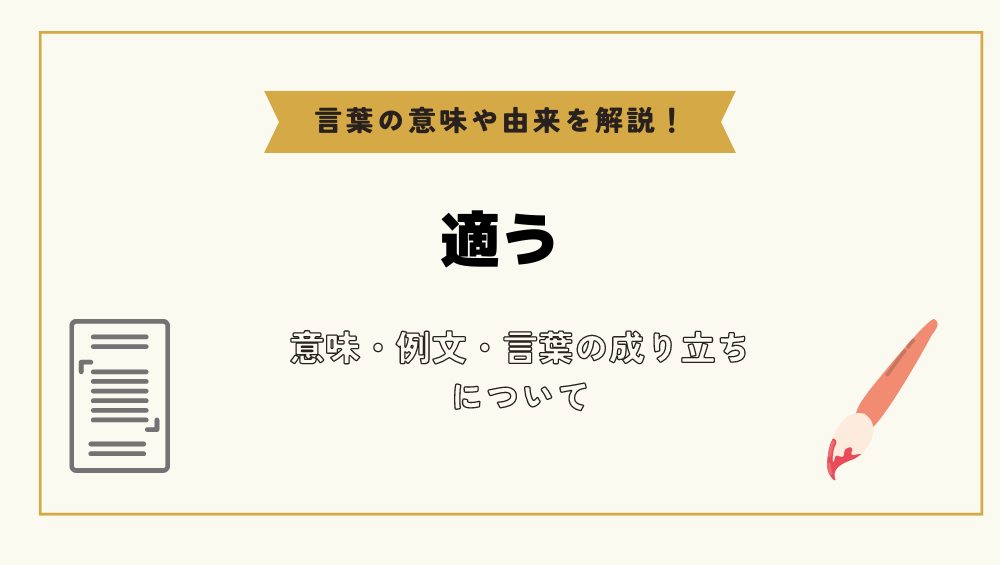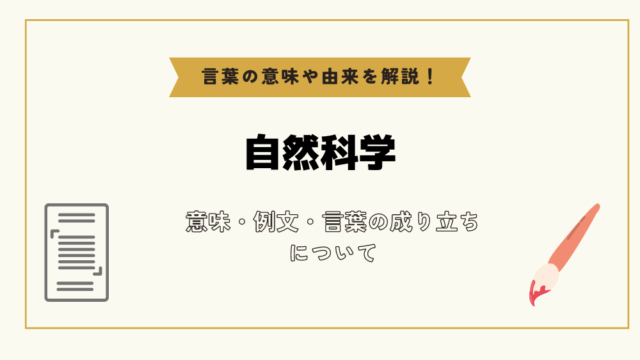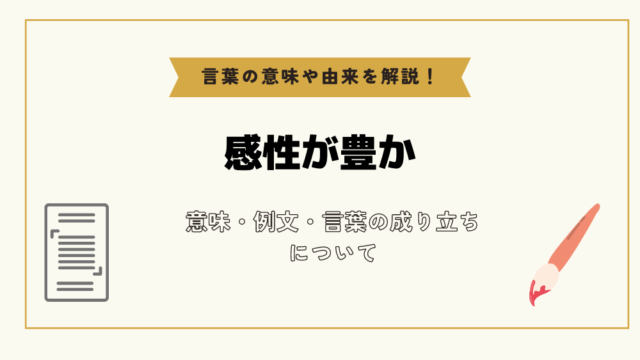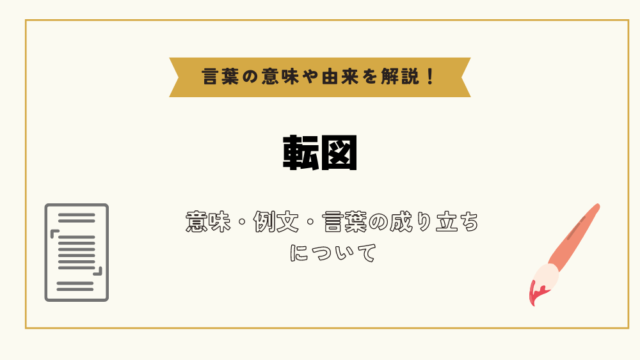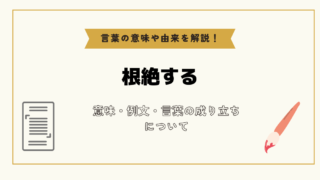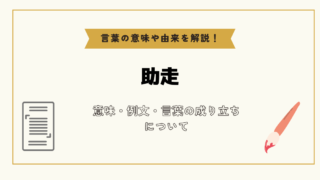Contents
「適う」という言葉の意味を解説!
「適う」という言葉は、物事がぴったり合う、適正な状態や条件になることを意味します。
例えば、ある人がある職業に向いていると言われる場合、その職業に「適っている」と表現することがあります。
また、課題や問題に対して最適な解決策が見つかることも、「適う」と言います。
「適う」は、物事が適切に成立することや適応することを意味し、その状態や条件に合致することを強調して表現します。
「適う」という言葉の読み方はなんと読む?
「適う」という言葉は、読み方は「かなう」となります。
この「かなう」という読み方は、古くから使われてきた表現であり、広く一般的に使われています。
しかし、現代の日本語ではあまり使われず、やや古風な言葉とも言えます。
「適う」という言葉の使い方や例文を解説!
「適う」という言葉は、さまざまな場面で使うことができます。
例えば、「この仕事には彼女の能力が適っている」と言えば、彼女の能力がその仕事に最適であることを表現しています。
また、例えば「この計画は予定通りに適わなかった」と言えば、計画が予定通りに成果を上げることができなかったことを意味します。
「適う」は、物事の適性や適応度を表現する場合に使われる言葉であり、その特徴や能力がぴったり合うことを強調します。
「適う」という言葉の成り立ちや由来について解説
「適う」という言葉の成り立ちや由来については、はっきりとした情報はありません。
ただし、「かなう」という読み方は古代の日本語に由来しており、それが現代の日本語で「適う」と表現されていると考えられます。
言葉の成り立ちや由来については詳細は不明ですが、その意味と使い方は日本語の特徴的な表現として広く使われています。
「適う」という言葉の歴史
「適う」という言葉の歴史は、古代から使われてきたと考えられています。
古代の文献や歌の中にも、「適う」という表現が見られます。
これは、物事の調和や適合性を表現するために用いられたものです。
現代の日本語ではあまり使われず、やや古風な言葉とも言えますが、それでも文学や詩歌などでは時折見られる表現です。
「適う」という言葉についてまとめ
「適う」という言葉は、物事がぴったり合う、適正な状態や条件になることを意味します。
その読み方は「かなう」となり、古風な表現とも言えますが、日本語の特徴的な表現として広く使われています。
「適う」は、自分や他の人の特徴や能力がうまく生かされ、物事が適応することを強調する場合に使われます。
文学や詩歌などでも見られる表現であり、その歴史は古代から続いています。
「適う」という言葉は、言葉での表現によって理解しやすく、その意味や使い方は広く一般的です。