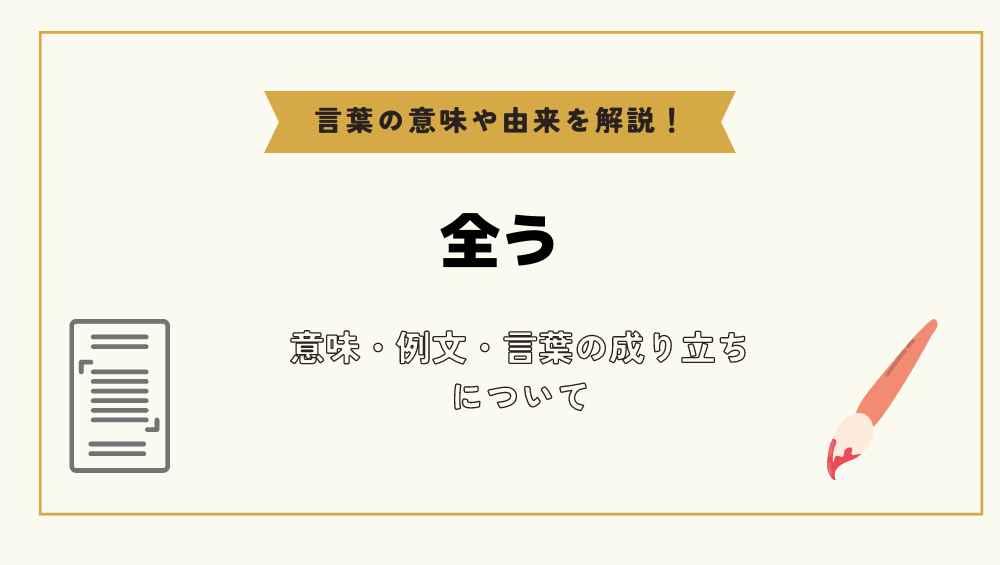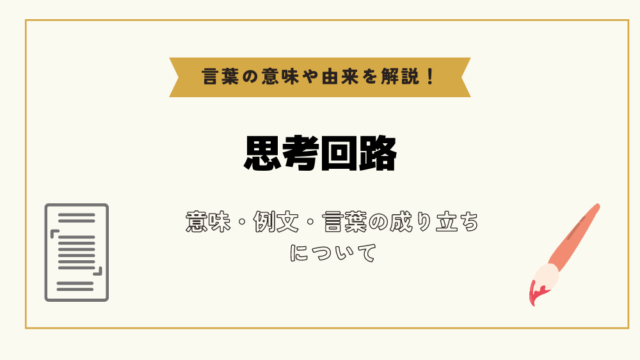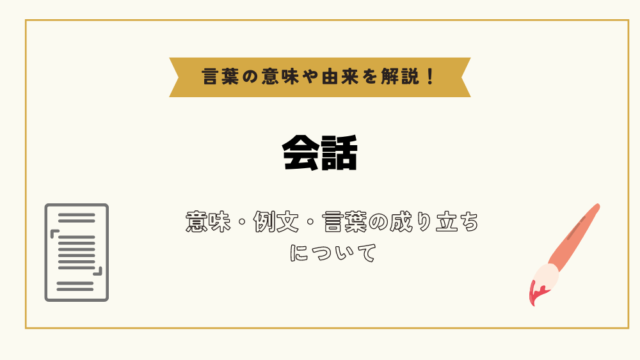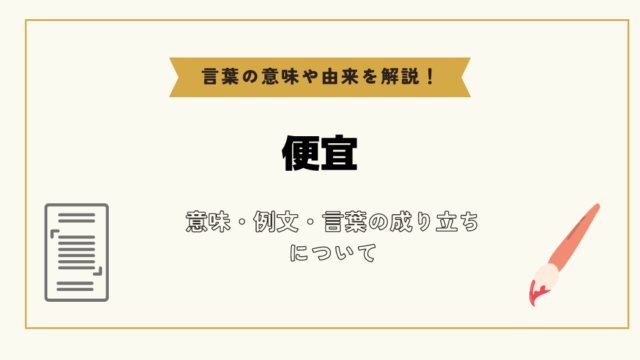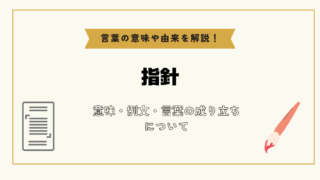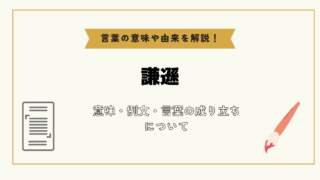「全う」という言葉の意味を解説!
「全う」は漢字のとおり「全く(まったく)欠けていない」状態を示す言葉で、「完全である」「十分である」という形容動詞的な意味と、「任務をやり遂げる」「目的を果たす」という動詞的な意味の二面性を持っています。日常的には後者の「やり遂げる」ニュアンスで耳にすることが多いですが、古語的な文章や法律文では形容動詞的にも機能しています。特に現代日本語では「責任を全うする」「使命を全うする」のように、与えられた役割を最後まで果たす意で使うのが一般的です。
語源的にも「全」はすべてを欠けなく備えたさま、「う(乎)」は状態を表す接尾辞とされ、セットで「万全の状態」を示す語が生まれました。そこから「完全な状態に仕上げる」「満足いくまで成し遂げる」という動作的な意味が派生し、今日まで受け継がれているのです。なお「全う」は「まとも」と読み替えて「正しい」「筋が通っている」を含意する場合もあり、文脈で意味の振れ幅が見られます。
司法・行政分野では「権限を全うする」「義務を全うする」のように、契約・法律上定められた責務を履行しているかどうかを示す指標として機能します。そのため、公文書では「完全履行」と同義で扱われることも少なくありません。学術的に見ると「全う」は「プロセスの完結」と「品質の充足」という二つの観点を一語で包含する、便利かつ濃密な語彙だといえます。
ビジネス領域では「プロジェクトを全うする」は「納期・品質・コストすべてを満たして完了させる」ニュアンスが含まれ、単なる終了とは一線を画します。「終わる」と「全うする」には達成度の開きがある点を押さえておきましょう。
「全う」の読み方はなんと読む?
「全う」は通常「まっとう」と読みます。歴史的仮名遣いでは「まつたう」と発音されていた時期もありましたが、現代仮名遣いの改訂で清音化されました。日常会話でも文章でも「まっとう」で通じるため、他の読み方を覚える必要は基本的にありません。
ただし古典文学や一部の雅文では「ぜんとう」と読ませる例も見受けられます。これは「全」を漢音読みしたうえで語尾の「乎」を音読する形で、主に学術的注釈の中で確認できます。とはいえ現代日本語の運用上、「ぜんとう」と読むと誤読と判断されることが多いため注意しましょう。
パソコンやスマートフォンの変換でも「まっとう」で「全う」が第一候補に上がるIMEがほとんどです。変換ミス防止の観点でも、正しい読みを押さえておくとスムーズに入力できます。「まとも」と入力して変換すると「正当」「健全」といった別の単語が出てくるため、表記ゆれが起こらないようにしましょう。
「全う」という言葉の使い方や例文を解説!
「全う」は名詞+を+全うする、という構文で使うのが最も標準的です。このとき前に置かれる名詞は「責任」「使命」「義務」「人生」「役割」など、完遂すべき内容を示す言葉が多く選ばれます。途中で投げ出すのではなく「最後までやり切る」意図を込めたいときに「全う」を使うと、文意が一層明確になります。
【例文1】彼は与えられた職務を全うし、プロジェクトを成功に導いた。
【例文2】医師としての責任を全うするために、最新の医学知識を学び続けている。
また形容動詞的に「全うな」の形で用い、「まっとうな意見」「まっとうな手段」のように「筋が通っている」「正当である」という評価を示す文も頻出です。ビジネス文書やプレゼン資料では「まっとうな根拠」「まっとうな市場調査」という言い回しが説得力を高めます。口語では「まとも」と置き換えられる場合が多いですが、文章語としては「全う」がよりフォーマルに響きます。
注意点として、やり遂げたかどうか確定していない事柄には基本的に用いません。例えば「やる予定の仕事を全うする」は未来志向で意味が通りますが、「やるかもしれない仕事を全うする」では語の重みが合わず違和感が生じます。目的語を慎重に選ぶと誤用を防げます。
「全う」という言葉の成り立ちや由来について解説
漢字「全」は「玉を傷つけずに取り出す様子」を象った字とされ、転じて「欠けるところがない」「完全」という概念を担うようになりました。中国最古級の字書『説文解字』にも同趣旨の説明があり、日本へは4〜5世紀頃に仏教経典とともに伝来したと推定されています。平安期には「全し(まったし)」が形容詞として定着し、そこに動作性を帯びた助動詞的「ふ(侑)」が付いて「まったう」と読まれたのが現在の「全う」につながると考えられています。
さらに鎌倉時代には武家社会の台頭により「武士の本懐を全うする」のような表現が出現し、武功・忠義を果たす語として一般化しました。この過程で「まっとうする」という動詞的成分が強調され、完遂・達成のイメージが広がったのです。
江戸期には商人階級の勃興とともに「契約を全うする」「年季を全うする」といった実務的な文例が増えました。明治以降は法律用語や軍事用語としても採用され、制度面でも用例が蓄積されています。こうした歴史的変遷をたどると、語の核にある「欠けないこと」と「やり遂げること」が一貫している点が浮かび上がります。
「全う」という言葉の歴史
「全う」は奈良・平安期の文学作品にはあまり見られず、室町期の軍記物語や宗教文書で頻出し始めたと確認されています。例えば『太平記』では「その志、終に全うせざりけり」といった表現が登場し、志望が完遂されなかった嘆きを強調しています。中世以降の武家文化が「全う」を普及させた大きな要因であり、武士の忠節・名誉という価値観が語の重厚さを形づくりました。
近世になると寺子屋教育の普及で読み書きが一般化し、庶民も「全う」を用いるようになります。歌舞伎や浄瑠璃では「孝行を全うせよ」と親子の情愛を説く台詞が残り、道徳語としての位置付けが高まりました。明治期の翻訳文学では「fulfil」「accomplish」の訳語として採用され、西洋概念と結び付いた広がりを見せます。
第二次世界大戦後は「国民の義務を全うする」「勤労を全うする」といった憲法・教育基本法関連の語彙として登場し、新聞・教科書を通じて再定義された経緯があります。現代ではビジネス、スポーツ、医療など多方面で定着し、世代を問わず理解される語となりました。こうして千年以上にわたる用例の蓄積が、「全う」という一語を普遍的な価値語へと押し上げたのです。
「全う」の類語・同義語・言い換え表現
「全うする」の類語としてまず挙げられるのが「遂行する」「完遂する」「履行する」です。これらはいずれも「任務や計画を最後までやり遂げる」意味を共有していますが、ニュアンスに微妙な差があります。「遂行する」はプロセス重視、「完遂する」は結果重視、「履行する」は契約や法的義務を果たすニュアンスが強い点が特徴です。
形容動詞「全うな」と同義で使える言葉には「健全な」「正当な」「まともな」「適切な」などがあります。文章のトーンや文脈に合わせ、柔らかく言い換えたい場合は「まともな」、堅い文章では「正当な」を選ぶと自然です。
動詞型では「やり抜く」「成し遂げる」「やり切る」も近い意味を持ちます。ただし口語的なカジュアル度が増すため、ビジネス文書では「全うする」のほうが好まれる傾向があります。目的語に「責任」を置く場合は「果たす」よりも「全うする」の方が「欠けなく・完全に」という含意が強まり、責任感の強さを強調できます。
「全う」の対義語・反対語
「全う」の対義語を考える際、まず焦点を当てるべきは「完全」「完遂」というコア概念を否定する語です。「途中でやめる」を示す「中断する」や「放棄する」が最も直接的な反対語となります。義務や責任の文脈であれば「怠る」「不履行」「未完」が対義語として機能します。
形容動詞的な「全うな」の反対は「不当な」「不健全な」「不適切な」「いびつな」などの語が挙げられます。これらはいずれも「欠陥がある」「筋が通っていない」ニュアンスを帯びています。文章中で対比を行う場合は、「全うな意見に対し、彼の主張は不当だ」のように使うと分かりやすい対照構造が生まれます。
なお単に「終わらなかった」という事実を述べたいだけならば「未完成」「失敗」「頓挫」といった語も対義的に機能しますが、これらは「全う」の道徳的・価値的側面には必ずしも立ち向かっていません。「全う」という言葉が持つ「道義的に正しい」という裏の含意を踏まえると、対義語選択にも慎重さが求められます。
「全う」を日常生活で活用する方法
仕事だけでなく、私生活でも「全う」という言葉は意識的に取り入れると目標達成のマインドセットづくりに役立ちます。例えば「今日の家事を全うする」「年間読書計画を全うする」と宣言することで、達成基準が「やるかやらないか」ではなく「全て終えたかどうか」に変わります。言葉にするだけで「途中で諦めない」という自己暗示が働き、行動の質が高まるという心理学的効果も期待できます。
また育児や介護の場面で「親としての責務を全うしたい」と自覚的に語ることで、家族間の共通認識が生まれやすくなります。言葉の重みが行動規範を引き締め、無理な状況でも支え合うモチベーションを共有しやすくなるからです。
趣味や学習でも「英語学習を全うする」「マラソン練習計画を全うする」のように使うと、途中で挫折しがちな場面に自律的なブレーキが働きます。スマートフォンのリマインダーや手帳に「全う」という言葉を添えて記録すると、視覚的プレッシャーが継続意識を高めるコツになります。
「全う」についてよくある誤解と正しい理解
まずありがちな誤解は、「全うする=終わらせるだけ」と短絡的に解釈してしまう点です。「終了」はプロセスを問わずとも可能ですが、「全う」は質を担保したうえでの完遂を前提としており、結果だけを指すわけではありません。例えば試験を受けて答案を提出しただけでは「受験を全うした」とは言えず、合格ラインへの到達や学習計画の完遂が伴って初めて「全うした」と評価されます。
二つ目の誤解は、形容動詞的な「全うな」を「まとも」と混同しすぎる点です。「まとも」は口語的で幅広い状況に使えますが、「全うな」はやや格式があり、論文・レポート・公式文書で好まれます。場面に応じた語の格調を読み違えると、伝えたい温度感がズレる原因になります。
さらに「全う」は高尚な言い回しで日常言語としては堅すぎるというイメージもあります。しかし「人生を全うする」は新聞や弔辞で定番の表現ですし、ビジネス書でも頻繁に登場します。適切な文脈をつかめば、決して敷居の高い言葉ではなく、むしろ芯の通った文章を作る頼もしい語彙です。
「全う」という言葉についてまとめ
- 「全う」は「欠けるところがなく、最後までやり遂げる」意味を持つ語である。
- 読み方は現代仮名遣いで「まっとう」と読むのが一般的である。
- 平安期の「全し」が語源とされ、中世以降に武士文化で広がった歴史を持つ。
- 責任や使命を表す名詞とともに用い、未完の事柄には使わない点に注意する。
「全う」という言葉は、単に何かを終わらせる以上の重みを帯びています。欠ける部分なく、質を保証しつつ完遂するという厳格な価値基準が語の中心に存在するためです。特に「責任を全うする」「人生を全うする」といった表現では、人としての誇りや覚悟まで含意されます。
また読み方は「まっとう」一択と覚えておけば変換ミスも防げます。歴史的背景を知ることで「全う」が持つ格式や重厚さを踏まえ、ビジネスから日常生活まで幅広く活用してみてください。筋の通った行動や発言を支える言葉として、日々の語彙に取り入れる価値は十分にあります。