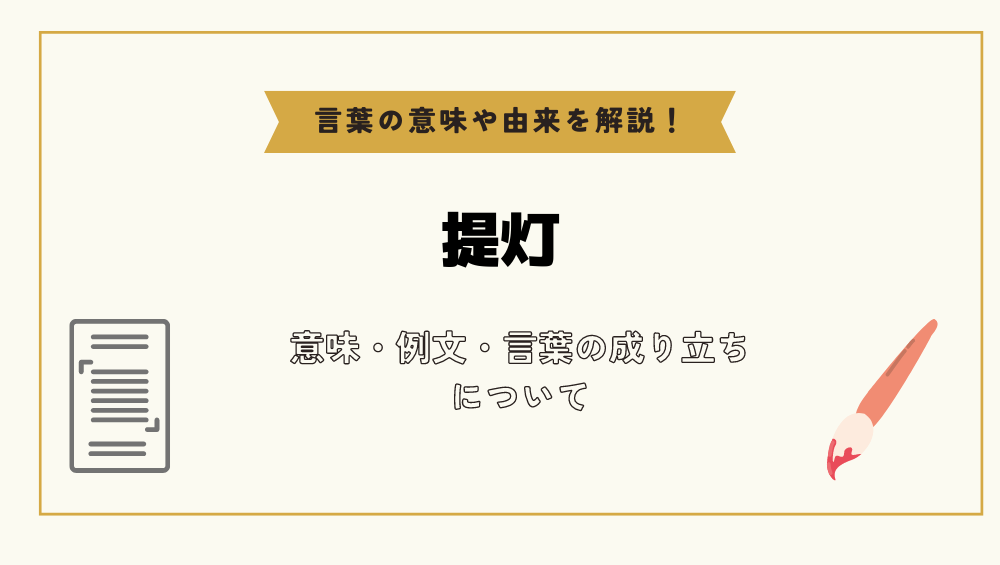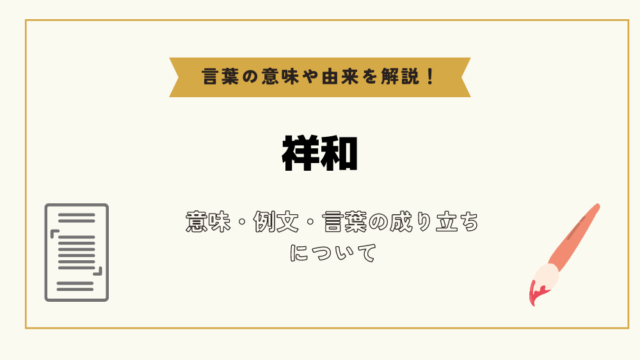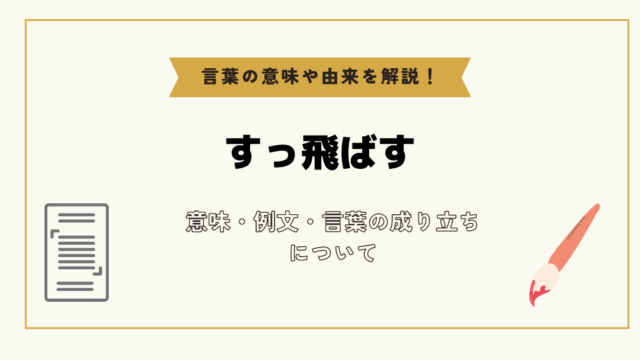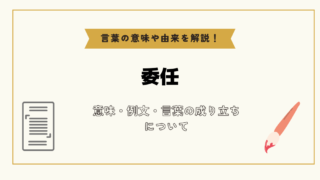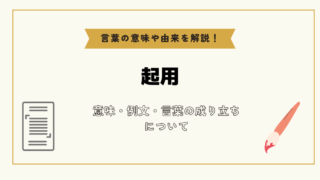Contents
「提灯」という言葉の意味を解説!
提灯(ちょうちん)とは、日本の伝統的な照明器具のことを指します。
灯りを包み込むような形状で、紙でできた袋状の部分にろうそくや電球を入れることで光を放ちます。
提灯は、祭りやお祝い事、店舗の看板などでよく見かけることがあります。
「提灯」という言葉の読み方はなんと読む?
「提灯」という言葉は、「ちょうちん」と読みます。
漢字の「提」は「さげる」という意味で、「灯」は「あかり」という意味です。
つまり、「さげる灯」という意味になります。
「提灯」という言葉の使い方や例文を解説!
「提灯」という言葉は、主に祭りやお祝い事など特別な場面で使われます。
例えば、「祭りの会場には、大小さまざまな提灯が飾られていた」という風に使います。
また、和風の雰囲気や日本らしさを表現する際にも、「提灯を使って店内を彩る」などと表現することがあります。
「提灯」という言葉の成り立ちや由来について解説
「提灯」という言葉の成り立ちは、中国の文化から日本に伝わったと言われています。
当初は宗教儀式で使用されることが多く、やがて祭りや行事、商業の世界にも広まりました。
また、提灯は災厄を避けるお守りとしても使われ、縁起物としての意味合いも持っています。
「提灯」という言葉の歴史
提灯の歴史は古く、奈良時代には既に存在していました。
当初は宗教的な儀式で使われることが多く、やがて民間の祭りや行事でも使用されるようになりました。
江戸時代に入ると、提灯は商業の世界に活用され、店舗の看板や広告としても重宝されました。
その後、明治時代以降も提灯の形状やデザインは進化し、現代でも伝統的な雰囲気を持った提灯が使われています。
「提灯」という言葉についてまとめ
「提灯」という言葉は、日本の伝統的な照明器具を指す言葉です。
祭りやお祝い事などの特別な場面でよく見かけることがあります。
読み方は「ちょうちん」といい、中国から伝わったとされています。
提灯の歴史は古く、奈良時代から存在しています。
現代でも伝統的な雰囲気を持つ提灯が使用され、和風の雰囲気を演出する重要な要素となっています。