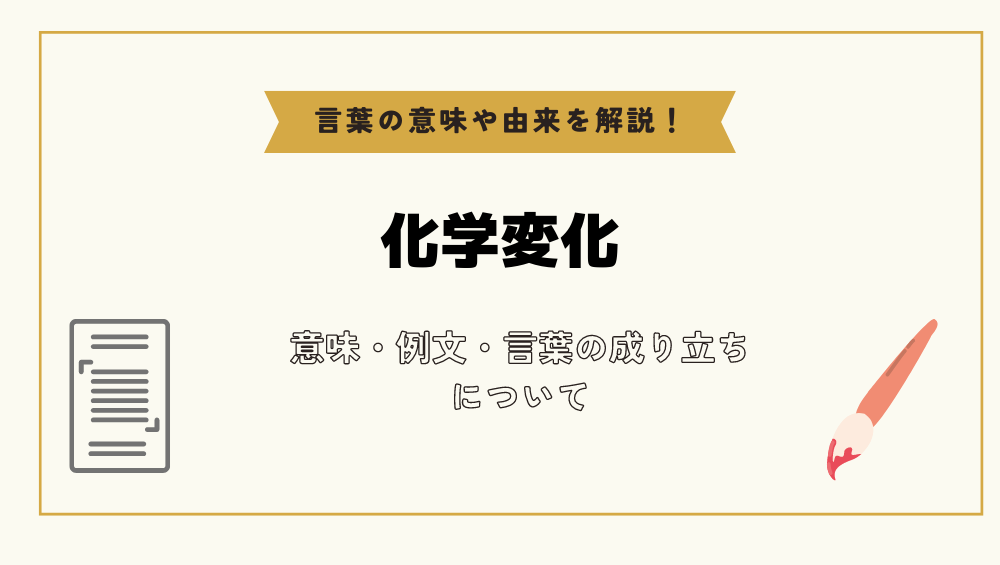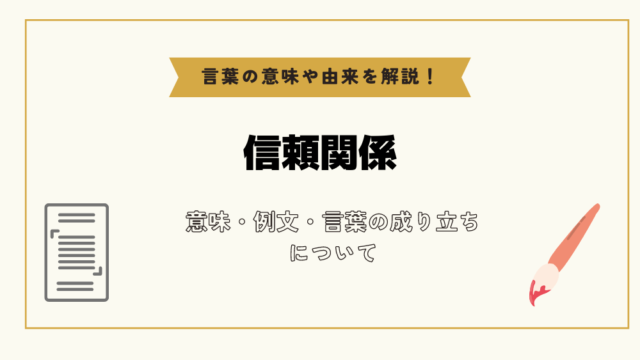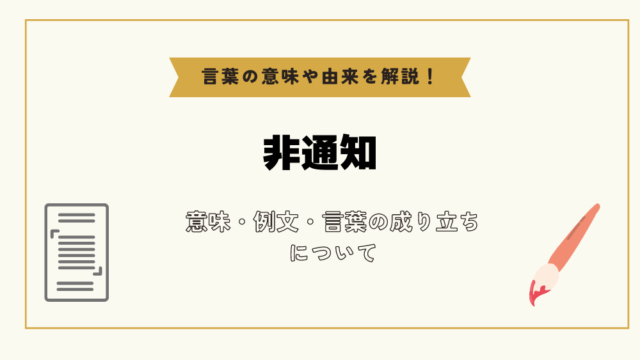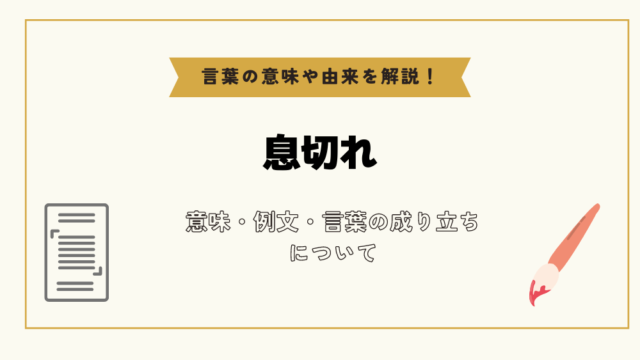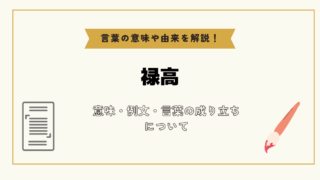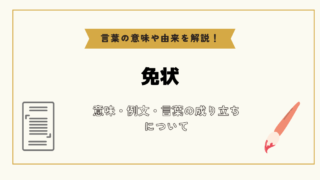Contents
「化学変化」という言葉の意味を解説!
「化学変化」という言葉は、化学的な反応や物質の性質の変化を指す言葉です。
物質が他の物質と反応して結合が変化し、新たな物質が生成されることを指します。
例えば、水素と酸素が反応して水が生成されることなどが化学変化の一例です。
「化学変化」という言葉の読み方はなんと読む?
「化学変化」という言葉は、「かがくへんか」と読みます。
日本語の読み方ですので、読みやすく親しみやすさを意識してみました。
「化学変化」という言葉の使い方や例文を解説!
「化学変化」という言葉は、科学関連の文献や学術論文、化学の教科書などでよく使われます。
例えば、「酸と塩基の反応は化学変化を引き起こす」といった表現が一般的です。
また、化学変化の具体的な例としては、「二酸化炭素の放出や色の変化が見られることがあります」といった文脈でも使用できます。
「化学変化」という言葉の成り立ちや由来について解説
「化学変化」という言葉の成り立ちは、漢字の「化学」と「変化」の組み合わせです。
古代ギリシャで「化学」の語源となった「χημεία」(ケメイア)は、エジプトの都市名であるケメを由来としています。
また、「変化」は日本語の古語であり、物質の性質や形態の変動を意味しています。
「化学変化」という言葉の歴史
「化学変化」という言葉は、近代化学の発展とともに使われるようになりました。
18世紀の化学革命によって、化学の研究が進み、物質の変化や反応についての知見が深まりました。
それに伴い、「化学変化」という言葉が定着しました。
「化学変化」という言葉についてまとめ
「化学変化」という言葉は、化学的な反応や物質の性質の変化を表す言葉です。
日本語で「かがくへんか」と読み、化学の文脈ではよく使われます。
古代ギリシャの「化学」と、日本語の古語である「変化」の組み合わせで成り立ち、近代化学の発展によって定着しました。