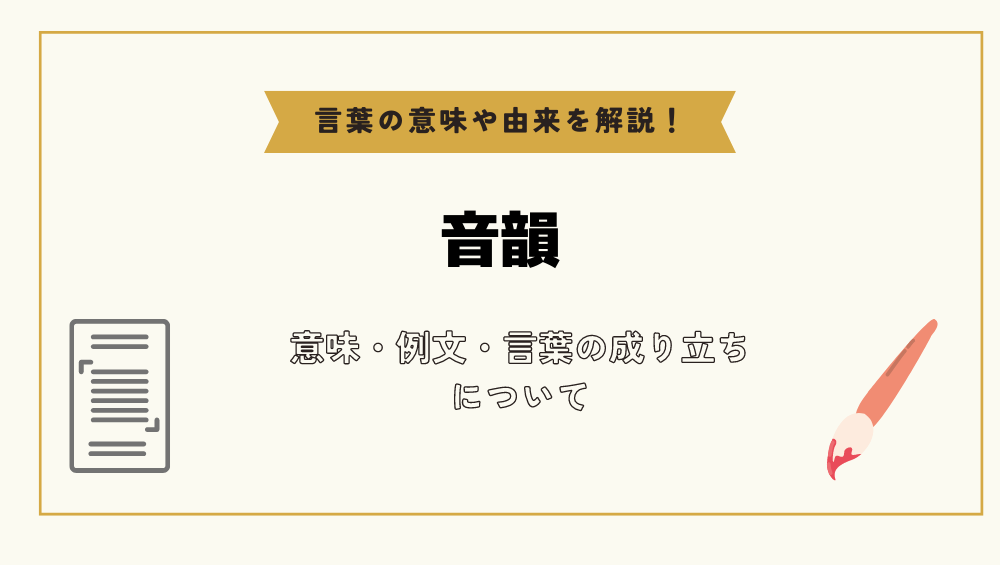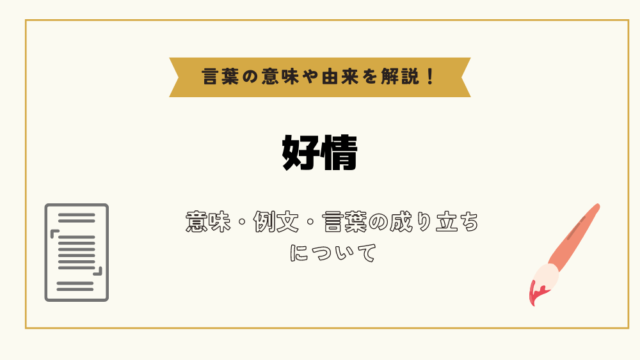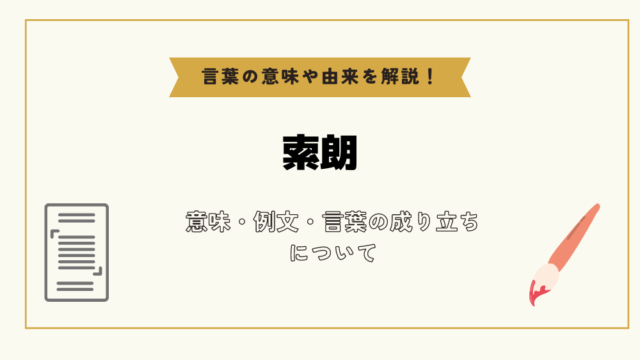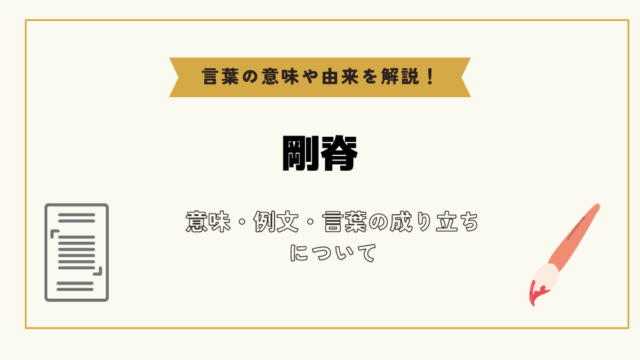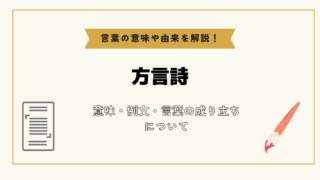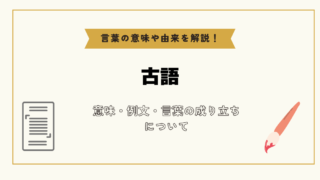Contents
「音韻」という言葉の意味を解説!
音韻とは、言語学の用語で、言葉の音の組み合わせや調子のパターンを指します。
具体的には、発音の特徴やルール、音の変化の仕方などを研究する分野です。
音韻は言語における重要な要素であり、言葉の意味や文法にも関わっています。
言語の音韻を解析することで、その言語の個性や文化、歴史を理解することができます。
「音韻」という言葉の読み方はなんと読む?
「音韻」という言葉は、おんいんと読みます。
日本語には四つの音(あいうえお)がありますが、それぞれの音を一つずつ組み合わせた読み方です。
日本語の読みやすさを考えると、この読み方が一般的です。
「音韻」という言葉の使い方や例文を解説!
「音韻」という言葉は、言語学の分野で使用されることが多いです。
例えば、「この言語は音韻の仕組みが複雑である」という場合、その言語の音のルールや変化の仕方が複雑であることを指しています。
また、「音韻による文章の響きを意識する」という場合は、言葉の音の組み合わせやリズムを考慮して文章を書くことを意味します。
「音韻」という言葉の成り立ちや由来について解説
「音韻」という言葉は、漢字の「音」と「韻」から成り立っています。
漢字の「音」は、音や声を意味し、「韻」は、詩や歌の響きやリズムを指します。
言語学の分野で使用されるようになった経緯は詳しくわかりませんが、言葉の音の特徴やルールを研究する分野として、この言葉が使われるようになったのでしょう。
「音韻」という言葉の歴史
「音韻」という言葉の歴史については、具体的な情報はわかりません。
しかし、言語は人々の意思疎通や文化の継承において重要な役割を果たしてきたため、音のルールや特徴を研究する分野として、古くから存在していた可能性があります。
近年では、技術の進化により、音韻の研究がより詳細に行われるようになりました。
「音韻」という言葉についてまとめ
「音韻」という言葉は、言語学の分野で重要な概念です。
言語の音の特徴やルール、音の変化の仕方を研究することで、その言語の個性や文化を理解することができます。
また、文章や詩などの響きにも関係しており、意思疎通や文化の継承においても重要な役割を果たしています。