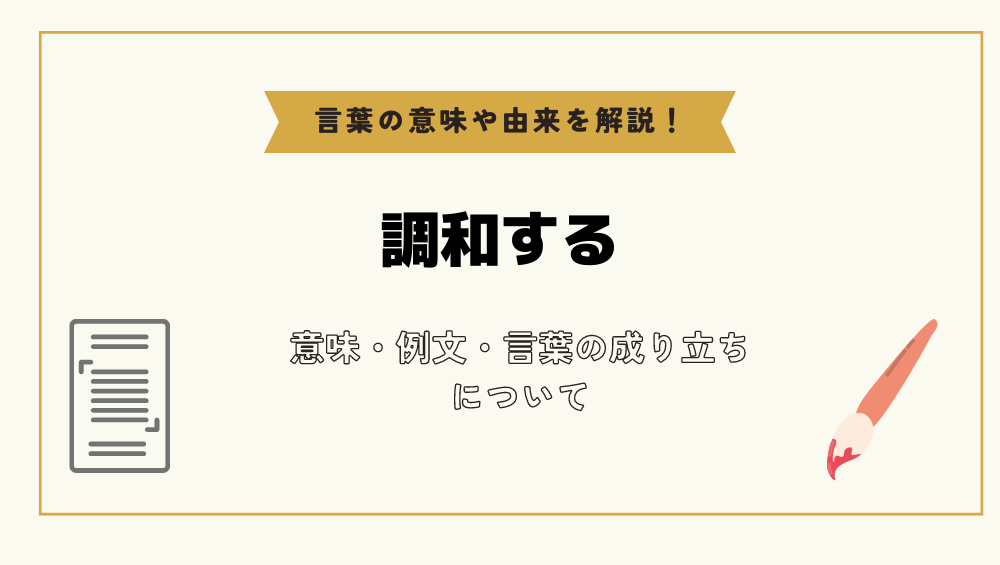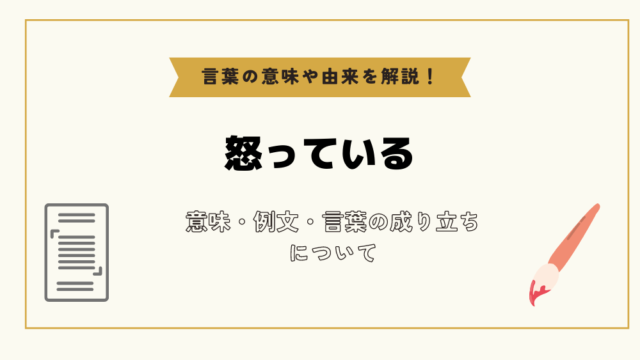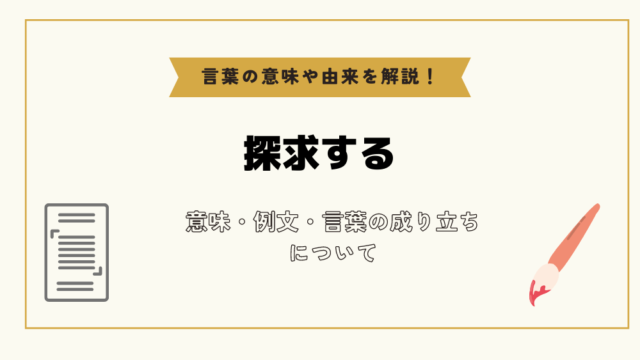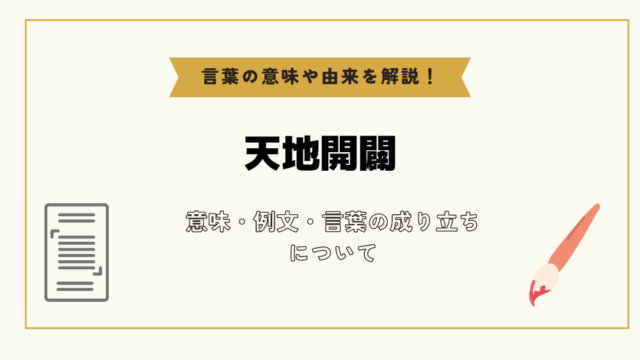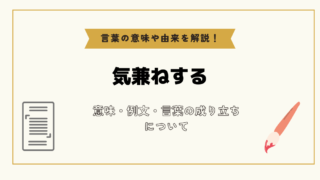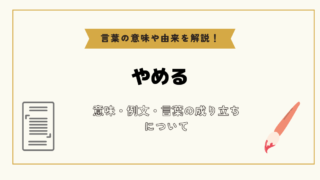Contents
「調和する」という言葉の意味を解説!
「調和する」という言葉は、異なる要素や要素間のバランスや調整がとれている状態を表します。
つまり、相反するものが一つにまとまり、調和のとれたバランスが生まれることを指しています。
例えば、個々の音楽の音符が一つに調和し、調和のあるメロディを奏でるような状態が「調和する」ということです。
「調和する」の読み方はなんと読む?
「調和する」の読み方は、「ちょうわする」と読みます。
日本語の発音によって、このような読み方になっています。
「調和する」という言葉の使い方や例文を解説!
「調和する」は、さまざまな場面で使われます。
例えば、人間関係での「意見が調和する」という表現では、相手の意見や考えに耳を傾け、自分の意見とも調整しながら、バランスのとれた意見の共有を意味します。
また、自然環境においても、「植物と動物が調和する」という表現では、互いに影響を与えながら、生態系のバランスが取れた状態を指します。
「調和する」という言葉の成り立ちや由来について解説
「調和する」という言葉は、古くから日本語に存在している言葉ですが、具体的な成り立ちや由来については明確には分かっていません。
ただし、「調和」の語源である「調(しら)べる」「調(ととの)える」といった言葉が、音楽や楽器の調整に用いられることから、バランスや調整の意味をもつ言葉として、広がっていったものと考えられています。
「調和する」という言葉の歴史
「調和する」という言葉の具体的な歴史については、古代から存在していましたが、古文書には使用例が見当たらないため、一般的に現代日本語として認識されるようになったのは近代以降のことです。
バランスや調整が必要な社会状況の変化に伴い、この言葉の重要性が浸透してきたと言えるでしょう。
「調和する」という言葉についてまとめ
「調和する」という言葉は、相反するものや要素のバランスや調整が取れた状態を表します。
人間関係や自然環境などさまざまな場面で使用され、互いに影響を及ぼしながらバランスが取れた状態を指します。
古代から存在している言葉であり、近代以降にさらに重要性が広まりました。
人間味豊かな関係性やバランスの取れた社会を築くために、調和の重要性を理解しましょう。