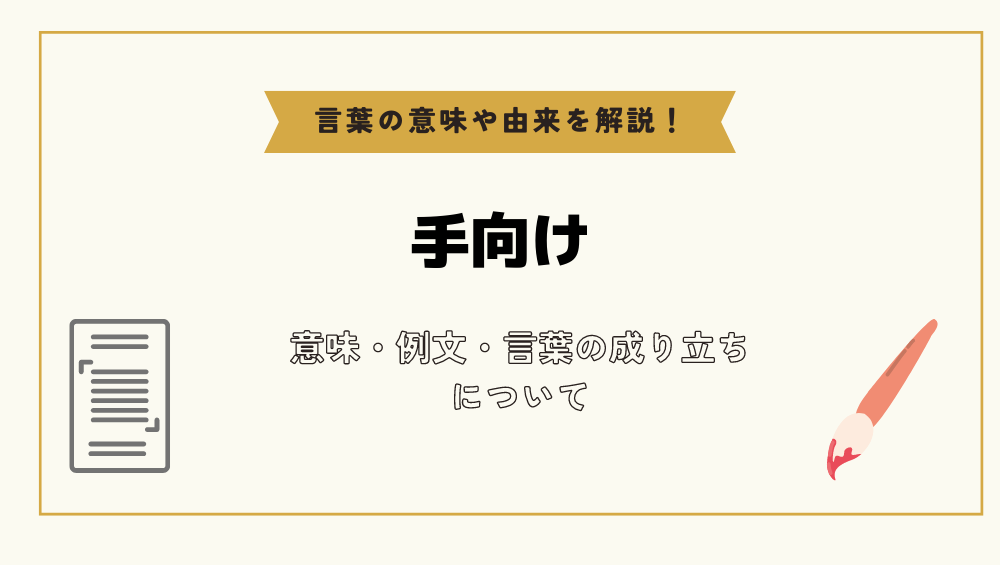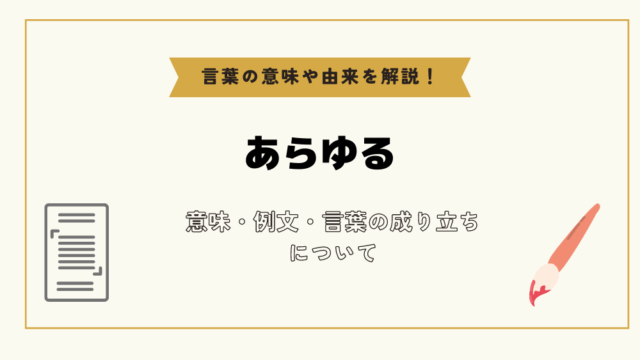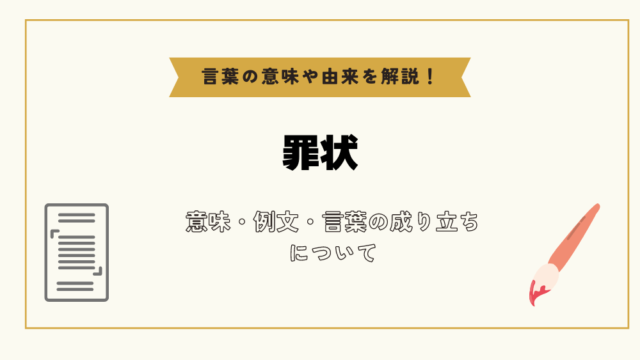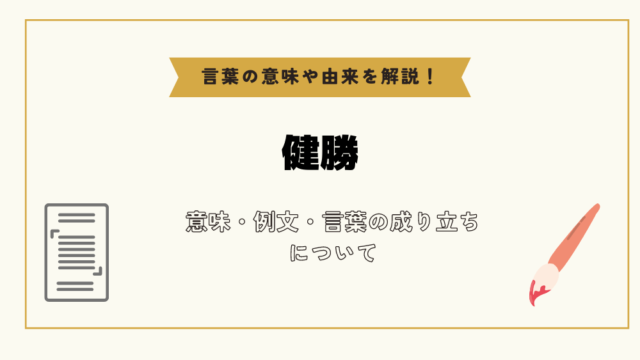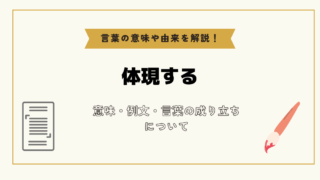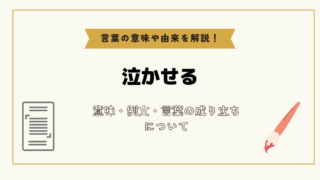Contents
「手向け」という言葉の意味を解説!
「手向け」という言葉は、感謝や敬意を込めて何かをささげることを意味します。
特に、神や亡くなった人への供物や祈りをささげることを指すことが多いです。
手向けは、大切な人への思いやりや感謝の気持ちを表現する際に使われる言葉としても知られています。
「手向け」という言葉の読み方はなんと読む?
「手向け」という言葉は、「たむけ」と読みます。
この読み方は一般的であり、日本語の文化や言葉の中で広く使用されています。
ですので、そのまま「手向け」と読むことがよくあります。
「手向け」という言葉の使い方や例文を解説!
「手向け」という言葉は、主に特別な機会や行事に使われます。
例えば、神社や仏壇にお参りする際に、手向けの供物を持参します。
また、故人への手向けとして、お墓や霊前に花を手向けることもあります。
さらに、感謝を込めて友人や上司に手向けの手紙を書くこともできます。
このように、「手向け」という言葉は大切な人に対する思いやりや感謝を伝えることができます。
「手向け」という言葉の成り立ちや由来について解説
「手向け」という言葉の成り立ちについては明確な由来がありませんが、日本の文化や宗教に深く根付いています。
神道や仏教の影響が大きく、祭りやお祀りの際に手向けをする習慣が生まれました。
手向けには、大切なものを手から手に渡すという意味もあり、そのまま感謝や敬意を表現する言葉として使われるようになりました。
「手向け」という言葉の歴史
「手向け」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や武士の信仰にも見受けられます。
また、江戸時代には武士の間で将軍や上司への手向けが行われ、感謝の気持ちや忠誠心を示す手段とされていました。
現代でも、「手向け」という言葉は大切な人への感謝を表現する手段として使われ続けています。
「手向け」という言葉についてまとめ
「手向け」という言葉は、感謝や敬意を込めて何かをささげることを意味します。
神や亡くなった人に対する供物や祈りをささげる場面でよく使われる言葉です。
日本の文化や言葉の中で広く使われており、特別な機会や行事で頻繁に目にすることができます。
「手向け」という言葉は、大切な人への思いやりや感謝の気持ちを表現するために使われる重要な言葉です。