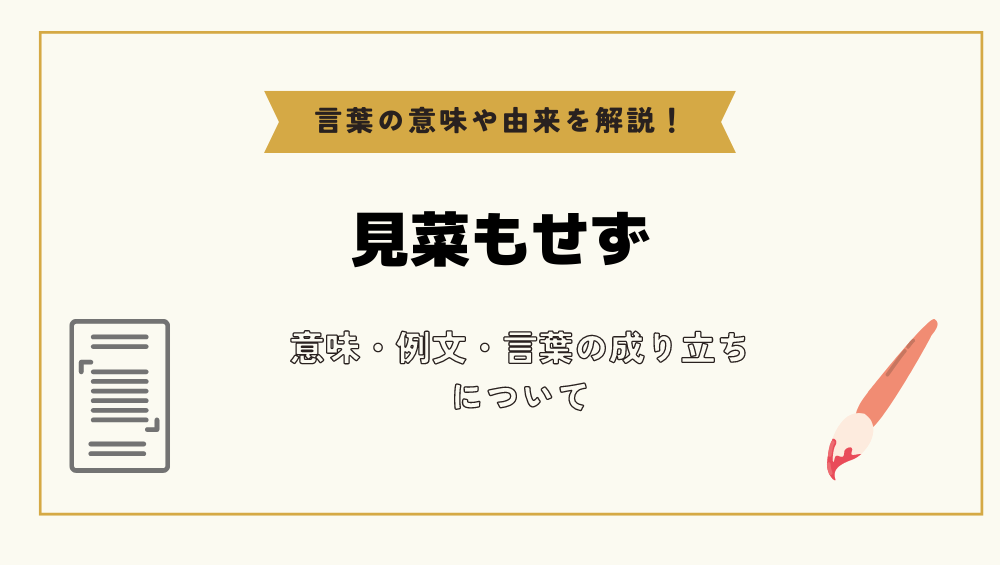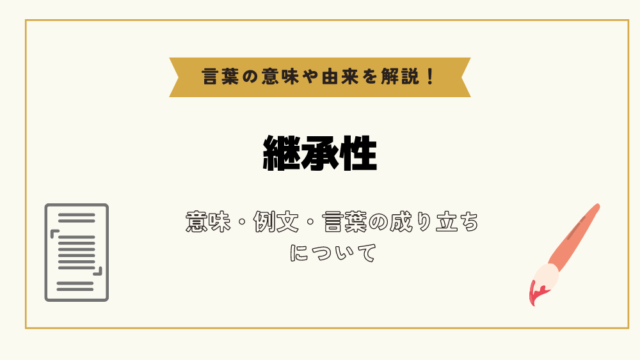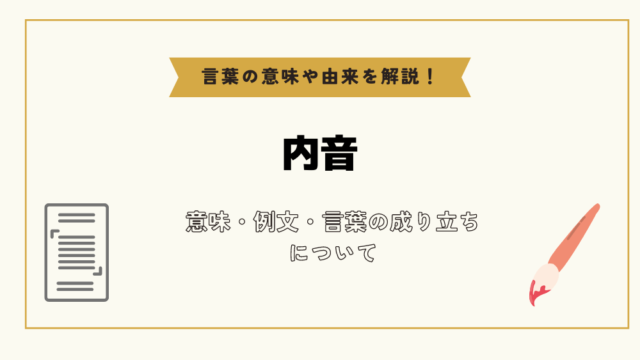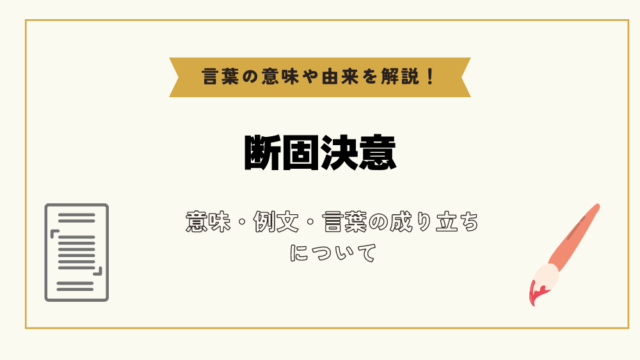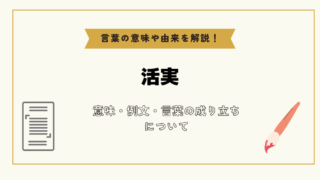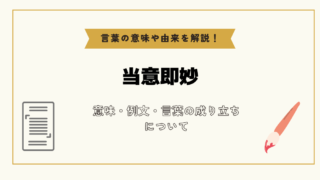Contents
「見菜もせず」という言葉の意味を解説!
「見菜もせず」という言葉は、仕事や勉強などに真剣に取り組まない様子を表現した表現です。具体的には、何もしないでただ見ているだけで、活動的でない状態を指します。
この言葉は、懸命に取り組むことが大切な場面で、その逆の行動をする人を揶揄するために使われます。例えば、仕事や学校でのプレゼンテーションの場で、他の人が頑張っている中でただ見ているだけの人に対して「見菜もせず」と言われることがあります。
「見菜もせず」という言葉の読み方はなんと読む?
「見菜もせず」という言葉は、「みなもせず」と読みます。この読み方は、漢字の意味からしても自然なものです。
「見菜もせず」という言葉の使い方や例文を解説!
「見菜もせず」という言葉は、他の人との比較や批判的なニュアンスを含んでいるため、使い方には注意が必要です。
例えば、会議中に円滑な話し合いを進めるためには、全員が積極的に意見を出し合うことが求められます。その中で一人だけがただ見ているだけで、何も発言しない場合に「見菜もせず」と言われることがあります。
また、友人同士で遊びに行く予定があったが、いつまでたっても一向に準備をせずにいる友人に対しても「見菜もせず」と言えます。
「見菜もせず」という言葉の成り立ちや由来について解説
「見菜もせず」という言葉は、江戸時代の俳諧師である鶴亀という人物によって初めて使用されました。彼は、俳句の世界で活動する中で、他の人が真剣に取り組んでいない様子を皮肉った言葉として「見菜もせず」という表現を作りました。
「菜もせず」とは、菜の葉を刻むことからきており、真剣に取り組むことの比喩とされます。その後、この言葉は広まり、現代でも使用され続けています。
「見菜もせず」という言葉の歴史
「見菜もせず」という言葉の歴史は比較的新しいものです。江戸時代から使われ始め、明治時代以降も広まっていきました。
特に、昭和時代になると、日本の経済が急速に発展し、競争社会が進む中で、真剣に取り組まない態度を批判する言葉として広まりました。
現代においても、「見菜もせず」という言葉はそのまま使われ続けており、仕事や学校、プライベートなど幅広い場面で使用されます。
「見菜もせず」という言葉についてまとめ
「見菜もせず」という言葉は、他の人との比較や批判的なニュアンスを含んでいる表現です。何もせずにただ見ているだけの様子を指し、真剣な取り組みを求める場面で使われます。
この言葉の由来は江戸時代に遡り、現代でも広く使われ続けています。日本の文化や風土に根づいた表現として、今後も多くの人に使われ続けることでしょう。