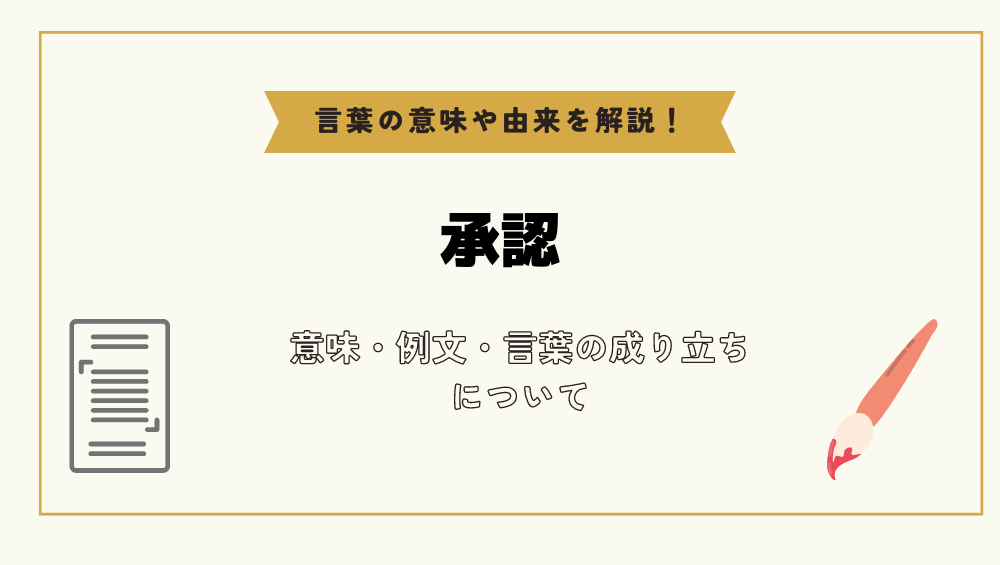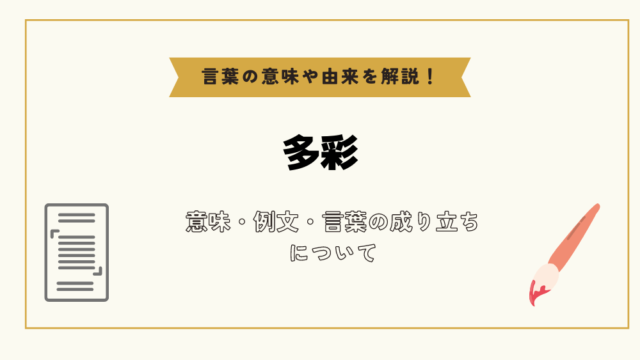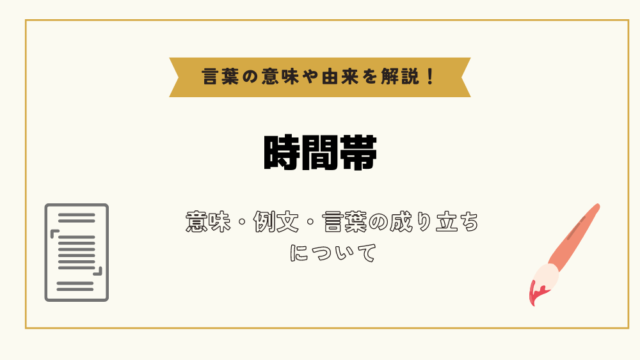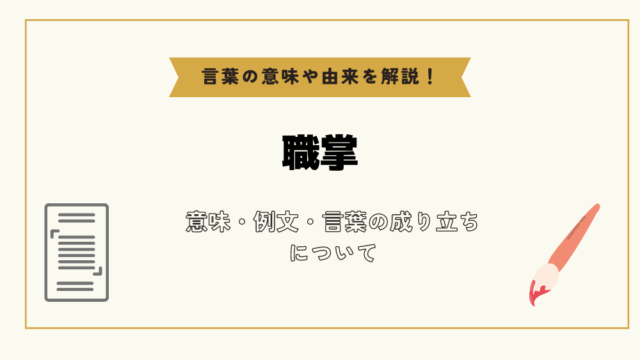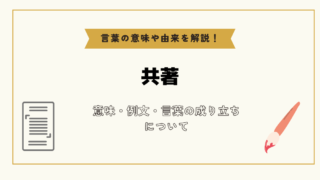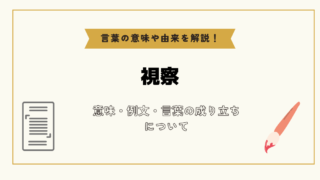「承認」という言葉の意味を解説!
「承認」とは、他者の意見・行動・存在を正当であると認め、受け入れる行為や状態を指す言葉です。
ビジネスシーンでは稟議書や申請書を上位者が「承認」するという使われ方が一般的です。
心理学の分野では「自己承認」や「他者承認」のように、人の心の満足度や帰属意識を説明するキーワードとして活用されています。
第二の意味として「法律上の有効性を認めること」もあります。
例えば裁判所が和解案を「承認」すると、その効力が確定し、関係者はその内容に従う義務を負います。
第三に「物事が世間に受け入れられている状態」を示す場合があります。
学術論文が学会で公に認められることを「承認された研究成果」と呼ぶのはその典型です。
いずれの用法でも共通するのは、「認めて受け入れる」という核心的なニュアンスです。
相手や制度から『OK』をもらうイメージを持つと覚えやすいでしょう。
「承認」の読み方はなんと読む?
「承認」は一般に「しょうにん」と読みます。
音読みのみで構成されるため、音訓の混在による読み方の揺れは起こりません。
「しょうにん」は四拍のリズムで発音し、アクセントは地域差が少ないとされています。
東京式アクセントでは「しょう↘にん↗」、関西では「しょう→にん↘」の傾向が見られます。
同じ字を使う熟語に「承認欲求(しょうにんよっきゅう)」がありますが、ここでも読みは変わらず「しょうにん」です。
「証人(しょうにん)」との混同に注意が必要で、文脈で区別すると誤読を防げます。
なお、人名用漢字として「承」の字を「うける」「たもつ」と訓読する場合もありますが、熟語「承認」では訓読みは用いません。
「承認」という言葉の使い方や例文を解説!
「承認」は動詞化して「承認する」、名詞として「承認が必要」、形容的に「承認済み」と多彩に使えます。
社内手続き・法律・心理学・ITなど幅広い場面で登場し、意味は状況によって微妙に変化します。
ビジネスでは部長が稟議書に押印する行為を「承認」と呼びます。
IT分野ではアプリがカメラへのアクセスを求めるとき、ユーザーが許諾ボタンを押す行為も「承認」に当たります。
キーワードは「許可+正当性の確認」であり、単なる閲覧や報告とは一線を画します。
【例文1】課長の承認を得てから発注処理を行います。
【例文2】SNSでフォロワーからのコメントが承認欲求を満たしてくれる。
口語では「承認をもらう」「承認しておく」とライトに用いられますが、公式文書では「承認を受ける」が一般的です。
「承認」という言葉の成り立ちや由来について解説
「承」は「受ける」「引き継ぐ」を意味し、「認」は「みとめる」「しるし」を意味します。
組み合わせることで「受け入れて認める」という語義が自然に導かれました。
古代中国の文献には「承」の字が「上命を受ける」の意で登場し、日本でも律令制下で天皇の勅許を「承る」と表現しました。
中世以降、「認」の字は証書や判物で真偽を確かめる際に使われるようになり、公家や寺社の記録で「勅命承認」などの形が見られます。
近代になると欧米から入った「アプローバル(approval)」の概念を既存の熟語で置き換える際に「承認」が広く採用されました。
輸入概念と在来語義が重なり合うことで、現代的な「承認」の用法が確立したといえます。
文学作品では樋口一葉『にごりえ』などに「人の心の承認」という表現が現れ、心理的ニュアンスが強調されていきました。
「承認」という言葉の歴史
古代律令制時代、太政官符や勅許を「承認書」とは呼びませんでしたが、「承る」「認むる」という表現は別々に存在しました。
鎌倉時代の武家文書では、将軍や執権が所領安堵を「みとめる」際に「承」の字が添えられる事例が確認されています。
江戸時代になると、幕府発給の朱印状や寺社領の安堵状で「承認」の2字が連続して使われ始めました。
このころから「上位者が下位者の願いを聞き入れる」という制度的意味が定着し、明治以降の官僚制にスムーズに引き継がれます。
戦後、日本国憲法第7条で天皇の国事行為に「承認」という語が登場し、法令用語としての地位が確立しました。
現在も議院内閣制の下で条約締結の「国会承認」など、統治機構を支える重要なキーワードとなっています。
1990年代からはインターネットの普及により「アクセス承認」「コメント承認」などIT関連語として急速に広まりました。
「承認」の類語・同義語・言い換え表現
「承認」と似た語には「許可」「認可」「了承」「採択」「是認」などがあります。
いずれも「認める」という点で重なりますが、ニュアンスや使われる場面が異なります。
「許可」は権限者が行為を許す意味が強く、法律用語でも頻出します。
「認可」は行政機関による正式な許しを指し、学校法人の設立や特許で多く用いられます。
「了承」は「事情を理解し受け入れる」柔らかい表現で、目上から目下に用いると失礼になる場合があります。
「是認」は道徳的・価値判断的に是とする意味を含み、単なる事務手続きの承認とは一線を画します。
言い換える際は「権限の厳密さ」「正式性」「価値判断の有無」を意識すると使い分けが容易になります。
「承認」の対義語・反対語
最も一般的な対義語は「否認」です。
刑事裁判で被告人が起訴事実を「否認」するケースが知られています。
類似語として「拒否」「却下」「不承認」「棄却」「否決」などがあります。
これらは全て「認めない」「受け入れない」を示しますが、手続きの段階や権限者によって使い分けが必要です。
例えば議会での議案に対しては「否決」、裁判所の申し立てには「却下」、行政庁の申請書類には「不許可」が一般的です。
対義語を正しく選ぶことで、文章の正確性と説得力が向上します。
「承認」を日常生活で活用する方法
家庭や学校でも「承認」の考え方は大切です。
子どもが描いた絵を「上手だね」と肯定的に評価する行為は「他者承認」に当たります。
職場ではメンバーの成功体験を共有し、互いに称賛する文化を作ることで「承認欲求」を健全に満たせます。
上司が部下に対して“ありがとう”“助かった”と伝えるだけで、心理的安全性が高まり生産性が上がるという研究結果が報告されています。
スマートフォンアプリの通知を利用して「歩数目標を達成するとバッジをもらう」といった仕組みも、自分自身を承認するセルフリワードとして機能します。
さらに、友人のSNS投稿に「いいね!」を押す行為は即時的な「承認」を相手に提供する簡単な方法です。
ただし過度に承認を求めると依存状態に陥るリスクもあるため、バランス感覚が重要です。
「承認」という言葉についてまとめ
- 「承認」は他者や制度が正当性を認め受け入れる行為・状態を示す言葉。
- 読み方は「しょうにん」で、同音異義語の「証人」と区別が必要。
- 古代の「承る」「認むる」が結びつき、近代に制度語として定着した。
- ビジネス・法律・心理学など幅広く使われ、対義語は「否認」。
「承認」は単なる手続き用語にとどまらず、人間関係や自己肯定感を支える根本的なキーワードです。
ビジネス文書で押印をもらう場面から、友人のSNS投稿にリアクションする瞬間まで、私たちは日常的に「承認」を与えたり、受け取ったりしています。
時代が変わっても「誰かに認めてもらいたい」「正当性を確保したい」という人間の普遍的欲求は変わりません。
これからも「承認」という言葉は、制度と感情の両面で社会をつなぐ重要な橋渡し役として機能し続けるでしょう。