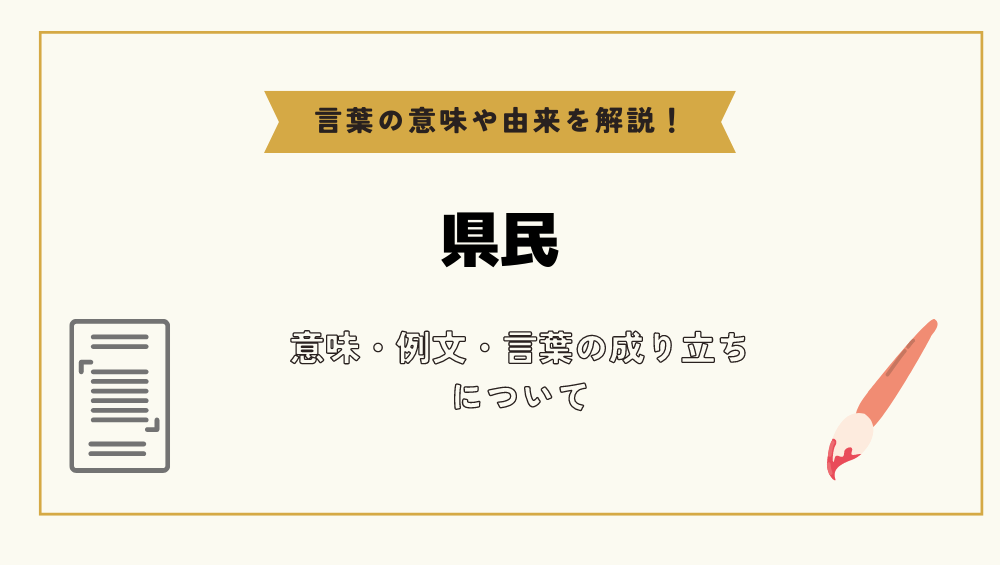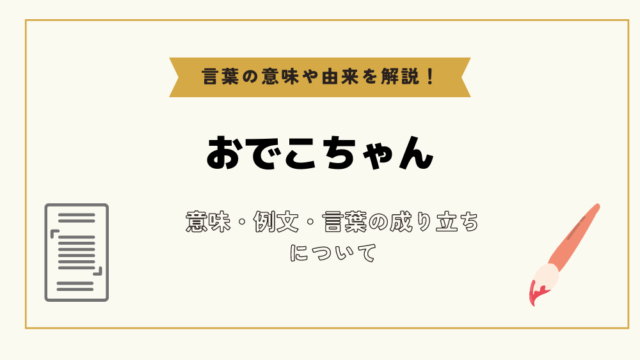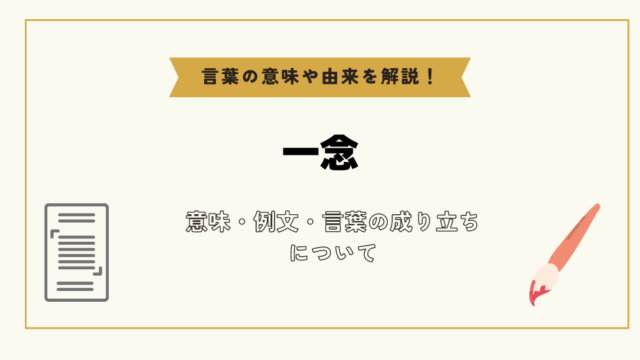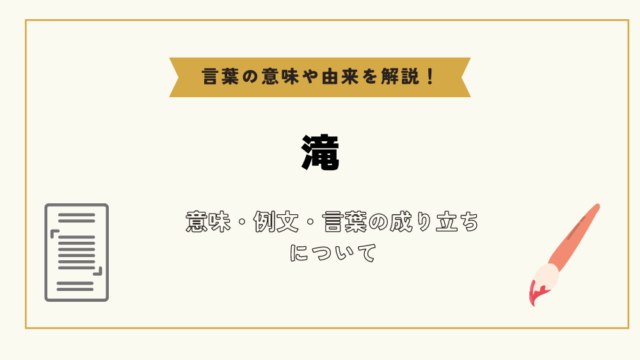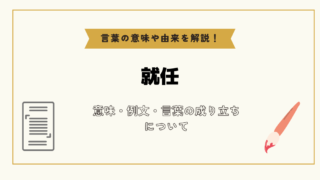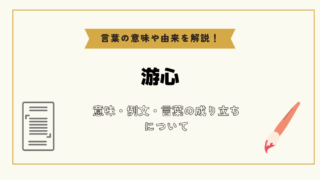Contents
「県民」という言葉の意味を解説!
「県民」という言葉は、ある特定の地域に住んでいる人々を指す言葉です。
具体的には、ある県に居住している人々を指します。
県民はその地域に根付いた暮らしを営み、その地域の文化や風習に親しんでいます。
県民同士は一体感を持ち、地元のイベントや行事に参加することも多いです。
「県民」という言葉の読み方はなんと読む?
「県民」という言葉は、「けんみん」と読みます。
日本語の発音において、各文字がそれぞれの音を持っており、それを組み合わせることで単語が形成されます。
ですので、「県民」という言葉も同様に、それぞれの文字の音を順番に発音して「けんみん」という読み方になります。
「県民」という言葉の使い方や例文を解説!
「県民」という言葉は、特定の県に住んでいる人々を指すために使用されます。
例えば、「私は静岡県の県民です」と言うことで、その人は静岡県に住んでいることや、その地域の文化や習慣に通じていることが伝わります。
また、「県民限定のイベント」といった言い回しもよく使われます。
これは、そのイベントがその県の住民のみを対象としていることを表しています。
「県民」という言葉の成り立ちや由来について解説
「県民」という言葉は、各地に設置された県庁や地方自治体が発展する過程で生まれた言葉です。
日本の地方自治体は戦後の地方分権によって設立され、それに伴い県民という概念も広まっていきました。
県民は、その地域の発展や行政に関わりながら、地域のために尽力する存在として位置づけられています。
「県民」という言葉の歴史
「県民」という言葉の歴史は比較的新しいものです。
戦後の地方分権によって日本の地方自治体が成立し、各県に県庁が設置されたことで「県民」という概念が生まれました。
以前は地域ごとに異なった名称で呼ばれていた地域住民たちが、統一された言葉として「県民」と呼ばれるようになりました。
この言葉は、地域の一体感を醸成する役割を果たしています。
「県民」という言葉についてまとめ
「県民」という言葉は、特定の県に住んでいる人々を指します。
地域の文化や風習に親しんだり、地元のイベントに参加したりすることが多いです。
この言葉は戦後の地方分権によって成立し、その地域に根ざした共感や一体感を生み出す役割を果たしています。