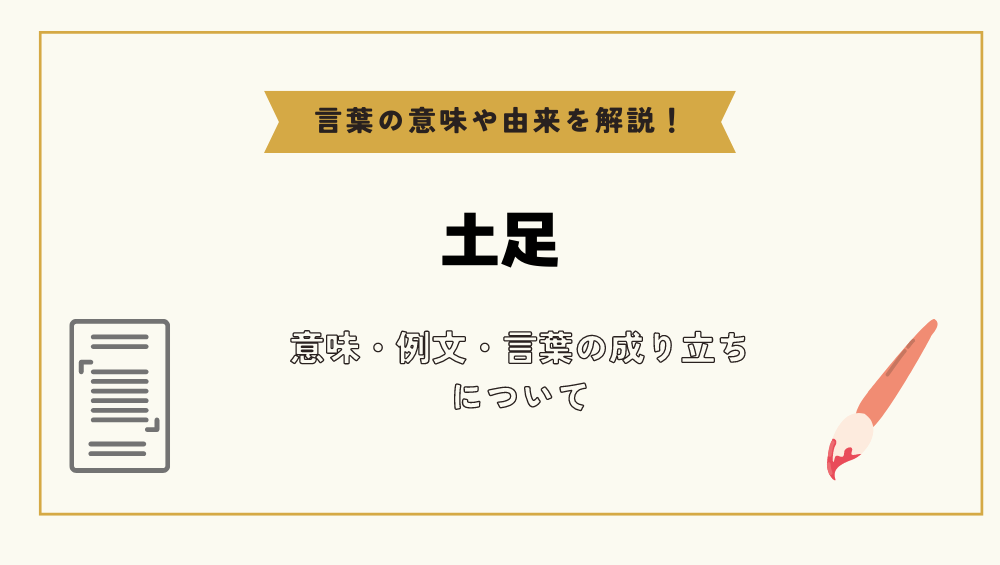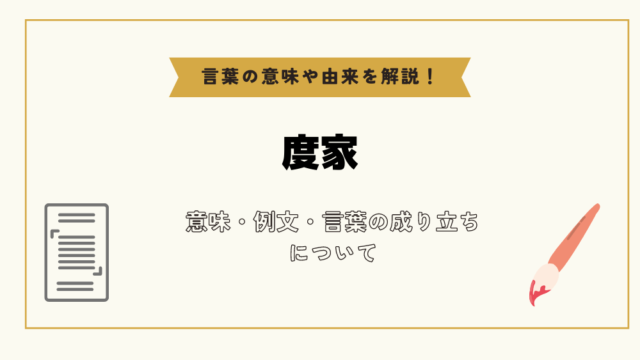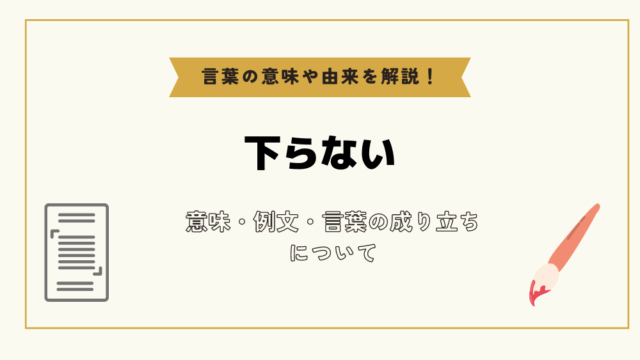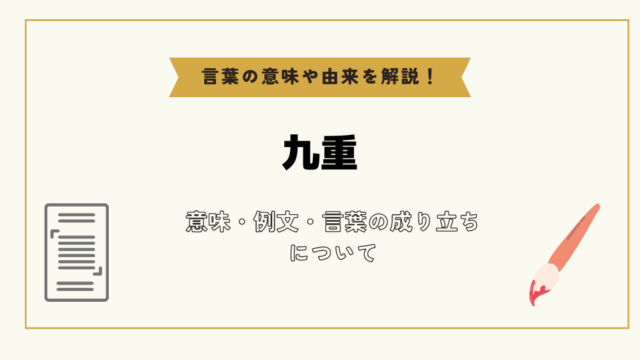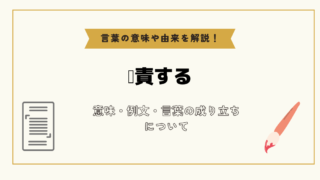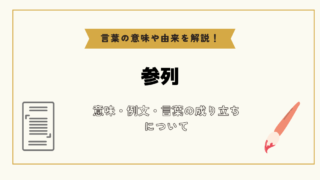Contents
「土足」という言葉の意味を解説!
「土足」という言葉は、室内や特定の場所で靴を脱ぐべきではないという意味を持ちます。
一般的には日本の文化において、家庭や神社、お寺など、清潔な場所では靴を脱いで上がるべきであることを指します。
これは「土足禁止」とも言われ、室内に汚れを持ち込まないためのマナーです。
「土足」の読み方はなんと読む?
「土足」は、「どそく」と読みます。
正確には「とそく」とも読める場合もありますが、一般的には「どそく」と読まれることが多いです。
「土足」という言葉の使い方や例文を解説!
「土足」という言葉は、特定の場所で靴を脱ぐべきではないという意味を表します。
例えば、「このお家では土足禁止ですので、玄関で靴を脱いでください」というように使われます。
他にも神社やお寺の入り口には「土足禁止」の看板が掲げられており、そこで上記の言葉が使われています。
「土足」という言葉の成り立ちや由来について解説
「土足」という言葉は、元々は建物の中に汚れを持ち込まないためのマナーとして生まれました。
日本の伝統的な建築様式である「よく汚れた土間に座る」ことから、靴を脱いで室内に上がる習慣が生まれました。
これが後に広まり、現在の「土足禁止」という形になっているのです。
「土足」という言葉の歴史
「土足」という言葉の起源は古く、奈良時代から存在していました。
当時は寺社や皇室の中に靴を脱がなければならないという風習がありました。
また、江戸時代には特に庶民の間で靴を脱ぐ習慣が広がり、現在のような「土足禁止」という言葉が一般的になりました。
「土足」という言葉についてまとめ
「土足」という言葉は、建物の中で靴を脱ぐべきであることを指します。
この習慣は日本において非常に重要であり、清潔さや礼儀を尊重する意味が込められています。
室内に汚れを持ち込まないためには、しっかりと「土足禁止」というマナーを守ることが大切です。