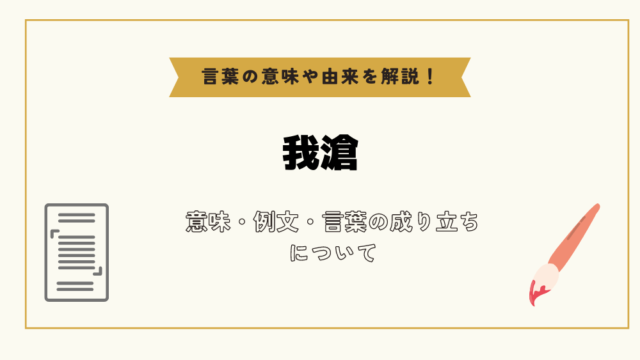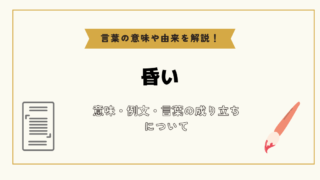Contents
「謀る」という言葉の意味を解説!
「謀る」とは、計画を立てたり、策略を巡らせたりすることを意味します。
何かを企てる、陰謀をめぐらすといったニュアンスがあります。
この言葉は、他人を欺いたり、自分の利益のために計画をめぐらす場面でよく使われます。
謀るは人間関係やビジネスの場でよく用いられる言葉です。
議論や交渉の際、相手の思考や意図を読み取り、自分の立場を保つためには、相手よりも先を見越した計画を立てる必要があります。
「謀る」の読み方はなんと読む?
「謀る」は「はかる」と読みます。
この言葉は、意外と難しい読み方をされることもあるかもしれませんが、実際には「はかる」と正しく読まれることが一般的です。
謀るという言葉は、日本語の中でもやや堅い表現ですが、日常会話やビジネスシーンでも使われることがあります。
正確な読み方を知っておくことで、より自然な表現ができるでしょう。
「謀る」という言葉の使い方や例文を解説!
「謀る」という言葉の使い方はさまざまですが、共通していえるのは、計画を立てたり策略を巡らせることによって、自分の意図を達成するという点です。
たとえば、ビジネスの世界では、「競合他社を出し抜くため、新たな戦略を謀る」といった表現がよく使われます。
また、政治の世界でも、「選挙の勝利を謀るため、有権者に対して魅力的な政策を提案する」といった使い方があります。
「謀る」という言葉の成り立ちや由来について解説
「謀る」という言葉の成り立ちや由来については明確な情報がありません。
ただ、形容詞の「謀(はかる)い」と同じく、古くから日本語に存在する言葉と考えられています。
謀るは、人間の思考力や計画力を表す言葉であり、人々が互いに競い合い、優位に立つために用いられてきた言葉と言えます。
「謀る」という言葉の歴史
「謀る」という言葉の歴史は、古代日本までさかのぼることができます。
古くから人々は生き残りや繁栄を求め、計画的な行動や策略によって目的を達成しようとしてきました。
戦国時代や江戸時代には、武士や政治家が国や家を守るために様々な計略を謀りました。
また、幕末の動乱期には、倒幕を謀る志士たちが活躍し、日本の近代化を推進するきっかけとなりました。
「謀る」という言葉についてまとめ
「謀る」という言葉は、計画を立てたり策略を巡らせたりすることを意味し、他人を欺いたり自らの利益を追求する際に用いられます。
読み方は「はかる」となります。
この言葉は、日本の歴史や文化に深く根付いており、人々の計画力や思考力を表す重要な言葉として使われています。
ビジネスや政治の場でもよく使われるので、しっかりと意味と使い方を覚えておきましょう。