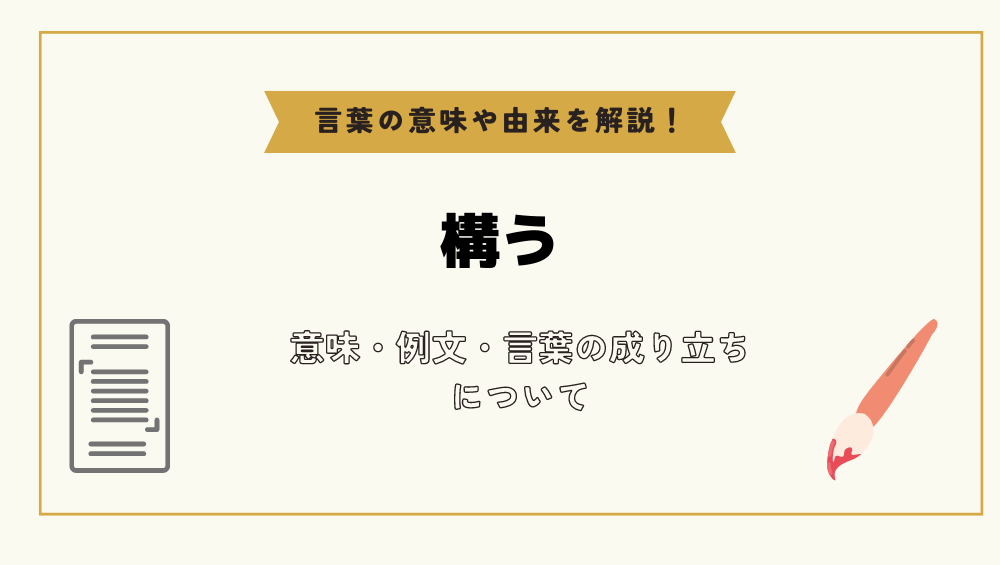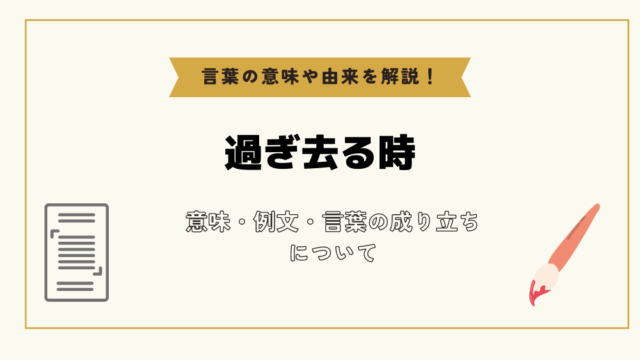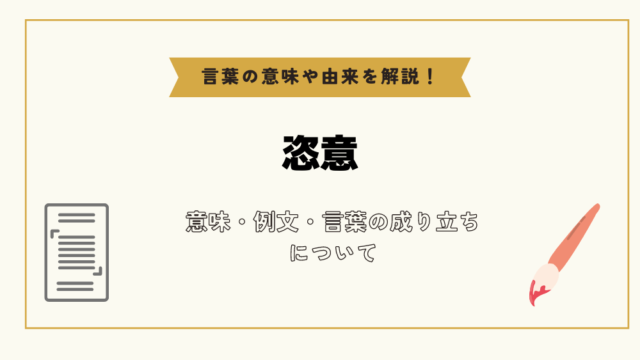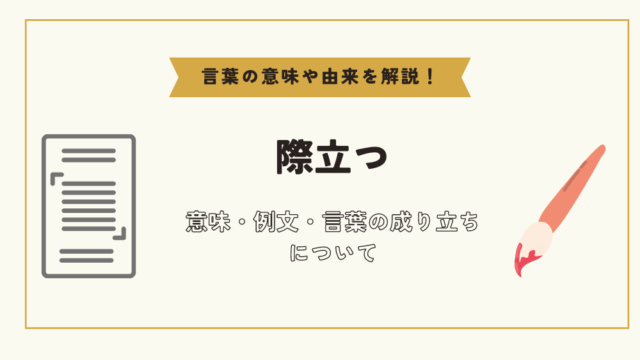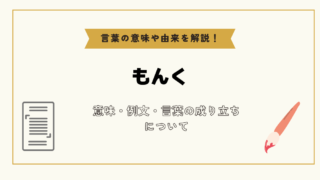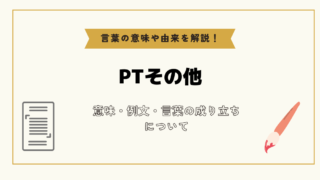Contents
「構う」という言葉の意味を解説!
「構う」とは、相手のことを気にかけたり、心配したりすることを意味します。人や物事に対して関心や配慮を持つこと、気にすることを表す言葉です。人間関係や社会生活において、他者を大切に思う気持ちや思いやりを表す言葉として使用されます。
人の悩みに寄り添う姿勢や、思いやりの気持ちが表れる「構う」という言葉は、相手のことを大切に思うことができる人間らしさや優しさを感じさせます。
「構う」という言葉の読み方はなんと読む?
「構う」という言葉は、読み方としては「かまう」と読みます。日本語のユニークな言葉の一つですが、その意味や使い方を理解することで、より豊かなコミュニケーションができるでしょう。
「構う」という言葉の使い方や例文を解説!
「構う」という言葉は、他人や他の物事に対して関心や配慮を示すときに使われます。例えば、「友人の悩みに構ってあげる」「部下の成長を構い、サポートする」といった使い方があります。
この言葉は、相手の気持ちや状況に寄り添い、思いやる姿勢を示すときにも使われます。例えば、「大切な人の心配を構う」「子どもの将来を構ってあげる」といった表現があります。
「構う」という言葉の成り立ちや由来について解説
「構う」という言葉は、古代日本の言葉「心配(かんぱく)」や「気にする(きにする)」などが発展し、漢字で「憂(うれ)う」や「顧(かえり)みる」などに関連付けられてきました。
このように、古来から日本人の言葉の中には、「構う」という意味や感じ方に近いものが存在していました。そのため、日本語の豊かな表現力が、「構う」という言葉の成り立ちにつながっていると言えるでしょう。
「構う」という言葉の歴史
「構う」という言葉は、古今和歌集や枕草子など、日本の古典文学にも多く登場しています。また、歌舞伎や能などの伝統芸能や現代の小説、ドラマ、映画などでも頻繁に使用されています。
このように、日本の文学や芸能の中で多く使われる言葉として、「構う」という言葉は歴史を持っています。長い間、人々の心や感情に寄り添い、共感を呼ぶ言葉として親しまれてきました。
「構う」という言葉についてまとめ
「構う」という言葉は、相手を気にかける気持ちや関心を表す素敵な言葉です。日本人の思いやりや優しさが表れる言葉として広く使われており、古代から現代に至るまで歴史を持っています。
この言葉を使うことで、相手に寄り添い、思いやりの気持ちを伝えることができます。日本語特有の表現力を活かして、人間味あふれるコミュニケーションを築く手助けとなるでしょう。