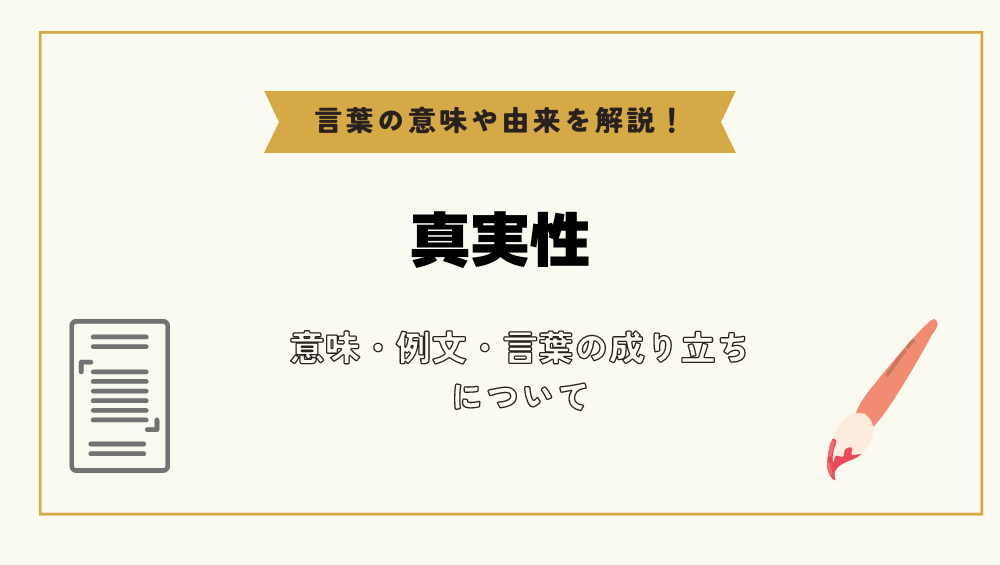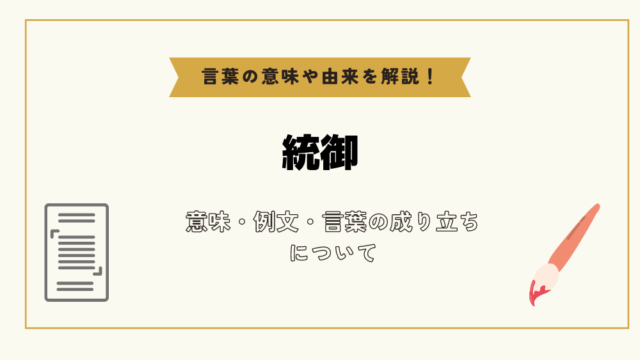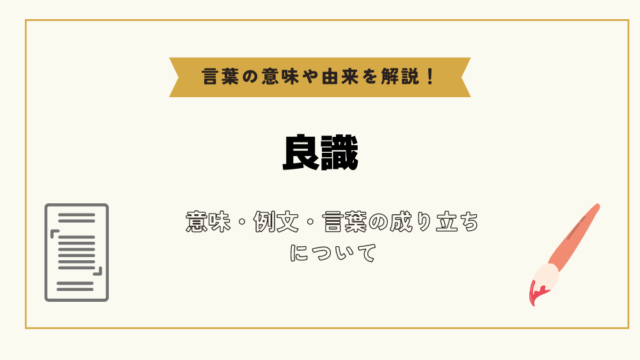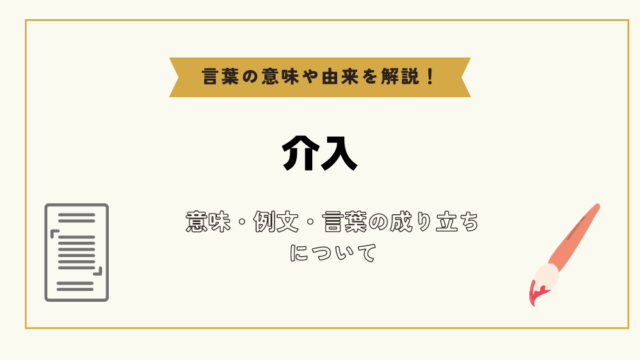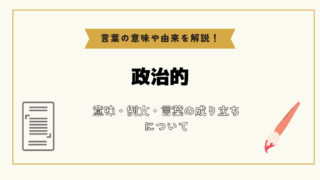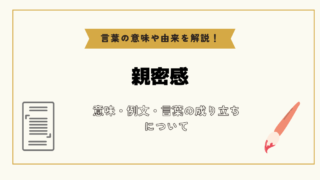「真実性」という言葉の意味を解説!
「真実性」とは、物事や情報が事実に基づき、虚偽や誇張を含まずに正確であるという性質を示す言葉です。この語は「真実」という名詞に、性質を表す接尾語「性」が付いた熟語であり、「真実である度合い」「真実であることの確かさ」を示します。したがって、単に「真実」と言うよりも、事実性・確実性など、やや抽象的で客観的なニュアンスが強くなります。
ビジネスや研究など、公的な場面で「真実性の検証」「真実性の担保」といったかたちで使用されるときは、事実関係を裏付ける証拠・根拠があるかに焦点が置かれます。裁判や報道の分野では「真実性の抗弁」という法律用語が存在し、名誉毀損の成否を左右する概念として知られています。
日常会話で「真実性が低い」と言えば「信ぴょう性が乏しい」とほぼ同義ですが、公的文書ではより定義が明確な語として扱われます。このように、真実性という言葉は客観的な確認可能性と結びつき、「主観的にそう思う」というレベルを超えている点が大きな特徴です。
そのため、感情論や推測に基づく発言とは区別され、「真実性のない主張」と評価されると大きな信用失墜につながりかねません。正確な情報発信が求められる現代では、真実性を意識することがますます重要になっています。
「真実性」の読み方はなんと読む?
「真実性」は一般に「しんじつせい」と読みます。多くの国語辞典でもこの読みが採録されており、公的文書や法律用語でも「しんじつせい」と発音されます。
稀に「しんじつしょう」と読む例が古い文献に見られますが、現在の日常的な読み方としてはほとんど浸透していません。また「真実さ」と訓読調に言い換える場合もありますが、意味合いがやや口語的・感情的になる点には注意が必要です。
ビジネスメールなどで使用する場合は、ふりがなを振る必要はありませんが、話し言葉では「しんじつせい」と明瞭に発音することで誤解を防げます。特に「信実性」「真正性」といった類似語との混同を避けたい場面では、漢字と読みを明確に提示すると効果的です。
なお、英語に訳す際は “veracity” や “truthfulness” が相当しますが、法律分野では “truthfulness defense” のように複合語として扱われる例もあります。読み方を押さえることで、議論の場面でもスムーズに用語を共有できます。
「真実性」という言葉の使い方や例文を解説!
真実性は「その情報が事実に合致しているか」を示す評価指標として、文章でも会話でも幅広く用いられます。主語にあたる対象は「情報」「証言」「報道」など抽象名詞が多く、動詞は「確認する」「担保する」「欠く」などが相性の良い組み合わせです。
報道機関では「記事の真実性を二重にチェックする」と表現し、エビデンスの有無を強調します。法律実務では「名誉毀損における真実性の立証責任」という言い回しが定着しており、専門性の高い文脈でも頻出します。
【例文1】第三者の検証により、報告書の真実性が確保された。
【例文2】その証言の真実性について、裁判所が疑問を呈した。
【例文3】発表前にデータの真実性を担保するプロセスを設計する。
例文のように「真実性+を+動詞」で構文を組むと、客観的・公的な響きが生まれ、相手に専門性と信頼感を与えやすくなります。反対に、プライベートな場面で使うとやや堅い印象になるため、言葉のトーンを調整すると円滑なコミュニケーションが図れます。
「真実性」という言葉の成り立ちや由来について解説
「真実性」は「真実」と「性」から構成される合成語です。「真実」の語源は漢籍に遡り、「真(まこと)」と「実(み)」が合わさり「虚偽がないこと」を示しました。
ここに性質を示す接尾語「性」が付くことで、主観的な“真実”そのものではなく、“真実であるかどうか”を判定する抽象概念へと拡張されました。このパターンは「安全性」「信頼性」などと同様で、日本語の造語法として一般的です。
法律分野では、明治期に西洋法を翻訳する中で “veracity” “truth” の訳語として採用された経緯があります。新しい概念を漢字で精緻に表そうとした法令翻訳家たちが、「真実性」という表現を体系的に整備したと考えられています。
また、新聞が普及しはじめた明治後期には「記事の真実性」というフレーズが紙面に登場し、一般読者にも徐々に浸透しました。現代でもメディアリテラシー教育の文脈で頻繁に取り上げられています。
「真実性」という言葉の歴史
江戸末期までは「真実」単体が多く用いられ、「真実性」という熟語は文献上ほとんど確認できません。しかし、明治維新後に制度・科学・法律が急速に西洋化したことで、「性」を付した抽象概念を表す語群が大量に生まれました。
明治23年公布の旧刑法草案にはすでに「真実性」の語が登場し、名誉毀損罪の要件を説明する中で使用されています。その後、大正期には新聞紙法や出版法の議論でも取り上げられ、メディア規制の焦点となりました。
戦後はGHQの影響で報道の自由が保障されつつも、「真実性の原則」がジャーナリズムの倫理基準として再確認されました。この時期に作成された日本新聞協会編集委員会の文書では「取材と発表における真実性の確保」が明示されています。
インターネット時代に入り、フェイクニュースやデマが拡散しやすくなると、真実性という概念は再び脚光を浴び、プラットフォーム企業でもポリシーとして採用されるようになりました。現在ではAIが生成する情報の検証にも活用され、歴史を通じてその重要度が高まり続けていると言えます。
「真実性」の類語・同義語・言い換え表現
「真実性」と近い意味をもつ語には「信憑性」「正確性」「確実性」「真正性」などがあります。
「信憑性」は情報が信じるに足るかを示す語で、心理的要素がやや強いのに対し、「真実性」は事実との整合性をより重視する点で異なります。「正確性」は誤差がないかに注目し、主に数値やデータに対して用いられます。一方「確実性」は実現の蓋然性を示すため、「計画の確実性」など未来志向に用いられることが多いです。
また「真正性(オーセンティシティ)」は「改ざんがない、生まれ持ったままの状態であること」を強調します。芸術品や哲学の領域で用いられる点が特徴です。
状況に応じてこれらの語を使い分けることで、話し手の意図や文脈をより精確に伝達できます。例えば、調査報告書では「データの正確性」、SNS投稿の検証では「情報の信憑性」とすることで、評価軸を明確にできます。
「真実性」の対義語・反対語
真実性の反対概念として最も一般的なのは「虚偽性(きょぎせい)」です。虚偽性は事実に反している、あるいは偽りが含まれている性質を示し、法令でも「虚偽の申告」「虚偽広告」などの形で制裁対象となります。
「偽造性」「欺瞞性」も近い反対語ですが、これらは「意図的に偽る」ニュアンスが強調されます。したがって、誤情報が意図的かどうかを問わず真実と異なる場合は「虚偽性」、故意に誤導する場合は「欺瞞性」と区別して使うと適切です。
実務の場面では「真実性が担保されていない情報=虚偽性が疑われる情報」という対比で語られることが多く、双方の用語理解が欠かせません。特に法律文書では、真実性の証明責任と虚偽性の認定基準がしばしば問題になります。
「真実性」を日常生活で活用する方法
日々の情報収集においては、ニュース記事やSNS投稿を読む際に「真実性の確認」を習慣化することで、誤情報に振り回されにくくなります。
具体的には「一次情報源をたどる」「複数の信頼できるメディアを参照する」「発信者の利害関係をチェックする」といった手順が、真実性を評価する基本です。家庭内でも、子どもと一緒に「この情報は本当かな?」と問いかけることで、メディアリテラシー教育につながります。
ビジネスでは、社内報告や企画書にエビデンスを添付し「真実性を担保しました」と一言添えることで、上司や関係者の信頼を得やすくなります。さらに、商品説明書にデータソースを明記することで、顧客からの信頼も向上します。
真実性を確保する姿勢は、人間関係のトラブルを未然に防ぎ、説得力あるコミュニケーションを実現する鍵となります。
「真実性」についてよくある誤解と正しい理解
「真実性が高い=100%完全に正しい」と誤解されがちですが、実際には証拠・根拠が十分にそろっているかどうかを評価する概念です。絶対的な真理を示すわけではなく、新たな事実や研究が判明すれば評価は更新されます。
「真実性=客観性」と混同されることもありますが、客観的であっても事実と異なる場合は真実性が欠ける点に注意が必要です。例えば、誤ったデータを中立的に伝えても、内容が間違っていれば真実性は担保されません。
また「真実性は主観的に判断できる」と考える人もいますが、学術的には検証可能性が必須条件です。証拠を提示し、第三者が再現可能であることが真実性の裏付けとなります。
誤解を解くためには「真実性は“事実に合致しているかどうか”を示す評価基準であり、情報の価値を測る物差しである」と理解することが大切です。
「真実性」という言葉についてまとめ
- 「真実性」とは、情報や出来事が事実に一致している性質を示す言葉である。
- 読み方は「しんじつせい」で、漢字表記は一般にこの一形だけが用いられる。
- 明治期の法令翻訳を通じて普及し、報道や法律分野で重要概念となった。
- 現代ではフェイクニュース対策やビジネス資料の信頼確保など、多方面で活用される。
真実性は、単なる「真実」という言葉を一歩進め、情報が客観的に事実へ適合しているかどうかを測定する枠組みを提供します。法律・報道・研究など、公的信頼が重視される領域で確固たる位置を占めており、インターネット時代の今日、私たち一人ひとりが意識すべき重要なキーワードです。
読み方は「しんじつせい」とシンプルですが、意味は奥深く、類語・対義語と対比させることで理解が一層深まります。情報洪水の現代社会を賢く生き抜くために、真実性をチェックする視点を習慣化しましょう。