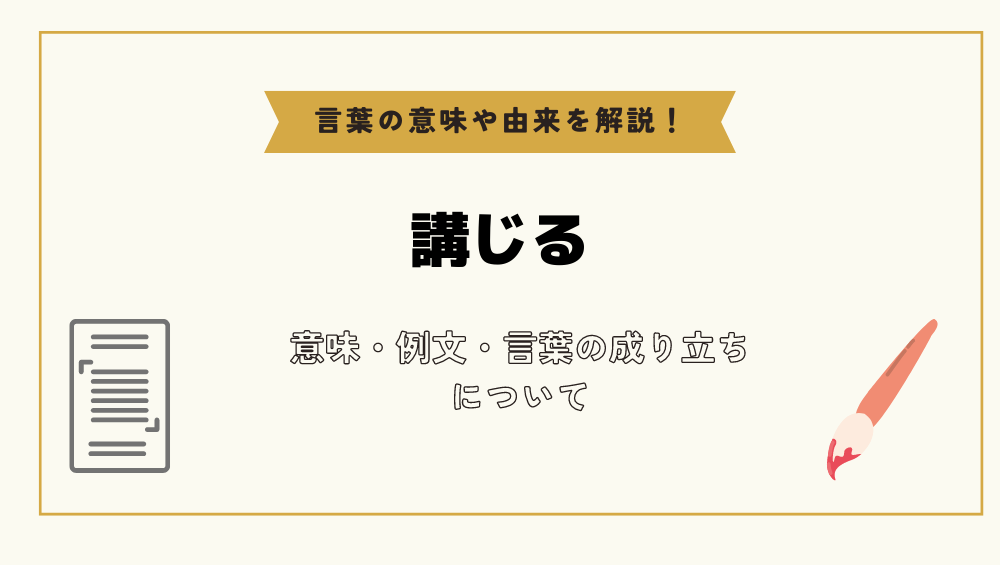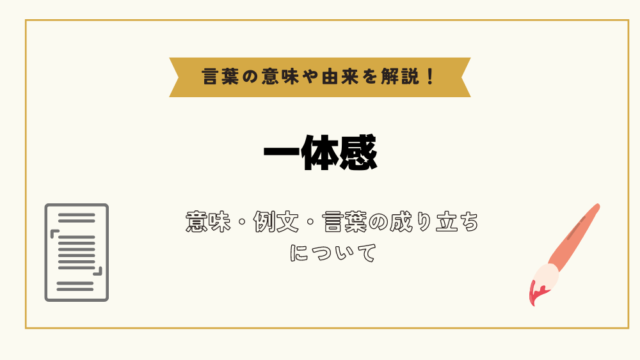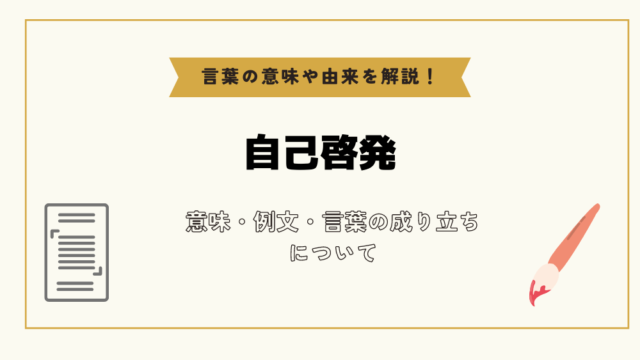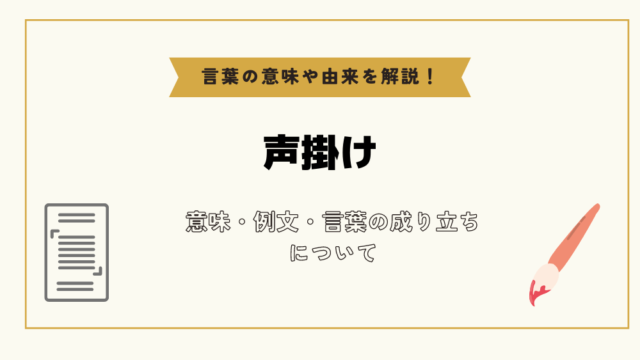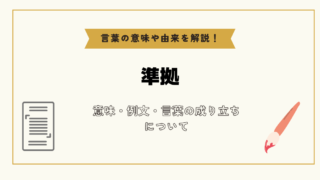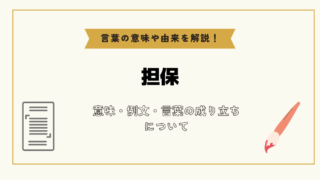「講じる」という言葉の意味を解説!
「講じる」は物事の解決に向けて具体的な手段や方策を立案し、実行に移すという意味を持つ動詞です。文語的な表現でありながら、ビジネス文書やニュース記事など幅広い場面で見かける語です。多くの場合「対策を講じる」「手を講じる」などの形で用いられ、問題に対して能動的かつ計画的に行動するニュアンスを含みます。
語源的には「講(こう)」が「人々が集まり、知識や方法を示し合うこと」を指し、そこから「講義」「講習」と同系統で発展しました。「講じる」はその場で語られた知や策を「じる=する、行う」に接続したもので、「策を示し同時に実施する」という二段階の動きを一言で表現できる便利な語となりました。
現代日本語では、「具体的な手段」「体系的なプラン」に重きが置かれています。単に「考える」「取り組む」よりも計画性や公式性が強調されるため、公的な文章やフォーマルな会話で好まれます。したがって、オフィシャルな報告書では「即座に対応を講じる必要がある」と書くことで、迅速かつ計画的な行動を促す一文になります。
「講じる」の読み方はなんと読む?
「講じる」は「こうじる」と読みます。「講」という字は「講演」「講座」などと同じ訓読みではなく音読みの「こう」、送り仮名の「じる」は動詞化の働きを担います。音読み+送り仮名の形は「興じる」「掲げる」などと同様に、古くから慣用的に用いられてきました。
読み間違いとしては「こうずる」と濁らずに読む誤用が挙げられます。「図る(はかる)」の言い換えで「講ずる」と書く場合は「こうずる」と読めますが、「講じる」と送り仮名が付く形では濁音化しないのが正しいです。この点は国語辞典や文部科学省の表記基準でも明示されています。
また、類似表現として「講ずる」が同義文語形として存在しますが、現代語の一般的な表記は「講じる」です。公報など極めて形式ばった文書では「講ずる」が用いられる例もあり、読み分けに注意が必要です。
「講じる」という言葉の使い方や例文を解説!
使い方の核心は「対策・策・手段」と組み合わせ、行動まで含意する点にあります。対象はリスク、問題、課題などネガティブ要素が多い一方、イベント成功に向けた「工夫を講じる」のようにポジティブ文脈でも使用可能です。
【例文1】政府は感染拡大を防ぐために厳格な入国管理策を講じる。
【例文2】プロジェクト遅延を回避するため、追加要員投入という手を講じた。
書き方としては「対策を講じる」と「講じる」が文末に来る形が基本で、目的語は必ず具体的な策や手段が置かれます。一方「講じている最中」「講じられる予定」のように進行形・受動形へも容易に変化させられ、文章の柔軟性が高い点も魅力です。
注意点は、話し言葉で乱用するとやや堅苦しく聞こえることです。日常会話で自然さを保つためには「手を打つ」「対策する」など口語的表現とバランスを取り、必要に応じて「講じる」を使い分けるとよいでしょう。
「講じる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「講」は奈良時代に仏教の経典解説会を指した語で、学術的・宗教的文脈から派生したのが「講じる」の原点です。当時、僧侶が集まって経を読み解き、行動指針を示し合う場が「講」でした。その場で得た教えを社会や修行に生かす行為が「講ずる」「講じる」と呼ばれたと考えられています。
平安中期になると、貴族社会で政治的な方策を練る儀式的会合までも「講」と称されるようになります。「講じる」はそこで決まった策略を速やかに実施するという宮中語として定着し、鎌倉期以降に武家や庶民へ広まりました。江戸時代には町人同士の「頼母子講(たのもしこう)」など、共同出資・互助活動にも語が使われ、実際の行動を伴う点がイメージと合致しています。
近代以降、法令や新聞記事で「講じる」が頻出し、現代日本語における「対策を立て実行する」という意味が確立しました。由来をたどると、単なる計画ではなく「共同体が協議し、成果を行動で示す」濃厚な社会性を帯びていることがわかります。
「講じる」という言葉の歴史
文献上の初出は平安時代後期の『今昔物語集』とされ、そこでは僧が災厄回避の法要を「講じた」と記録されています。中世では『吾妻鏡』に「策を講ず」との表記が見られ、源頼朝が軍略を立てる文脈で用いられました。語の核心が「計画+実行」であることは当時から不変です。
江戸期に入ると、町人文化の帳簿や口上書にも「講じ候(こうじそうろう)」が散見され、災害対策や防火体制の整備を指す言葉として浸透します。近世の大火は頻発していたため、「火除けの手を講じる」という表現が町奉行所の記録に多く残っています。
明治維新後、近代法体系の整備に伴い「講じる」は法令用語として採用されました。特に旧内務省の布告では「衛生上必要ナル処置ヲ講ズベシ」といった形で使用されたため、官僚語としての地位が強固になります。現代でも省庁の通達で「当該措置を講じること」とあるように、公式文書での使用頻度は高いままです。
「講じる」の類語・同義語・言い換え表現
同義語としては「施策する」「図る」「実施する」「打つ(手を)」「採る(方策を)」などが挙げられます。これらは「計画+実行」を共通点とするものの、微妙なニュアンス差があります。たとえば「図る」は計画段階の含意が強く、実行が伴わない場合もあります。「実施する」は実行に重きがある一方、策を立てる過程への言及が薄いです。
ビジネス文書でのおすすめ言い換えは「施策を打つ」「策を採る」などですが、公式なトーンを保ちたいときは「措置を講じる」が最も定番です。口語では「手を打つ」「手立てを考える」が自然で、相手に硬さを感じさせにくいメリットがあります。
ただし、契約書やリスク報告のように法的・責任的な重みが必要な場面では「講じる」のほうが適切です。言い換えは状況・文脈・読者層によって選択すると失礼なく意図を伝えられます。
「講じる」の対義語・反対語
対義的な構造を持つのは「放置する」「怠る」「見送る」など、何らかの措置を取らない行為を指す語です。また、「静観する」「様子を見る」も結果的に動きを取らないという点で反対のニュアンスを帯びます。
「講じる」が積極性や計画性を内包するため、対義語は自然と消極性や無作為を表します。たとえば「対策を講じる」の反対は「対策を怠る」であり、文章において責任の所在を強調する際に好対照を形成します。リスク管理やクレーム対応の文書では「必要な措置を講じなかった結果、被害が拡大した」という使い方が典型例です。
ただし「静観する」は必ずしも悪い選択ではなく、状況によっては最善策です。対義語を用いる際は、感情的な非難表現にならないよう客観的評価を付け加えることが重要です。
「講じる」についてよくある誤解と正しい理解
最も多い誤解は「講じる=思いつくだけ」と解釈し、実行フェーズを含まないと思われがちな点です。しかし、辞書的定義では「計画し、実施する」までがワンセットで明記されています。この誤解が生じる背景には、「対策を考える」というライトな口語との混同があります。
次に多いのが「講じる」と「講ずる」の混同です。両者は意味上ほぼ同じですが、現代では「講じる」が主流であることを覚えておくと誤記を防げます。文語調や古文書を読む際に「講ず」が出てきても慌てずに同じ意味と判断してください。
さらに、「敬語的ニュアンスの高さ」を誤って理解する例もあります。実際には尊敬語や謙譲語ではなく、単に語調が硬いだけです。立場が高い相手に対して「講じられる」と受動形敬語を組み合わせることで、初めて丁寧さが担保されます。誤用すると過剰敬語になるため注意しましょう。
「講じる」を日常生活で活用する方法
日常生活でも「危機管理」や「家計改善」など具体策を強調したい場面で「講じる」は有効に働きます。たとえば、家族会議のメモに「光熱費削減策を講じる」と書けば、単なる「節約する」より計画的で実行性の高いニュアンスを醸し出します。
また、自治会やPTAの議事録で「安全対策を講じる」と表現することで、公的公文書と同等の説得力を付与できます。ビジネスメールだけでなく、ボランティア活動の報告書やブログ記事でも「手を講じる」という言い回しを使うと、読者に具体的行動を想起させる効果が期待できます。
コツは、目的語を必ず具体的かつ測定可能なものにすることです。「改善策を講じる」では抽象度が高く、説得力に欠けます。「週次レビュー実施の習慣化を講じる」のように行動が描ける表現へ落とし込むと実行フェーズが明確になります。家庭・職場・地域活動のいずれでも、「講じる」を使いこなすことで文章が締まり、意思決定の責任感が高まります。
「講じる」という言葉についてまとめ
- 「講じる」は計画を立て実行するまでを含む能動的な動詞である。
- 読みは「こうじる」で、送り仮名付きが現代標準表記である。
- 仏教の「講」から派生し、平安期以降に策を実践する語として定着した。
- 公式文書で多用され、日常でも具体策を強調したい時に有効である。
「講じる」は、ただ思いつくだけでなく計画を実行するところまで含む点が最大の特徴です。読みや表記を正しく押さえれば、公的文書から日常メモまで幅広い文章に説得力を持たせられます。
歴史をひもとくと、共同体で教えや策を共有し実践するという背景があり、その社会的ニュアンスが今も色濃く残っています。適切な場面で使いこなし、言葉の力で行動を後押ししてみてください。