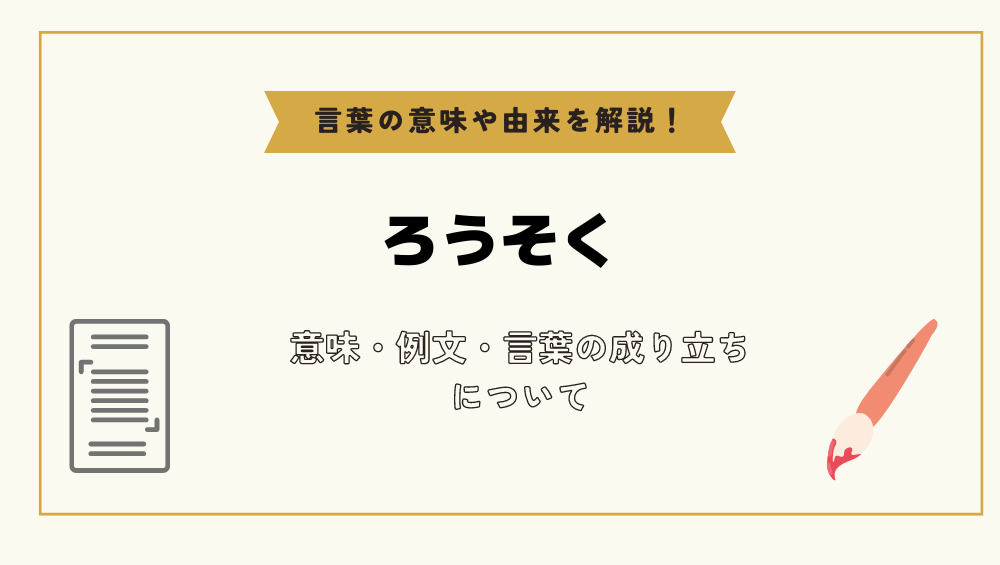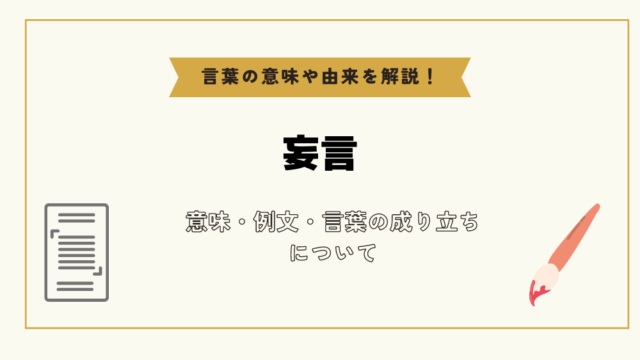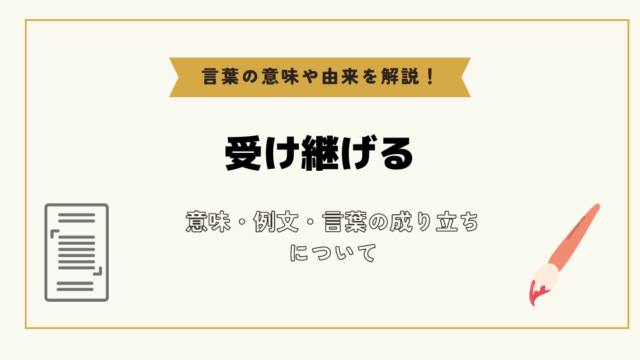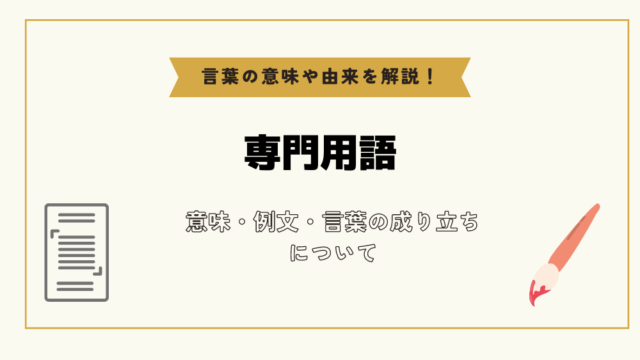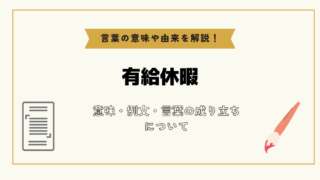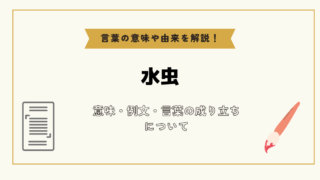Contents
「ろうそく」という言葉の意味を解説!
。
「ろうそく」という言葉は、キャンドルのことを指します。
キャンドルは炎を灯すために使われるアイテムであり、多くの場面で利用されています。
例えば、停電時には暗闇を照らすために、お祝い事やロマンティックなディナーには雰囲気づけとして使用されます。
また、宗教的な行事や儀式でも重要な役割を果たしています。
「ろうそく」という言葉の読み方はなんと読む?
。
「ろうそく」という言葉は、「ろう・そく」と読みます。
日本語の「ろう」という言葉は、キャンドルを表す際に使われることが一般的です。
一方、「そく」という言葉は、燃えることを意味し、ろうそくに火を灯して使用するため、この読み方が一般的となっています。
「ろうそく」という言葉の使い方や例文を解説!
。
「ろうそく」という言葉は様々な場面で使われます。
例えば、「ディナーにろうそくを灯す」という表現は、特別な雰囲気を演出するために使われます。
また、「ろうそくの光で暗闇を照らす」という表現は、停電時などの緊急事態での利用方法を表しています。
「ろうそく」という言葉の成り立ちや由来について解説
。
「ろうそく」という言葉は、古代中国の伝統的な照明器具である「燭」という言葉から派生してきました。
それが日本に伝わり、「ろうそく」となったと考えられています。
「燭」の元々の意味は「明るさをもたらすもの」とされており、そのまま日本語に取り入れられました。
「ろうそく」という言葉の歴史
。
「ろうそく」という言葉は、古代から存在している照明器具の一つです。
古代ローマ時代や古代エジプト時代からキャンドルを使用する習慣があったと言われており、その後中世ヨーロッパで広まり、世界各地で利用されるようになりました。
技術の進歩により、近代では安全性や効率性が向上し、ますます普及するようになってきました。
「ろうそく」という言葉についてまとめ
。
「ろうそく」という言葉は、キャンドルのことを指します。
暗闇を照らすために灯されるキャンドルは、特別な雰囲気を作り出すと共に、停電時や宗教的な儀式などで利用されます。
この言葉の読み方は「ろう・そく」であり、古代中国の「燭」から派生しました。
そして、古代から現代に至るまで、世界中で使われ続けています。