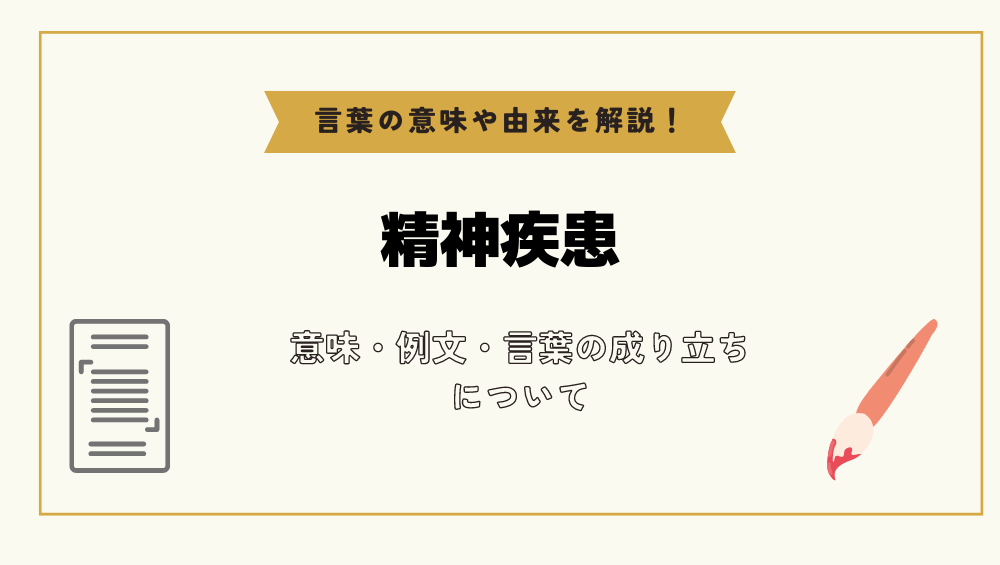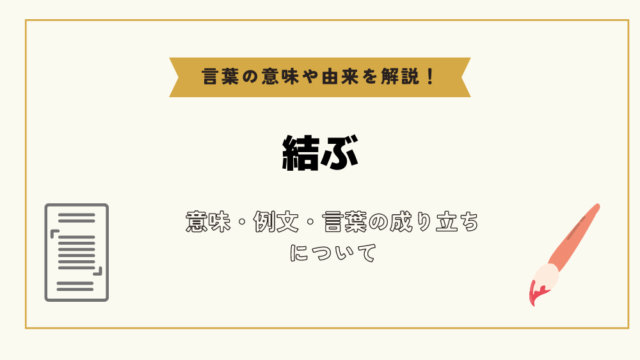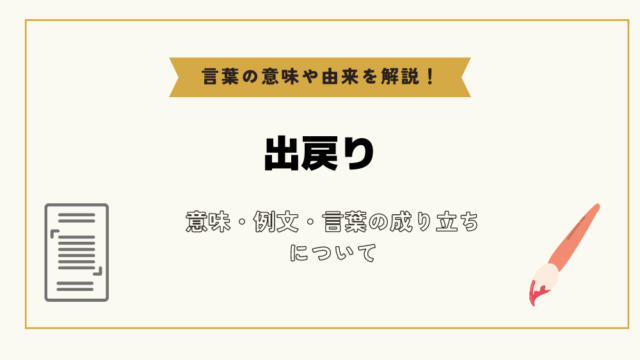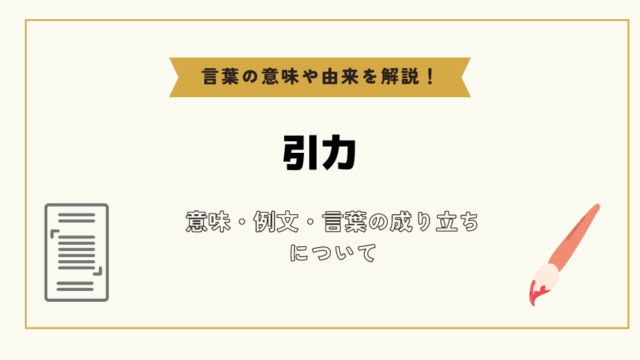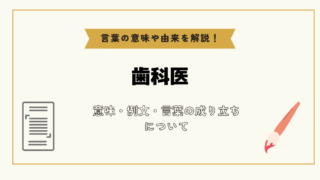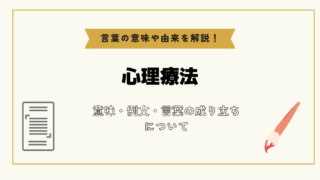Contents
「精神疾患」という言葉の意味を解説!
精神疾患とは、心や精神に関する病気や障害のことを指します。
具体的には、うつ病や統合失調症、パニック障害などがその一例です。
これらの疾患は、心の働きや感情に関わる神経の異常な活動や化学物質のバランスの乱れなどが原因とされています。
精神疾患は身体的な症状だけでなく、日常生活や人間関係にも大きな影響を与えることがあり、早期の診断や適切な治療が重要です。
「精神疾患」の読み方はなんと読む?
「精神疾患」は、せいしんしっかんと読みます。
この言葉は漢字で書かれており、それぞれ「精神(mind)」と「疾患(illness)」という意味を持つ言葉が合わさっています。
精神疾患は、日本語でよく使われる言葉であり、医療や心理学の分野でよく使われています。
「精神疾患」という言葉の使い方や例文を解説!
「精神疾患」という言葉は、心や精神に関する病気や障害を表すのに使用されます。
医療や心理学の専門家、またはその分野に関心を持つ人々がよく使用します。
例えば、「彼は精神疾患を抱えている」という文は、その人が心の病気や障害を抱えていることを意味します。
また、「精神疾患に対する社会的な認識が必要」という文は、精神疾患に対する理解や支援の必要性を表しています。
「精神疾患」という言葉の成り立ちや由来について解説
「精神疾患」という言葉は、日本語の特徴や文化背景に基づいて作られた言葉です。
一部の医学的な専門用語は、英語や他の言語からそのまま借用されることがありますが、精神疾患は日本語で独自に作られた言葉です。
精神疾患の「精神」は心や精神を意味し、「疾患」は病気や障害を意味します。
このように、日本語を基にした言葉であるため、日本語の文化や思考の特徴が反映されています。
「精神疾患」という言葉の歴史
「精神疾患」という言葉は、精神科の研究や治療の歴史とともに発展してきました。
昔の日本では、精神疾患に対する理解や対応が不十分であったため、患者は社会的な偏見や差別に苦しめられることがありました。
しかし、近年では精神疾患の啓発活動や医療の進歩により、より包括的なサポートが行われるようになりました。
精神疾患に対する理解や寛容な社会を築くためには、さらなる取り組みが求められています。
「精神疾患」という言葉についてまとめ
「精神疾患」とは、心や精神に関連する病気や障害のことを指します。
これらの疾患は、神経の異常な活動や化学物質のバランスの乱れなどが原因とされています。
精神疾患は、身体的な症状だけでなく、日常生活や人間関係にも大きな影響を与えます。
早期の診断や適切な治療が重要です。
精神疾患に対する社会的な認識や支援の必要性も高まっています。