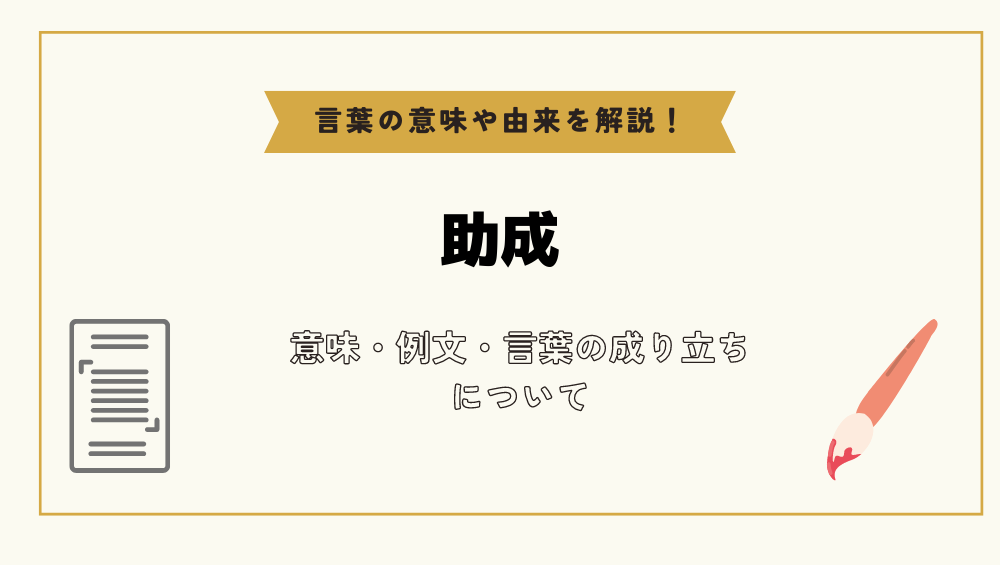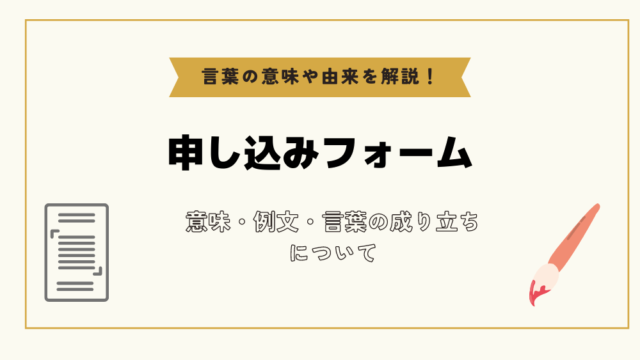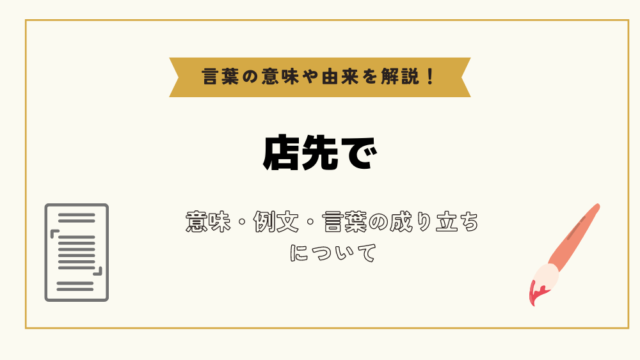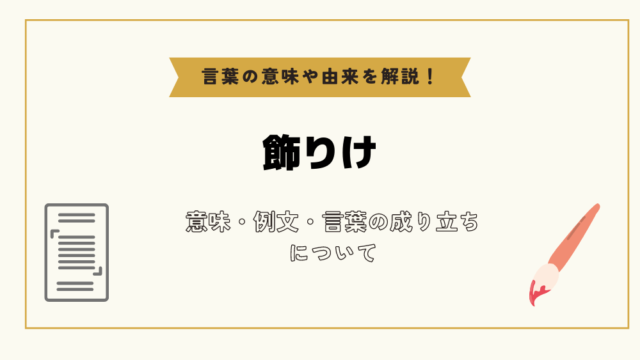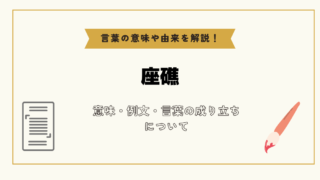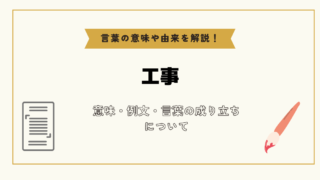Contents
「助成」という言葉の意味を解説!
助成とは、他人や組織が困難に直面している人や事業に対して支援や援助を行うことを指します。
例えば、教育や文化・芸術などの分野で活動している団体が助成金を受けて事業を行ったり、福祉施設の運営費を補助するために自治体が助成を行ったりすることがあります。
助成の目的は、社会福祉や文化の振興、教育の推進など社会全体の発展や向上を図ることです。
助成は生活や活動の基盤を支える重要な役割を果たしており、多くの人々や組織にとって重要な存在となっています。
「助成」という言葉の読み方はなんと読む?
「助成」という言葉は、ふつうの読み方が「じょせい」となります。
「じょ」と「せい」の2つの音で表されますが、語感的には親しみやすく、なんとなく温かみのある印象を受けることが多いようですね。
大切なのは、その言葉が持つ助け合いや支援の意味を理解し、実際に行動に結び付けることです。
「助成」という言葉の使い方や例文を解説!
「助成」という言葉は、具体的な支援や援助行為に関する文脈で使用されます。
例えば、「自治体は地域のスポーツクラブに助成金を交付した。
」「この事業は財団からの助成を受けて行っています。
」などです。
また、助成を受ける側の立場で使われる場合には、「助成を申請する」「助成を受ける資格がある」といった表現がよく使われます。
「助成」という言葉の成り立ちや由来について解説
「助成」という言葉の成り立ちや由来は、古代中国の文献や漢字の語源から追うことができます。
「助成」は、漢字の「助」と「成」で構成されています。
「助」は相手の困難や劣っている点を支える意味を表し、「成」は完成や達成を意味します。
つまり、「助成」は相手を助けて成長させるという意味を持ち、この言葉が日本に伝わったことで、支援や援助の行為を指すようになったと考えられます。
「助成」という言葉の歴史
「助成」という言葉の歴史は古く、日本の古典文学や歴史書にも登場します。
江戸時代には、幕府や各藩が学問や文化の振興を目的として、財政的な援助や人材の育成を行っていました。
このような取り組みが助成の先駆けとされています。
現代でも、国や地方自治体、民間の団体などが様々な分野で助成制度を設け、社会の発展や文化の振興を目指しています。
「助成」という言葉についてまとめ
「助成」という言葉は、他人や組織が困難に直面している人や事業に対して支援や援助を行う意味を持ちます。
読み方は「じょせい」となり、親しみやすく温かみのある印象を与えます。
助成は社会の発展や向上を促進するための重要な役割を果たしています。
様々な分野で助成制度が設けられており、多くの人々や組織にとって支えとなっています。
助成の成り立ちや歴史を知ることで、その意味や重要性をより深く理解することができます。