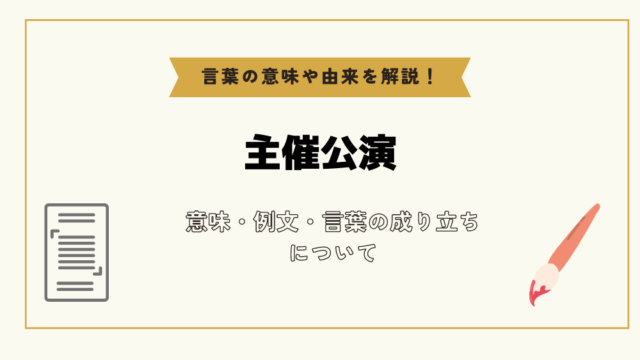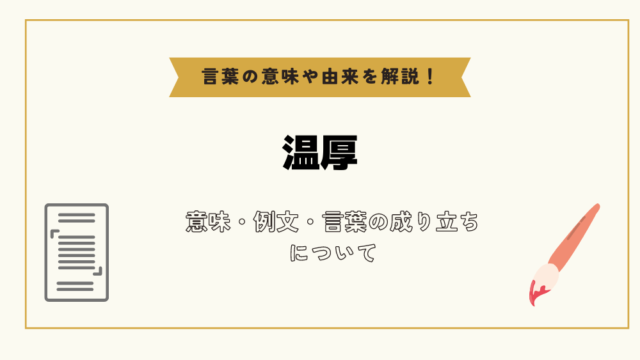Contents
「掛かる」という言葉の意味を解説!
「掛かる」という言葉は、さまざまな意味で使われます。
まずはその基本的な意味を解説しましょう。
一つ目の意味は、時間や労力、費用がかかることです。
「時間が掛かる」とは、何かをするのに時間が必要であることを表します。
「大掛かりな改装工事には数ヶ月かかる」というような使い方が一般的です。
二つ目の意味は、物が取り付ける・乗る・かかることです。
「壁に絵を掛ける」とか「電車に乗る」というような使い方があります。
「カーテンレールにカーテンを掛ける」というのもこの意味になります。
三つ目は、病気やトラブルになることです。
「風邪を掛ける」とか「転倒して骨折を掛ける」というような使い方です。
「掛かる」という単語が使われるのは、何かに影響を受けたり、結果として何かが生じる場合がほとんどです。
「掛かる」という言葉の読み方はなんと読む?
「掛かる」という言葉は、一般的に「かかる」と読みます。
この「かかる」という読み方は、日本語の基本的な読み方の一つです。
他にも「掛かる」を「かける」と読むこともありますが、意味や使い方によって使い分けられる場合があります。
「かかる」と読む場合、アクセントは「か」にあります。
つまり、「かかる」と発音する際には、「か」の部分を強く発音すると良いでしょう。
「掛かる」という言葉の使い方や例文を解説!
「掛かる」という言葉は、さまざまな場面で使われます。
ここではその使い方や例文を解説します。
まず使い方ですが、前述したように「時間が掛かる」や「費用が掛かる」という形で使われることがよくあります。
例えば、「そのプロジェクトには多くの時間が掛かる」といった具体的な例文です。
また、「掛かる」と「~に~が掛かる」という形で使われることもあります。
例えば、「彼には多くの責任が掛かる」といった使い方です。
この場合、責任が彼にかかるという意味になります。
さらに、物がかかる意味でも使われます。
例えば、「壁に掛ける」とか「肩にかばんを掛ける」といった使い方です。
この場合、物が壁などに取り付けられるという意味になります。
「掛かる」という言葉の成り立ちや由来について解説
「掛かる」という言葉の成り立ちや由来について解説します。
「掛かる」の語源は諸説ありますが、古代中国の言葉「架る(かる)」に由来すると言われています。
「架る」とは、物を支えるために橋や建造物の一部を作るという意味です。
その後、「架る」から派生して現代の「掛かる」という形になったものと考えられます。
「掛かる」という言葉は、物が何かに取り付けられるという意味だったり、時間や労力がかかるという意味だったり、幅広い用途に使われるようになりました。
「掛かる」という言葉の歴史
「掛かる」という言葉の歴史について解説します。
「掛かる」という言葉は、日本語の古典文学においてもしばしば登場します。
古くは万葉集や平安時代の文学作品などにも見られます。
また、江戸時代から明治時代にかけての文学や口承文化でも頻繁に使われています。
例えば、浄瑠璃や歌舞伎の演目や講談、寄席などで「掛かる」という言葉が使われたことが知られています。
現代でも、日常会話や文学作品、メディアなどで「掛かる」という言葉が依然として広く使われています。
「掛かる」という言葉についてまとめ
以上で、「掛かる」という言葉についてまとめました。
「掛かる」とは、時間や労力、費用がかかることや物が取り付けられること、病気やトラブルになることなどさまざまな意味で使われます。
「掛かる」という言葉の読み方は、「かかる」が一般的であり、アクセントは「か」にあります。
また、「掛かる」という言葉は古代中国の言葉「架る」が語源であり、現代の日本語に発展してきたと考えられます。
繰り返し使われる言葉である「掛かる」は、日本語の基本的な語彙の一つとも言えます。
日常会話や文学作品、メディアなどで幅広く使用されているため、しっかりと理解し、使いこなせるようになりましょう。