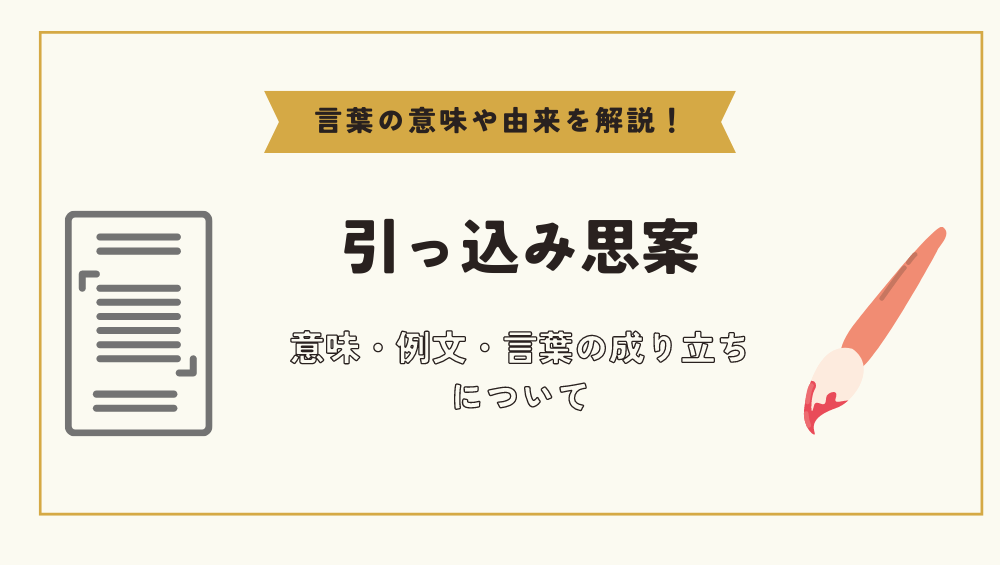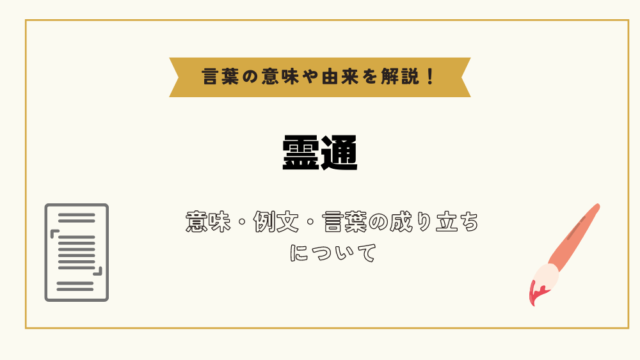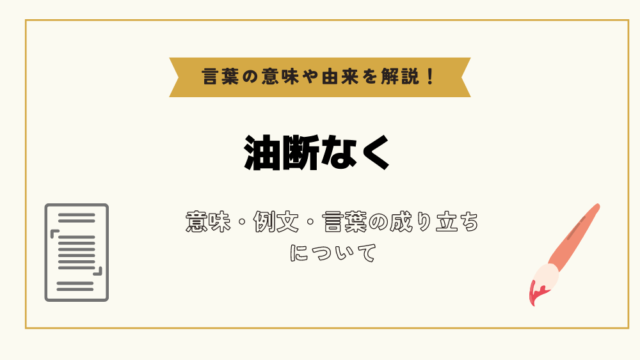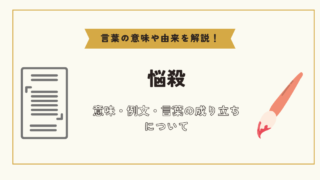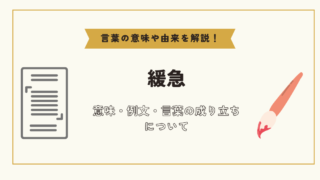Contents
「引っ込み思案」という言葉の意味を解説!
「引っ込み思案」という言葉は、人の性格や態度を表す言葉です。引っ込み思案とは、自己主張が苦手で控えめな態度をとることを指します。社交的な場において、自分の考えや感情をうまく表現できず、内に引っ込みがちな性格を持つ人によく使われる言葉です。
「引っ込み思案」の読み方はなんと読む?
「引っ込み思案」は、「ひっこみじあん」と読みます。日本語の読み方にはいくつかのバリエーションがありますが、一般的にはこの読み方が広まっています。
「引っ込み思案」という言葉の使い方や例文を解説!
「引っ込み思案」は、自己主張が苦手な人の性格を表現する言葉として使われることが多いです。「引っ込み思案の彼は、会議では発言せずに黙っていることが多い」といった具体的な例文があります。また、「彼女は引っ込み思案な性格だが、自分の意見をしっかりと伝えることができるようになりたいと思っている」といったように、自己改善や成長の意思を示す使い方もあります。
「引っ込み思案」という言葉の成り立ちや由来について解説
「引っ込み思案」は、日本語の言葉であり、その成り立ちや由来には明確な情報はありません。ただし、「引っ込む」という言葉は、もともとは「奥へと入り込む」という意味で使われていましたが、その転じて「自己を内に閉じ込める」といった意味合いになったと考えられています。
「引っ込み思案」という言葉の歴史
「引っ込み思案」は、日本語としては比較的新しい言葉です。現代の表現として使われるようになった経緯や、具体的な起源については詳しい情報はありません。しかし、社会や人間の性格に関する言葉として一般的に使われ、認知度も高まってきています。
「引っ込み思案」という言葉についてまとめ
「引っ込み思案」という言葉は、自己主張が苦手で内向的な性格を持つ人を表す言葉です。人とのコミュニケーションや社会的な場での活動に苦手意識を持つ人々によく使用されます。この言葉を通じて、引っ込み思案な性格を持つ人々に共感や理解を示すことが重要です。