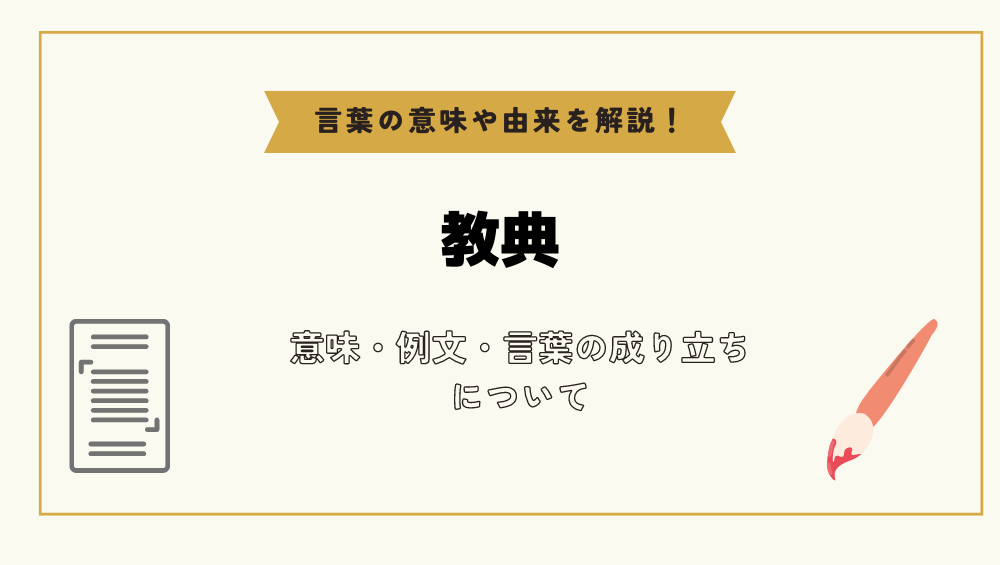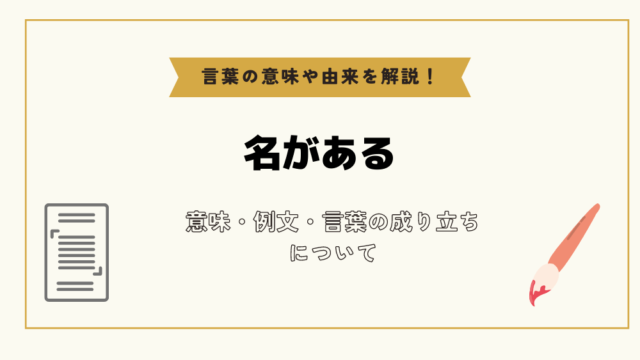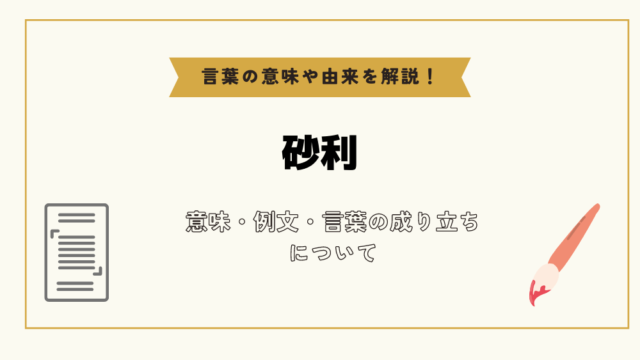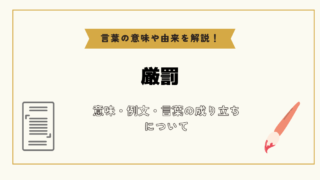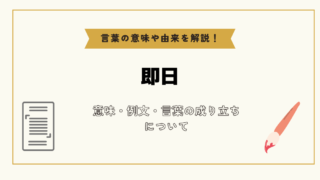Contents
「教典」という言葉の意味を解説!
「教典」という言葉は、信仰や教育を基盤とした宗教書や教育書のことを指します。
教義や教えが記され、その宗教や教育の基本原理を示す書物のことです。
「教典」は特定の宗教や教義に関連していることが多く、その宗教や教育において絶対的な権威を持っているものとして重視されています。
「教典」の読み方はなんと読む?
「教典」は、「きょうてん」と読みます。
日本語の発音のルールに従って「きょう」は「キョウ」ではなく、「きょう」となります。
「てん」は「テン」と読むのではなく、中国の読み方を応用して、「てん」と読むことが一般的です。
「教典」という言葉の使い方や例文を解説!
「教典」という言葉は、特定の宗教や教育において使用されることが一般的です。
例えば、仏教における「仏典」という言葉や、キリスト教における「聖典」という言葉が「教典」の一例と言えます。
「教典」を用いた例文としては、「彼は教典の教えを厳粛に守っている」という文があります。
「教典」という言葉の成り立ちや由来について解説
「教典」という言葉は、中国語の影響を受けた言葉です。
中国語では「教」は「教える」という意味であり、「典」は「規範や基準」といった意味合いがあります。
この二つの言葉を組み合わせることで、「教えるための規範や基準」という意味が成り立ちました。
「教典」という言葉の歴史
「教典」という言葉の歴史は古く、宗教や教育の発展とともに形成されてきました。
古代の聖典や仏典、経典などが、後の「教典」という概念の基礎となっています。
宗教や教育の発展に伴い、各宗教や学問における「教典」も増え、多様性を持つようになってきました。
「教典」という言葉についてまとめ
「教典」という言葉は、宗教や教育において重要な書物を指す言葉です。
「教典」は信仰や教育の基礎となり、その宗教や教育の中心的な役割を果たしています。
さまざまな宗教や学問において「教典」が存在し、その内容や意義も多様です。
知識や学びを深める上で、「教典」という言葉は重要であると言えます。