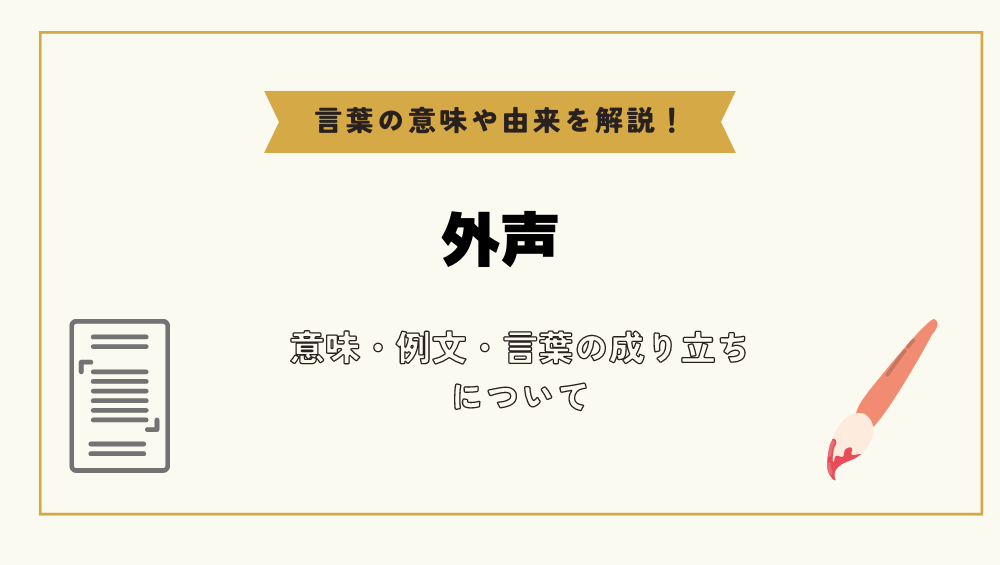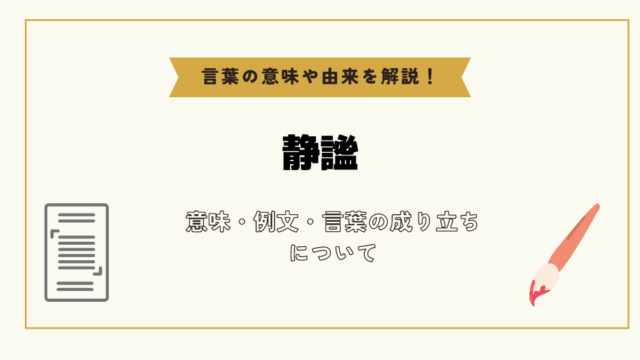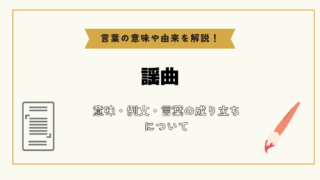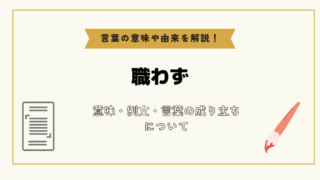Contents
「外声」という言葉の意味を解説!
「外声」という言葉は、他の人が耳にするような大きな声のことを指します。
つまり、自分の声を他の人に向けて出すことを指す言葉です。
例えば、講演やプレゼンテーションなどで大勢の人に向かって話をする場合、外声を使います。
外声は、声を出すだけでなく、相手に聞こえる音量や発音の仕方にも注意が必要です。
しっかりと意思を伝えるためには、声をしっかりと出し、はっきりと発音することが大切です。
「外声」という言葉の読み方はなんと読む?
「外声」という言葉は、「がいせい」と読みます。
声の外側に向けて出す声という意味合いから、このような読み方になりました。
日本語の読み方の特徴である「外来語」のように、外国の言葉になじませる形で読まれることが一般的です。
「がいせい」という読み方は、堅苦しくなく、親しみやすい印象を持たせます。
このような読み方を使うことで、人間味が感じられる文章を作ることができます。
「外声」という言葉の使い方や例文を解説!
「外声」という言葉は、例えば以下のような使い方ができます。
1. 「一度外声で読んでみてください。
」
。
2. 「彼は外声で大きな声で話した。
」
。
3. 「大勢の人に向かって外声で挨拶をしました。
」
。
このように、「外声」という言葉は、声の音量や大きさを強調する際に使われます。
特に公の場でのスピーチやプレゼンテーションなどでよく使われます。
「外声」という言葉の成り立ちや由来について解説
「外声」という言葉は、中国の古典である「論語」に由来しています。
論語の中には、「外声盈譬」(がいせいえいいつ)という言葉があります。
これは、「外からの声は内側まで満たす」という意味で使われます。
日本語において「外声」という言葉が使われるようになったのは、江戸時代からです。
当時の人々は、公の場や人々への発信の重要性を認識し、声を大きく届けるために「外声」という言葉を使い始めました。
「外声」という言葉の歴史
「外声」という言葉の歴史は、古代中国の「論語」までさかのぼります。
この言葉は、声の響きが内側まで届くことを意味していました。
そして、江戸時代になると、日本でも「外声」という言葉が使われ始めました。
その後、明治時代になると、近代的なコミュニケーション手段が発展し、声以外の方法でも情報を伝えることが可能になりました。
しかし、「外声」という言葉は、今でも声の大きさや届け方を強調する際に使われています。
「外声」という言葉についてまとめ
「外声」という言葉は、自分の声を他の人に向けて出すことを指します。
声の大きさや届け方を強調する際に使われます。
日本では江戸時代から使われ始め、古代中国の「論語」に由来しています。
親しみやすい印象を持たせるためには、「がいせい」という読み方が一般的です。
みなさんも、大勢の人に向けて情報を伝える際には、外声を使ってみてください。
対象者に確実に伝わるように声を出し、はっきりと意思を示すことで、効果的なコミュニケーションが行えるでしょう。