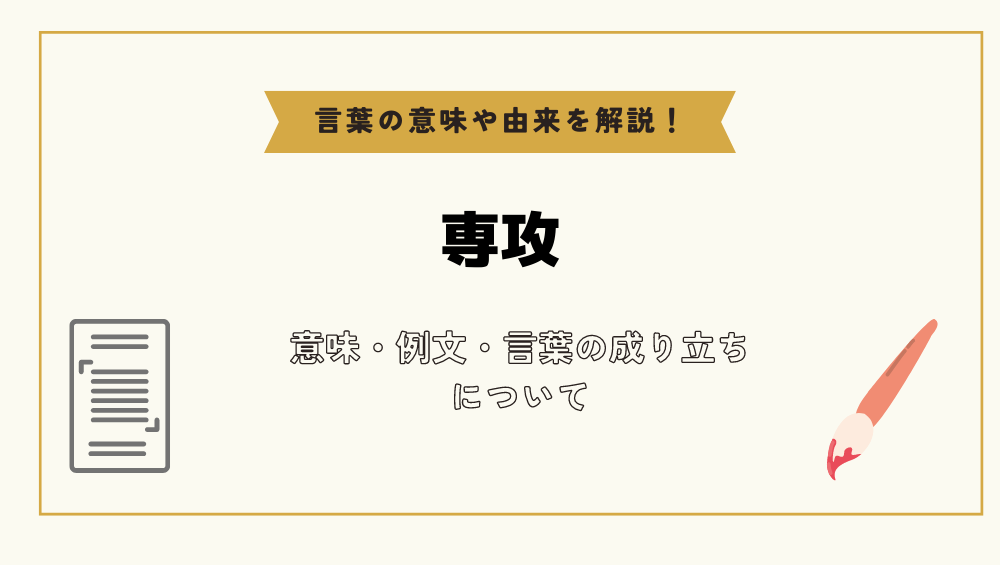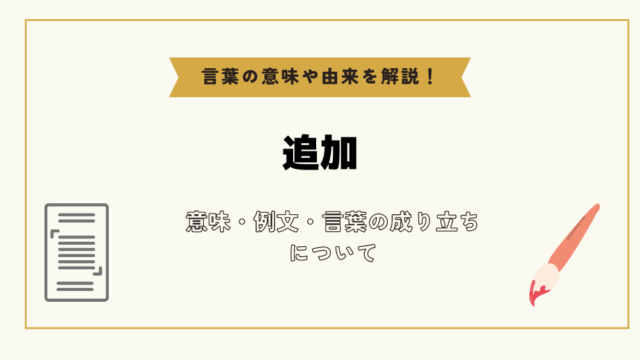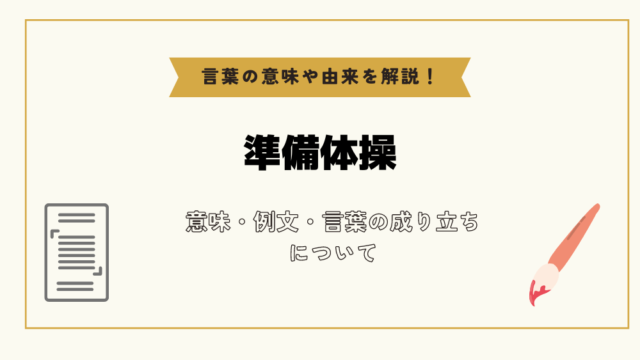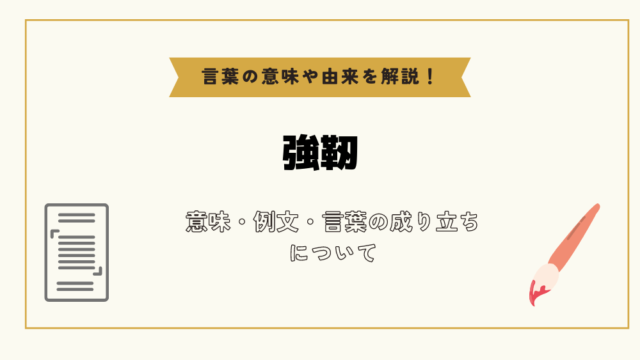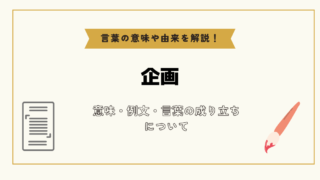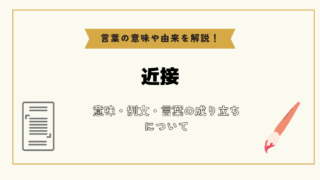「専攻」という言葉の意味を解説!
「専攻」とは、数ある学問や技芸の中から特定の分野を選び出し、集中的かつ体系的に学ぶことを指す言葉です。大学や大学院では「心理学専攻」「経済学専攻」などのように、履修課程そのものを示す場合が最も一般的です。社会人向け講座や資格スクールでも「〇〇専攻コース」という表現が見られます。
「専」という字には「もっぱら・ひとすじに」という意味があります。一方「攻」は「せめる」だけでなく「きわめる」「努力して身に付ける」の意も持ちます。二つが結び付き、特定領域に集中して取り組むニュアンスを生み出しました。
文部科学省の学位規程においては、専攻は教育課程の最小単位として定義されています。つまり、学位名称(学士・修士・博士)と併せて「〇〇学専攻」が並ぶことで、どの専門知識を修めたかが明確になる仕組みです。
学術の場に限らず、「専攻」は自分の強みや専門性を示す名刺代わりのキーワードとしても機能します。たとえば履歴書やSNSのプロフィール欄に書き添えることで、読んだ人に得意分野を伝えやすくなります。
その一方で、複数の分野を横断的に扱う学際領域では「専攻」という枠組みがかえって曖昧になるケースもあります。研究テーマが細分化・融合化している現代では、「専攻名」と実際の研究内容が必ずしも一対一で対応しないという課題も指摘されています。
「専攻」の読み方はなんと読む?
「専攻」は音読みで「せんこう」と読みます。学校教育で習う常用漢字の範囲に含まれ、小学生でも読めるレベルの語ですが、社会的には主に中等教育以降で触れることが多い語です。
「専」は「セン」「もっぱら」、そして「攻」は「コウ」「せめる」と読みます。漢字検定ではいずれも5級レベルの出題範囲とされ、比較的読みやすい部類です。とはいえ熟語としての「専攻」を誤って「せんこうぶ」「せんこうこう」と読んでしまうケースも散見されるため注意が必要です。
発音のアクセントは東京式で「せんこう(LHH)」が一般的です。地方方言によっては「センコー(HLL)」と頭高になる地域もありますが、公的な場ではLHHが推奨されます。電話応対や司会などで口にする際は、語尾をやや下げると聞き取りやすくなります。
留学生の日本語学習では“Narrowing Major”の概念が母語にない場合もあり、読み方とあわせて意味を丁寧に教える必要があります。読み方を押さえることは、意味を正確に伝える第一歩です。
「専攻」という言葉の使い方や例文を解説!
研究や就職活動、趣味の場面まで幅広く登場するのが「専攻」という語です。以下の使い方のポイントを押さえると、誤用を減らせます。「専攻」は名詞であり、「専攻する」の形で動詞的にも使える点が特徴です。
第一に、自己紹介における使用例です。「私は大学で物理学を専攻しています。」のように、自身の学問分野を示します。第二に、他者を紹介する場合。「彼女の専攻は文化人類学で、アフリカ研究が専門です。」とすると、相手の得意領域を端的に表せます。
【例文1】「情報科学を専攻した経験を生かし、AI分野の企業に就職しました」
【例文2】「彼は大学院で医療統計を専攻し、臨床データ解析に携わっています」
第三のポイントは、専門外との区別を明示できることです。「趣味で写真を撮っていますが、専攻は経済学です」と言えば、本業との違いを示せます。
ライティングやスピーチでは、同じ文中に「専攻分野」と重ねて書くと冗長になります。「専攻」の後に具体的な分野名を置くか、「専門分野」と言い換えるとすっきりします。
最後に注意点です。履歴書やエントリーシートでは正式名称を記載することが望ましく、略称や俗称は避けた方が無難です。「化学専攻」ではなく「応用化学専攻」など、大学公式の表記を確認しておくと信頼性が高まります。
「専攻」という言葉の成り立ちや由来について解説
「専攻」は中国古典に源流を持つとする説が有力です。「専」は『孟子』などでも見られる語で、「ひとつのことに集中する」を表しました。「攻」は戦いを意味するほか、『礼記』では「学問を深める」の用例が確認できます。この二字が組み合わさり、特定の学技を深耕するという意味が確立したと考えられます。
日本では奈良時代から「攻む(おさむ)」が「学問を積む」を指す動詞として使用されており、平安中期の文献にも見受けられます。ただし熟語「専攻」がまとまった形で登場するのはずっと後の近世以降です。
江戸後期、蘭学書の翻訳過程で「speciality」を訳す際に「専攻」があてられた記録が残ります。幕末の医師・箕作阮甫の門下に伝わる資料に「医道専攻」という表現があり、専門医教育の概念と結び付いていたことがわかります。
明治期に入ると学制改革でドイツ語の“Fach”や“Studienfach”を導入する必要が生じ、文部省は「専攻」を公式用語として採用しました。結果として「専攻」は高等教育制度の中核語彙として定着し、現在まで脈々と受け継がれています。
「専攻」という言葉の歴史
明治5(1872)年の学制発布では、「学科」という語が主に使われていました。しかし帝国大学令(明治19年)制定時に、ドイツ大学を範とした「学部・学科・専攻」区分が導入され、正式に「専攻」が法令に登場します。これが日本の近代教育での転機でした。大学史をたどると、「専攻」の位置づけは制度改正ごとに変化しながらも、専門教育の深度を表す最小単位として一貫して残っていることがわかります。
戦後の学制改革では、アメリカのメジャー制を参照して「主専攻(メジャー)」「副専攻(マイナー)」の枠組みが提案されます。実際に制度化した大学もあれば、単位制の中で柔軟に運用する大学もあり、多様化が進みました。
1970年代以降、学際研究の台頭に伴い「〇〇学専攻」という硬直的な名称に対し、より広域な「人間科学専攻」「環境共生専攻」など新語が多数生まれます。2000年代には大学院重点化で「専攻科目群」「先端専攻」も導入され、時代の要請を反映してきました。
近年、オンライン大学や専門職大学院の増加により、履修モデルが変わりつつあります。それでも「専攻」という語自体は教育課程のコア概念として存続し、多くの学生・研究者にとって道標となっています。
「専攻」の類語・同義語・言い換え表現
類語としてまず挙げられるのが「専門」です。両者はしばしば同義で扱われますが、「専門」は技能や職業上の領域を強調し、「専攻」は教育課程や研究テーマを示す色合いが強いと言えます。他にも「分野」「領域」「フィールド」などが文脈によって置換可能です。
「主専攻」「副専攻」という大学制度用語もほぼ同義で用いられます。また医学界では「専攻医」という語が存在し、臨床研修医修了後に専門分野を深める医師を指す用語として定着しています。
企業の研修部門では「コース」「トラック」が近い概念です。「技術トラック」「マネジメントトラック」のようにキャリアパスを示しますが、学術的評価を伴わない点で違いがあります。
言い換えの際は対象のニュアンスを損なわないように心掛けてください。たとえば研究室紹介記事では「〇〇学を主たる研究分野とする」などと書き換えると、読者に分かりやすい文章になります。
「専攻」を日常生活で活用する方法
大学や職場を離れても、「専攻」という視点を持つことで自己成長のヒントを得られます。日常生活での活用とは、興味をもったテーマを意識的に“自分の専攻”として設定し、学習計画を立てることです。
第一ステップは、対象を明確に絞ることです。料理なら「パン作り専攻」、スポーツなら「マラソン専攻」と宣言してみましょう。対象が決まれば、情報収集・反復練習・アウトプットという専門教育の方法論を応用できます。
第二ステップは成果の見える化です。ブログや動画で「〇〇専攻の学習記録」を公開すると、モチベーションが維持しやすくなります。外部からフィードバックも得られるため、学びの質が向上します。
【例文1】「今年は写真編集を専攻すると決め、毎週新しいレタッチ技法を試しています」
【例文2】「友人と一緒に発酵食品専攻チームを作り、味噌や醤油を手作りしています」
第三ステップはコミュニティ参加です。同じ関心を抱く人と意見交換することで、多角的な知見が得られます。また自ら講師役を務めることで、知識が整理され理解が深まります。
このように、「専攻」という概念をプライベート学習に取り込むと、趣味の域を超えた専門性が育ち、人生の幅が広がります。自分だけの“マイ専攻”を設定することは、生涯学習社会における新しいキャリア形成の一助となるでしょう。
「専攻」という言葉についてまとめ
- 「専攻」とは特定の分野を集中的に学ぶことを示す語で、学術・教育現場で広く用いられる。
- 読み方は「せんこう」で、正式な場では音調LHHが推奨される。
- 中国古典の語義を基に明治期の学制改革で定着し、専門教育の最小単位として発展してきた。
- 履歴書では正式名称を記載し、日常生活でも“マイ専攻”として学習計画に応用できる。
「専攻」は単なる学校用語ではなく、自らの学びの軸を示すラベルです。大学制度の中で築かれた歴史的背景を理解すると、言葉の重みが感じられるでしょう。
読む人にとっては、履歴書や面接時に自分の強みを伝えるキーワードとなります。また趣味や副業の学習にも応用しやすく、生涯学習の視点からも価値が高い語と言えます。意味・読み方・歴史を押さえたうえで、自分らしい「専攻」を持ち、深めていく姿勢が今後ますます重要になります。