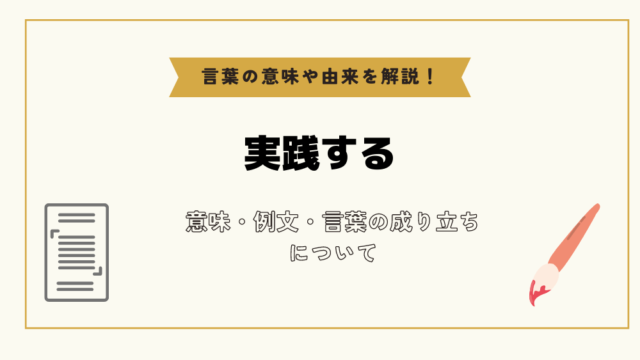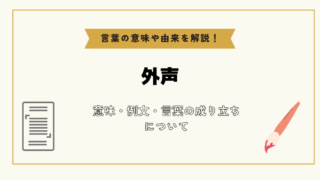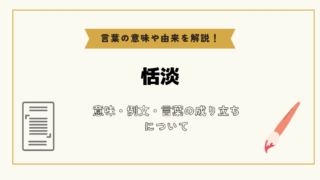Contents
「職わず」という言葉の意味を解説!
「職わず」という言葉は、一般的には「職につかないこと」という意味で使われます。つまり、仕事に就かずに何もしていない状態を指す言葉です。この言葉は、主に若者やニートといった社会的な問題に関連して使われることが多いです。
「職わず」はネガティブな意味合いが強い言葉ですが、必ずしも悪いことを指すわけではありません。例えば、自分の進路を模索するために職に就かない期間を設ける場合や、社会的なルールに縛られずに自由な生き方を選ぶ意思表明に使われることもあります。
「職わず」の読み方はなんと読む?
「職わず」という言葉の使い方や例文を解説!
「職わず」という言葉は、以下のような使い方や例文があります。
・「彼は職わずの生活を送っている。」
この文は、彼が仕事に就かずに暮らしていることを表しています。
このように、「職わず」は、仕事をしていない状態を表現する際に使われます。
・「職わずといっても、自分の進路を模索しているんですよ。」
この文は、職に就いていないけれども、自分の将来の方向性を探っていることを表しています。
ここでは、「職わず」が、仕事に就かない期間にも意味合いを持つことがわかります。
いずれの例文も、「職わず」という言葉が仕事に就かない状態を表していることが伺えます。
「職わず」という言葉の成り立ちや由来について解説
「職わず」という言葉の成り立ちや由来については明確な資料はありませんが、日本語の中には「職に就かずに暇を持て余すこと」という意味を表す言葉は存在します。それらの言葉と同様に、「職わず」も同じような意味を持つようになったと考えられます。
また、「職わず」という言葉は、仕事に就かずに暮らす人々に対する社会の偏見やステレオタイプを反映しているとも言えます。社会的な価値観が労働に重きを置く傾向にある日本において、仕事をしないという選択は一般的には好ましくないとされています。
「職わず」という言葉の歴史
「職わず」という言葉がいつから使われるようになったかははっきりしていませんが、若者やニートといった社会的な問題が表面化するにつれて使用されるようになったと考えられます。
特に、バブル期の経済状況が崩壊し、就職の難しさが問題視されるようになると、「職わず」という言葉の使用頻度も増えたと言われています。その後も、就職氷河期や景気の低迷など、経済的な要因によって「職わず」という言葉が注目され続けています。
「職わず」という言葉についてまとめ
今回は、「職わず」という言葉について解説しました。この言葉は、仕事に就かずに暮らす状態を表すものであり、一般的には否定的な意味を持っています。しかし、一方で自分の進路を模索する期間や自由な生き方の選択としても用いられることもあります。
「職わず」という言葉は、社会的な問題や経済状況と密接に関係しており、日本の労働観や価値観を反映していると言えるでしょう。