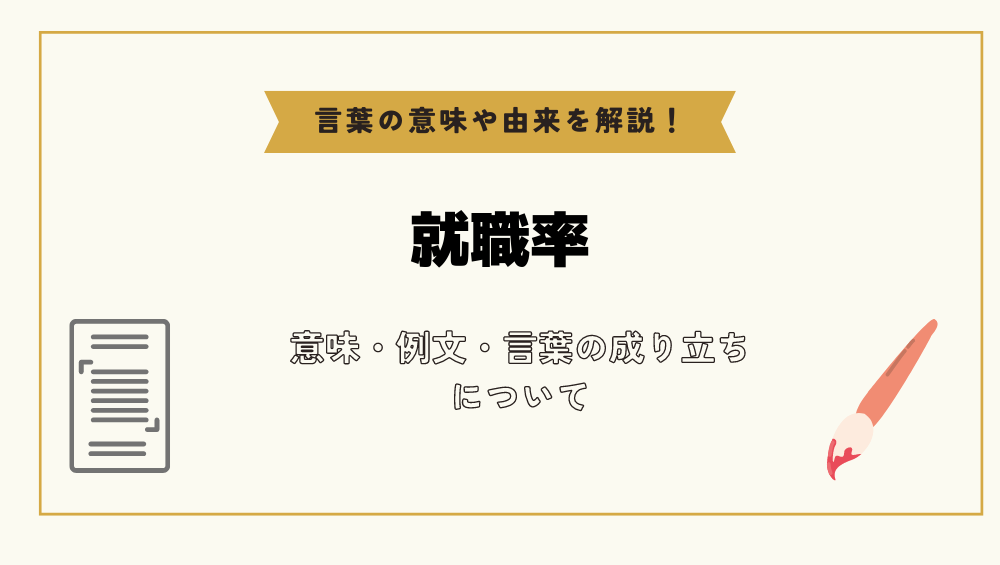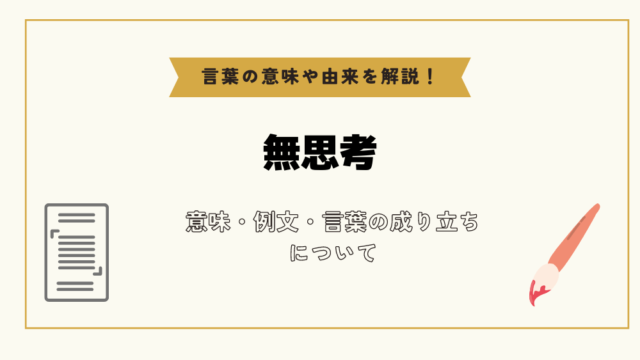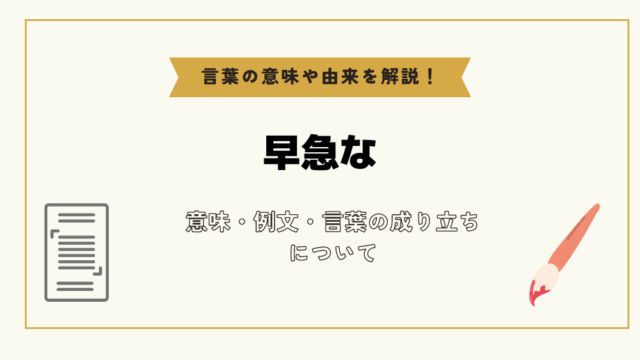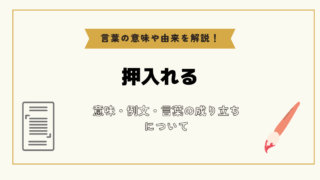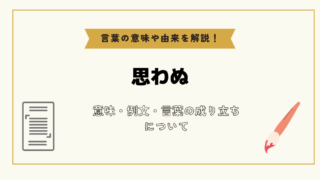Contents
「就職率」という言葉の意味を解説!
「就職率」とは、ある期間内に就職した人の割合を示す指標です。
具体的には、大学や高校、専門学校などの卒業生が一定期間内に就職した人の数を、卒業生総数で割ったものです。
この指標は、学校や地域の教育水準や産業の活性化度合いを示す重要なデータとなっています。
高い就職率は、学校の教育力や産業の発展による経済の安定を示す一つの指標となります。
就職率は、学生や若者にとっても重要な情報です。
自分が通う学校や地域の就職率を把握することで、将来の進路についての考え方や決定に役立てることができます。
「就職率」という言葉の読み方はなんと読む?
「就職率」という言葉は、日本語の読み方で「しゅうしょくりつ」と読みます。
日本語の読み方に沿って発音すると、そのまま「しゅうしょくりつ」となります。
「就職率」は日本語の言葉なので、日本語の読み方で表記されます。
読み方を間違える心配はありませんので、安心して使用することができます。
「就職率」という言葉の使い方や例文を解説!
「就職率」という言葉は、教育関連の場や経済ニュースなどでよく使用されます。
具体的な使い方としては、以下のようなものがあります。
・今年の大学の就職率は過去最高になった。
。
・高い就職率を誇る専門学校が注目を集めている。
。
・就職率向上のためには、学校と企業の連携が重要である。
。
就職率の使い方はとてもシンプルです。
主語に「大学」「専門学校」といった具体的な教育機関を置いて、「就職率が高い」や「就職率が向上する」といった形で使用することが一般的です。
「就職率」という言葉の成り立ちや由来について解説
「就職率」という言葉は、日本の教育制度の発展とともに生まれた言葉です。
日本では学校教育が重視されており、多くの学生が将来の進路として「就職」を選択します。
そこで、学校や地域の教育力や経済の健全性を測るために「就職率」という指標が使われるようになりました。
就職率は、学校や地域の経済的な健全性や教育の質を評価するための手がかりとなる重要なデータとして、広く利用されるようになりました。
「就職率」という言葉の歴史
「就職率」という言葉の歴史は、日本の戦後の教育改革の進展とともに始まります。
戦後は日本の経済が急速に発展し、高等教育への進学者が増加しました。
これに伴い、「就職率」という言葉が注目されるようになりました。
1960年代以降、大学や高等専門学校の普及が進み、就職率は社会的な関心事となりました。
特にバブル時代には就職率が高い学校への進学が注目され、競争率が激化した時期もありました。
現在では、就職率は教育の質や社会情勢の指標として重要視されています。
就職率を高めるための教育政策や企業との連携などが取り組まれており、就職支援の重要性がますます増しています。
「就職率」という言葉についてまとめ
「就職率」という言葉は、ある期間内に就職した人の割合を示す指標です。
学校や地域の教育力や経済の健全性を評価するための重要なデータとして使われています。
「就職率」は「しゅうしょくりつ」と読みます。
具体的な使い方としては、学校や地域の就職率が高いことや向上することを示す例文が一般的です。
「就職率」の成り立ちや由来は、戦後の教育改革の進展とともに生まれたものです。
現在では、就職率は日本の教育の質や社会の健全性を測る指標として重要な位置を占めています。