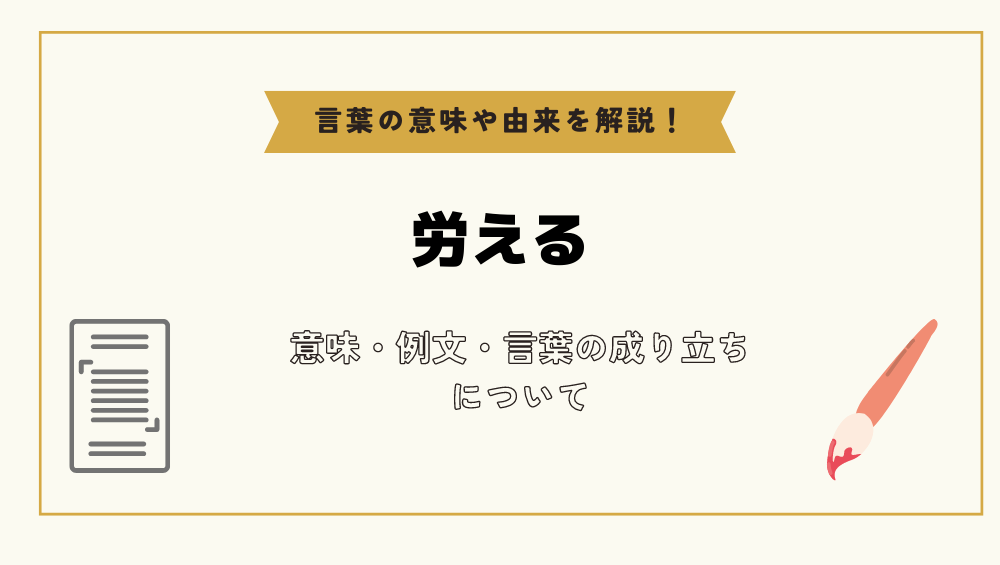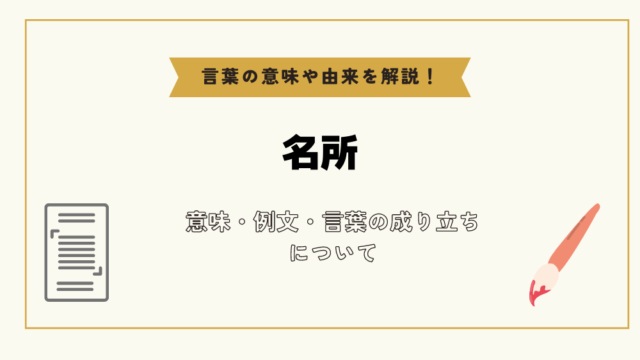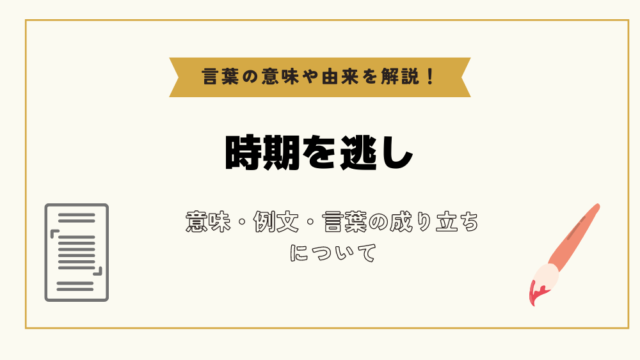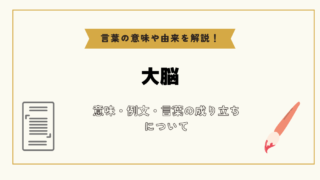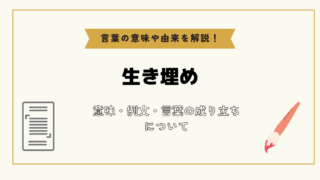Contents
「労える」という言葉の意味を解説!
労えるという言葉は、日本語の動詞「労う(いたわる)」を連用形にしたものです。
労うとは、相手の苦労や辛さを理解し、思いやりをもって支えることを意味します。
この言葉には、「気遣いする」といった意味も含まれており、相手をねぎらったり、心配をかけないように配慮することも労えると言えます。
労えるは一般的には「いたくえる」と読まれますが、方言や地域によっては「いたわえる」とも読まれることもあります。
「労える」という言葉の使い方や例文を解説!
「労える」という言葉は、人間関係や仕事上の場面でよく使われます。
例えば、友人が試験に失敗した時には、「頑張ったでしょう、労えるよ」と労うことができます。
また、仕事で忙しい上司にとって、部下が成果を上げた時には、「お疲れさま、労える」とねぎらう言葉としても使用されます。
使い方は自由であり、相手の状況や関係性に応じて使い分けることができます。
思いやりの気持ちを表す言葉として、「労える」は幅広く使われています。
「労える」という言葉の成り立ちや由来について解説
「労える」という言葉は、「労う」という動詞の連用形に助動詞「得る(える)」を組み合わせた形です。
労うとは、相手に対して思いやりを持って接する行為を指し、その行為が成果や効果をもたらすことを示しています。
この「労える」という形は、相手の労力や苦労に対して感謝や支援の気持ちを込めた言葉として広まりました。
「労える」という言葉の歴史
「労える」という言葉は、古くから日本語に存在している言葉です。
その由来は古い言葉に遡ることはできませんが、日本人の思いやりの心を表す言葉として重要な位置を持っています。
人々がお互いを支え合い、励ますことが大切であるという考え方が根付いているため、この言葉は広く使われてきました。
時代とともに「労える」という言葉も変化し、使われ方やニュアンスも変わってきましたが、相手を思いやる心を大切にする価値は変わることなく受け継がれています。
「労える」という言葉についてまとめ
「労える」という言葉は、相手の苦労や辛さを理解し、思いやりをもって支えることを表す日本語の動詞です。
使い方や読み方は地域や状況によって異なる場合もありますが、相手の労力や苦労に感謝や支援の気持ちを込める言葉として重要な役割を果たしています。
「労える」という言葉は、日本人の思いやりの心を象徴し、相手をねぎらう言葉として広く使われています。
人々が助け合い、励まし合うことの大切さを伝える言葉であり、日本語の豊かな表現の一つと言えます。