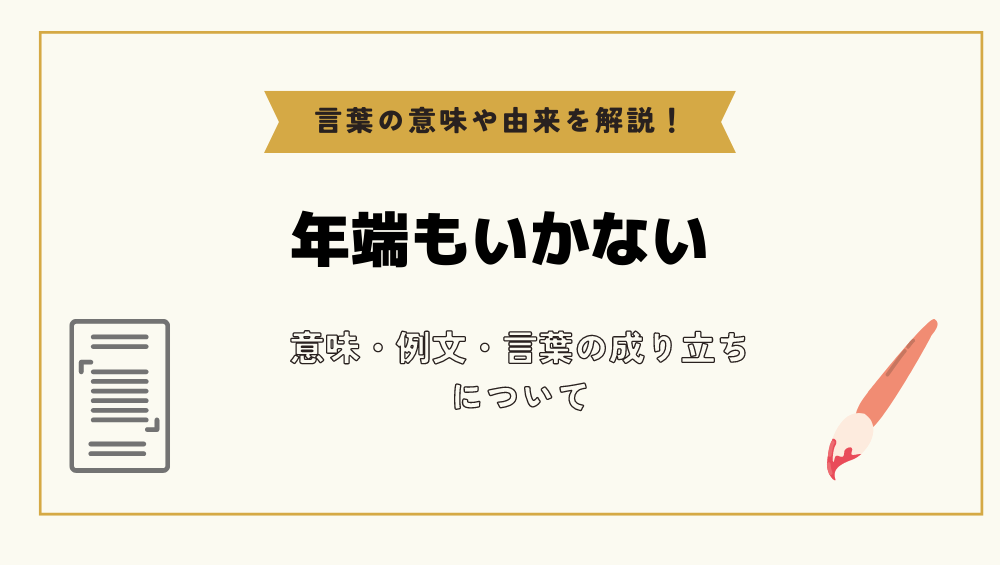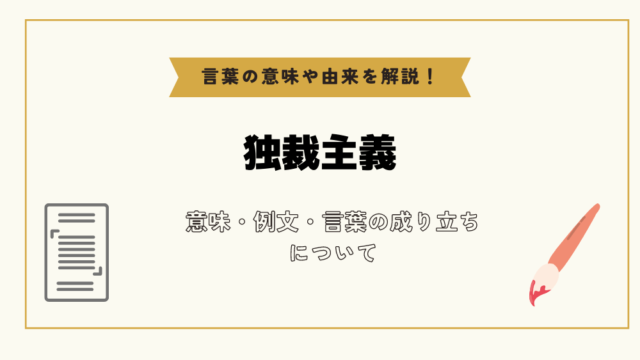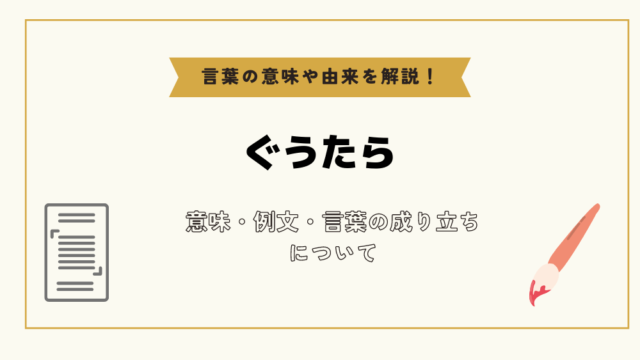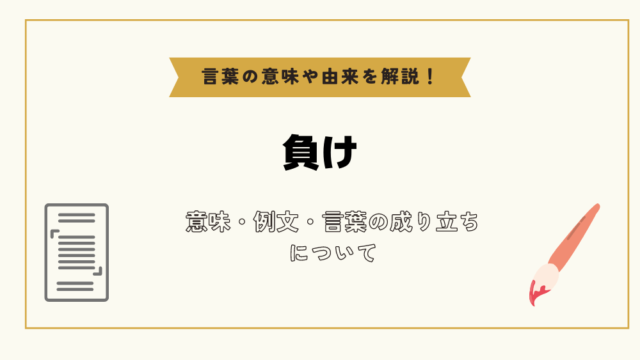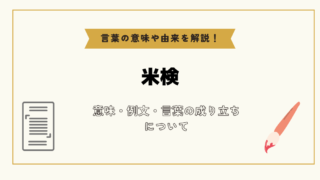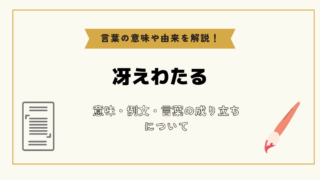Contents
「年端もいかない」という言葉の意味を解説!
「年端もいかない」という言葉は、子供や若者に対して用いられる表現であり、その意味は「まだ年齢が若くて未熟な」ということを指します。
年齢がまだ幼いために、経験や知識が不足している状態を表現する言葉として使われます。
この言葉は、年齢に関係なく未熟な人や行動にも使用することがあります。
「年端もいかない」の読み方はなんと読む?
「年端もいかない」の読み方は、「としはたもいかない」となります。
この言葉は、日本語の標準的な読み方である「訓読み」になります。
他には「ねんはたもいかない」「としはやもいかない」なども使われることがありますが、一般的には「としはたもいかない」と読むことが多いです。
「年端もいかない」という言葉の使い方や例文を解説!
「年端もいかない」という言葉は、未熟な様子や経験不足を表現するために使われます。
例えば、友達がまだ高校生であるため、まだまだ世間知らずで未熟な行動をする場合には「彼は年端もいかないから、そんなことをするのかもしれないね」と言うことができます。
また、自分自身がまだ経験不足であることを自己紹介する際にも「私はまだ年端もいかないですが、頑張ります」と言うことができます。
「年端もいかない」という言葉の成り立ちや由来について解説
「年端もいかない」という言葉の成り立ちは、年齢が幼いことを表現する際に使われるようになりました。
元々は「年端(とう)」という言葉は、日本古来の言葉で「年齢の幅」「年の数」といった意味を持ちます。
そして、「いかない」は「越えない」という意味です。
そのため、「年端もいかない」という表現は、まだ経験や知識が未熟な若い人や行動を表現するのに適した表現となったのです。
「年端もいかない」という言葉の歴史
「年端もいかない」という言葉の歴史は古く、日本の文献にも見受けられます。
江戸時代の文献や歌謡曲にも登場することがあり、古くから使われている言葉です。
ただし、使われる場面や意味合いは年代や時代によって異なることがあります。
時代の変化とともに、言葉の使い方や意味も変化してきたと言えるでしょう。
「年端もいかない」という言葉についてまとめ
「年端もいかない」という言葉は、若さや未熟さを表現するために使われる表現です。
年齢が幼いために経験や知識が不足している状態を指し、子供や若者に対して用いられることが多いです。
この言葉は古くから使われており、日本の文化や言葉に根付いている表現と言えます。
未熟さや成長の過程を含んだ言葉であるため、親しみやすく人間味のある表現として広く使われています。