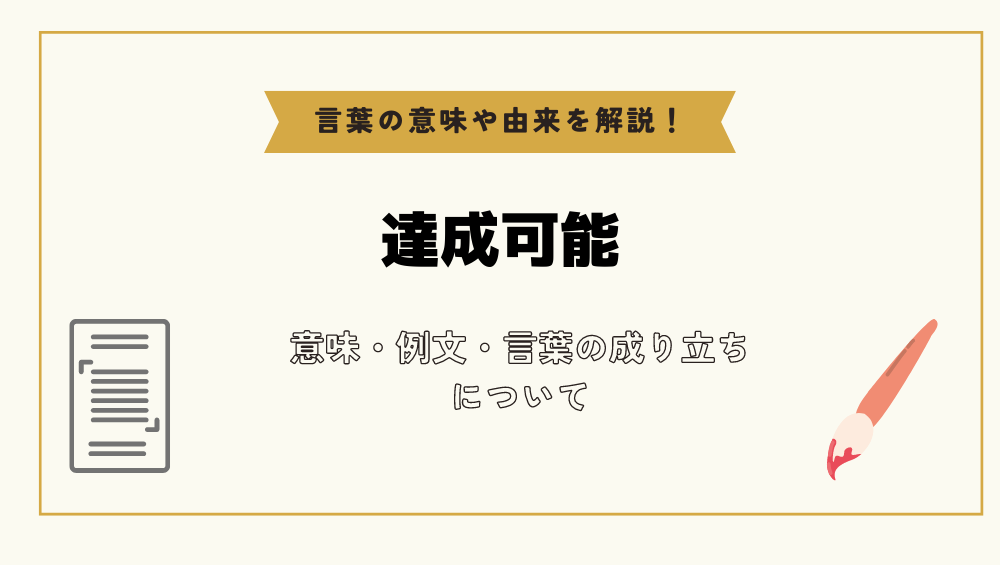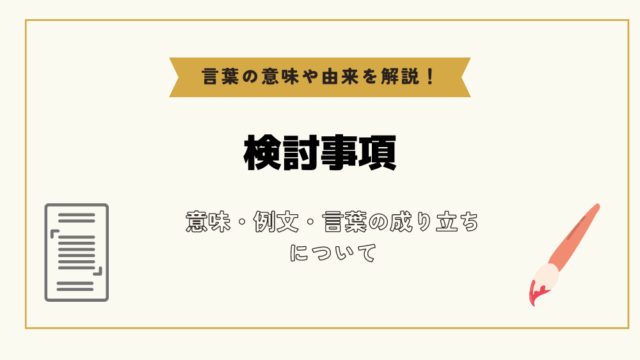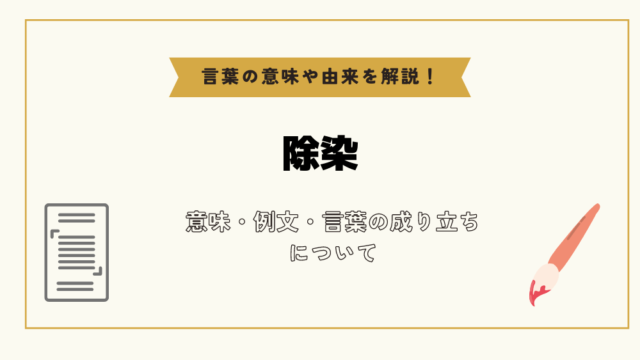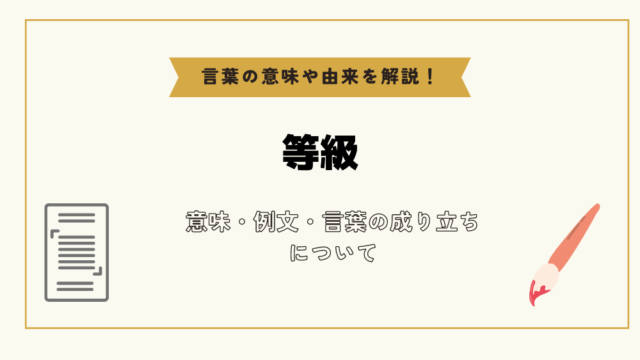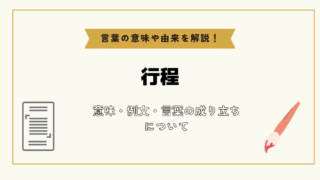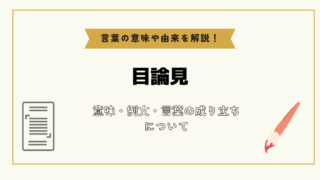「達成可能」という言葉の意味を解説!
「達成可能」とは、努力や計画次第で実際に成し遂げられる見込みがある状態を示す言葉です。ビジネス文書や学術論文、日常会話にいたるまで幅広い場面で登場し、「無理ではなく、現実的に手が届く」というニュアンスを含みます。英語の feasible や achievable に相当し、単なる願望ではなく実現性を重視する点が大きな特徴です。
目標設定理論で知られる「SMART」の“R”は Realistic(現実的)と訳されることがありますが、日本語環境では「達成可能性」という言葉が頻繁に用いられます。この背景には、具体的な達成可能ラインを示すことで、行動計画の策定やモチベーション維持が容易になるというメリットがあります。
【例文1】このプロジェクトは半年以内に完了するのが達成可能です。
【例文2】あなたの語学レベルなら、日常会話の習得は十分に達成可能です。
一方で、あまりに低いハードルを「達成可能」と呼ぶと成長の機会を逃しかねません。適切な難易度と達成可能性のバランスを取ることが、長期的な成功に直結します。
「達成可能」の読み方はなんと読む?
「達成可能」は「たっせいかのう」と読みます。音読みと訓読みが混在しており、「達成(たっせい)」は音読み、「可能(かのう)」も音読みです。どちらも漢語由来のため、発音リズムは比較的フラットで聞き取りやすいでしょう。
誤読として「たっせいこうのう」「たっせいかなう」などがありますが、標準的な辞書や公的資料では「たっせいかのう」が正式です。文章校正や音声読み上げソフトを利用する際に変換ミスが起こりやすいため、注意して入力・確認する習慣があると安心です。
音声コミュニケーションの現場では、早口になると「達成」の末尾と「可能」の頭が連結して「せいかのう」と聞こえる場合があります。プレゼンや研修で用いる際は一拍置いて「たっせい|かのう」と区切ると、聴衆が理解しやすくなります。
「達成可能」という言葉の使い方や例文を解説!
ビジネスシーンではプロジェクト計画書や提案書に「達成可能な目標」「達成可能なスケジュール」という形で多用されます。このときの「達成可能」は、リスク評価やリソース配分を踏まえたうえで実現性が高いことを示す客観的指標として働きます。
日常生活では「達成可能」を用いることで、相手に対して現実味を帯びた励ましやアドバイスを届けられるメリットがあります。たとえばダイエットや資格取得といった長期目標を共有する場面で、「達成可能な範囲から始めよう」と伝えると、相手の心理的負担を軽減できます。
【例文1】目標を細分化すれば、一日に30分の学習でも合格は達成可能です。
【例文2】予算を増額すれば、三か月以内の完成は十分達成可能となります。
公的文書では「実現可能」という表現も併記し、法的・技術的要件を満たすかどうかを厳密に評価します。作文やレポートでは、単に「できる」と書くよりも「達成可能」と書くことで、論理性と具体性を補強できる点が評価されやすいです。
「達成可能」という言葉の成り立ちや由来について解説
「達成」は中国古典に由来し、「目的に到達して成就する」という意味を持ちます。「可能」は明治期以降、西洋の“possible”の訳語として広まりました。二語を連結させた「達成可能」は、大正から昭和初期の技術翻訳書で確認できます。
産業革命以降の日本では、計画・統制・評価をセットで考えるマネジメント思想が輸入されたため、「達成可能」は管理用語として定着しました。特に戦後の経営学や教育工学の分野で頻出し、目標管理(MBO)やカリキュラム設計の必須ワードとなっています。
語源的に見ると、「達」は「たち(通す)」「とおる」を示し、「成」は「完成」「成功」を示します。「可能」は「可(よい)」「能(できる)」を意味し、ポジティブな語感が強調されます。したがって「達成可能」は、「到達でき、成し遂げることができる」という重ね表現であり、実現性を二重に保証する構造が特徴です。
「達成可能」という言葉の歴史
江戸末期までの日本語には「達成可能」という熟語は存在しませんでした。明治維新後、西欧の計画学や統計学を翻訳する過程で「可能性」「実現可能性」という言葉が生まれ、それに「達成」を組み合わせた形が徐々に使われ始めます。
1920年代の工業管理書『能率研究』に「作業標準は達成可能たるべし」との記述が確認され、これが現存する最古級の用例とされています(国立国会図書館デジタルコレクション調査による)。
高度経済成長期の1960年代には、目標管理制度(MBO)の普及とともに「達成可能目標」という表現がビジネス界で一般化しました。1980年代からは教育分野でも「達成可能な到達目標」という語が教員養成課程で定式化されます。
近年では政府の政策評価法やSDGs関連文書で「達成可能」が頻繁に登場し、持続的で実現性の高い目標設定の要として定着しました。
「達成可能」の類語・同義語・言い換え表現
「達成可能」と近い意味を持つ語には「実現可能」「可能」「できる」「成就し得る」「見込みがある」などがあります。それぞれニュアンスが微妙に異なるため、文脈に応じた使い分けが重要です。
ビジネス文書では「実現可能性が高い」「現実的に可能」といった形で、数値データや調査結果とセットで使用すると説得力が増します。逆に、日常会話やブログ記事など柔らかい場面では「やればできる」「手が届く」といった表現が親しみやすく感じられるでしょう。
専門用語としてはプロジェクト管理の「Feasibility(実現可能性)」「Viability(事業成立性)」が重要です。翻訳時には「達成可能性」と「実行可能性」が混同されることがあるため、可否判断の基準や目的を明確にする必要があります。
【例文1】この提案は初期投資が少なく、実現可能性が高い。
【例文2】手順を簡素化すれば、成就し得る目標へと変わります。
「達成可能」の対義語・反対語
「達成可能」の対義語として最も一般的なのは「達成不可能」です。さらにニュアンスを分けるなら「実現困難」「不可能」「非現実的」「到達し得ない」が挙げられます。
これらの語は計画立案時にリスクを示す赤信号として機能し、目標の修正や代替案の検討を促す役割を果たします。ビジネスレポートでは「現状のリソースでは達成不可能」と記述することで、追加予算や人員配置の必要性を示唆できます。
対義語を用いる際はネガティブな印象を緩和するために、「現時点では」「条件を満たさなければ」などのクッション言葉を添えると建設的な議論につながります。
【例文1】期日内の全工程の完了は現状では達成不可能です。
【例文2】この売上目標は市場規模から見て非現実的です。
「達成可能」を日常生活で活用する方法
目標設定のコツは「一歩先の自分が頑張れば届くレベル」を設定することです。これに「達成可能」というフィルターを通すと、無理な計画を避けつつモチベーションを保てます。たとえば筋トレなら「一週間に腕立て20回増やす」など、具体的かつ計測可能な指標を付けましょう。
習慣化の専門家によると、達成可能な目標を設定すると成功体験を小刻みに得られ、ドーパミン分泌が促進されて継続率が高まるとされています。この科学的根拠は、家庭学習や禁煙プログラムでも応用されています。
【例文1】毎日5分の英単語暗記なら達成可能だから、まずは続けてみよう。
【例文2】月に1冊の読書から始めれば、年間12冊は達成可能だ。
目標の棚卸しを毎週行い、達成可能性が低くなったら早めに修正することも重要です。これにより、挫折感を最小化しながら長期的な成長曲線を描けます。
「達成可能」に関する豆知識・トリビア
「達成可能率」を計算する統計的手法として、PERT(Program Evaluation and Review Technique)のβ分布モデルが用いられます。三点見積り(楽観・悲観・最頻値)から導かれる標準偏差で95%信頼区間を算出し、その範囲に収まるかどうかで達成可能性を判断します。
日本の気象庁でも、長期予報の説明資料に「達成可能範囲」という表現を用いて確度を示しています。これは一般的な予測モデルがもつ誤差幅を、理解しやすい形で国民に提示する狙いがあります。
ほかにも、スポーツ心理学では目標の達成可能性を視覚化する「ゴールマッピング」という技法が支持されています。紙面に達成した姿を描くことで脳が疑似体験し、パフォーマンス向上につながると報告されています。
「達成可能」という言葉についてまとめ
- 「達成可能」は努力と計画次第で実際に成し遂げられる見込みがある状態を示す言葉。
- 読み方は「たっせいかのう」で、音読みが連続する発音が標準。
- 明治以降の翻訳語を基盤に、大正期の技術書で定着した歴史がある。
- 現代では目標管理や自己啓発で広く使われ、適切な難易度設定が重要とされる。
「達成可能」という言葉は、単にポジティブな励ましではなく、実現性を見極める冷静な視点を提供してくれます。読み方や歴史的背景を理解することで、ビジネス・教育・日常生活のあらゆる場面で説得力を高められます。
また、対義語や類語と比較してニュアンスを掴むと、文章表現の幅が広がります。目標を掲げる際には「達成可能かどうか」を常に問い直し、現実的な行動計画へ落とし込むことが成功への近道です。