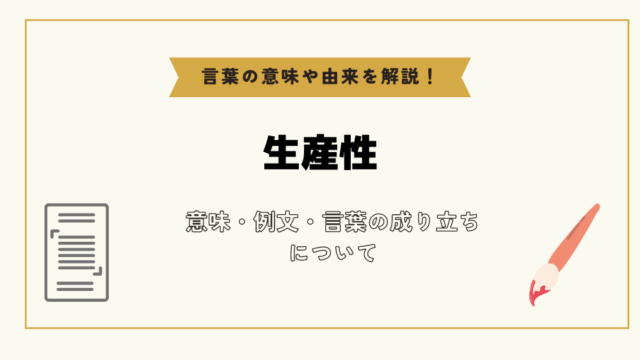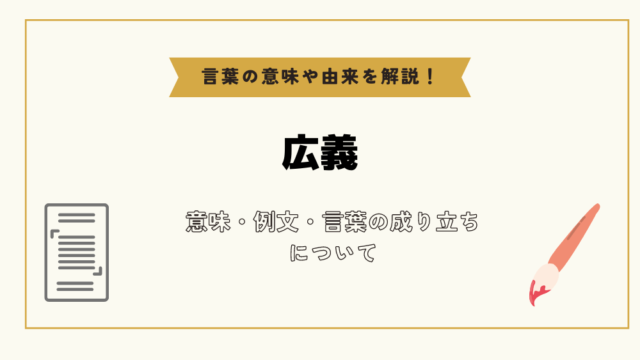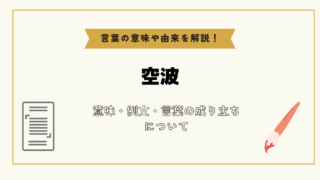Contents
「空署」という言葉の意味を解説!
。
「空署」という言葉は、警察署や駐在所に配属された警察官のうち、実際に現場に出勤せず、事務作業や研修などを担当する者を指します。
つまり、現場勤務ではなく、空いている場所(空室)での業務を行う職員のことを指します。
「空署」という言葉の読み方はなんと読む?
。
「空署」という言葉は「くうしょ」と読みます。
「空署」という言葉の使い方や例文を解説!
。
「空署」は、警察組織内での職制の一つです。
例えば、警察署内には、総務課や交通課、生活安全部などの各課がありますが、その中でも現場での活動を行わない、主に事務業務や研修に従事する職員が「空署」として配属されます。
例文としては、「彼は空署で働いているため、現場での事件対応はありませんが、日々警察官の研修や人事関連の業務を担当しています」といった使い方があります。
「空署」という言葉の成り立ちや由来について解説
。
「空署」という言葉は、「空」と「署」を合わせた言葉です。
もともと「空」という言葉は「何もない、中身のない」という意味で使われ、それに「署」という単語がついて、配属された職員が現場での実務業務を行わないことを示すようになりました。
具体的な由来については明確な情報はありませんが、警察組織の効率化や専門性の向上のため、現場とは別の業務を担当する職員が設けられたのが由来と言われています。
「空署」という言葉の歴史
。
「空署」という言葉自体の具体的な歴史は分かりませんが、警察組織の発展に伴い、管理職、専門職などが必要とされるようになり、これまで現場での業務を行っていた警察官とは異なる業務を担当する職員が必要になってきました。
そうした背景から、現場での実務に従事しない職員が「空署」という名称で呼ばれるようになったと考えられます。
「空署」という言葉についてまとめ
。
「空署」という言葉は警察組織内の専門職として存在し、現場での業務ではなく、事務や研修を担当する職員を指します。
その由来は、「空」という言葉の意味と「署」という単語が組み合わさったもので、警察組織の効率化や専門性の向上を目的として設けられました。
現場での実務に従事しない職員が必要になった結果、今日のような「空署」という概念が使われるようになりました。