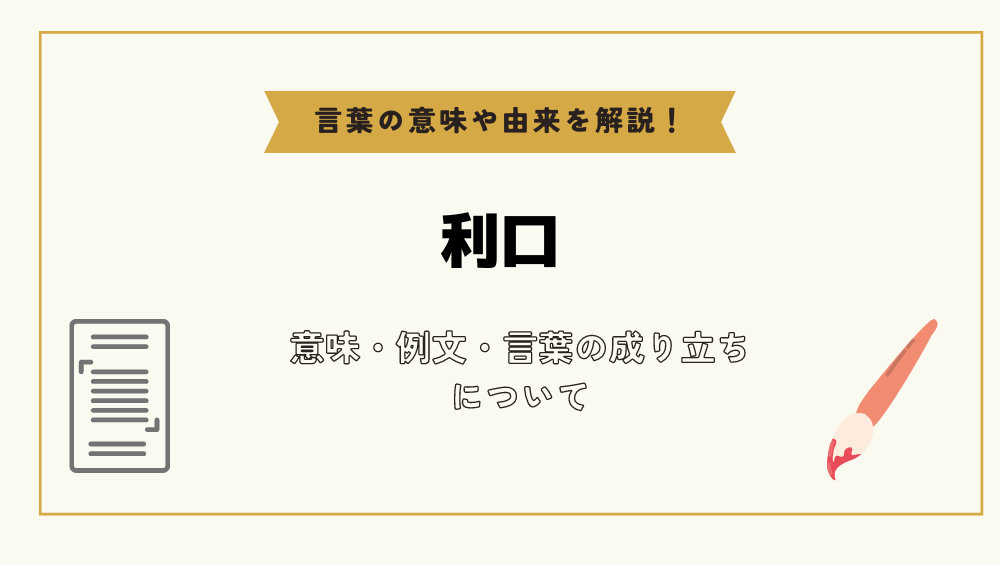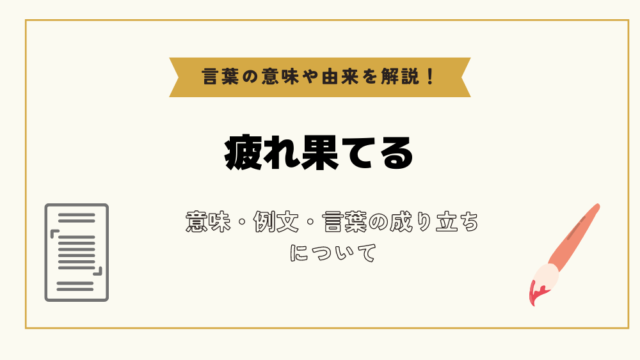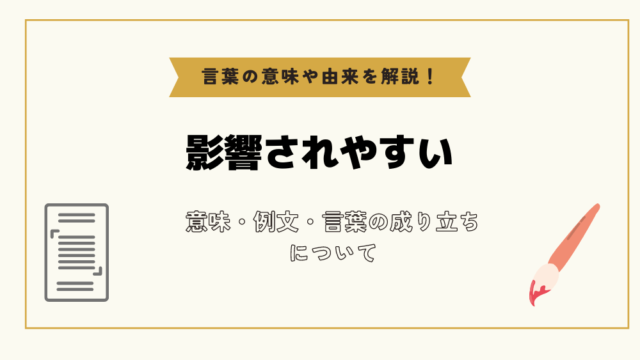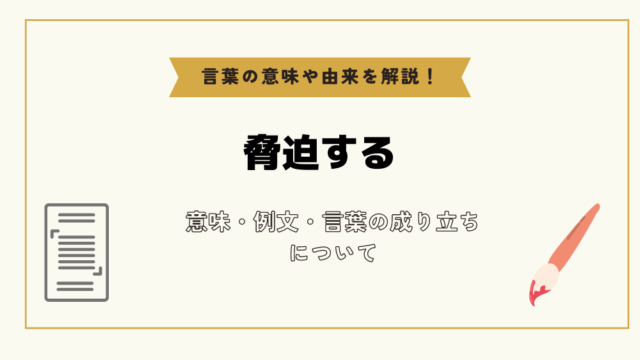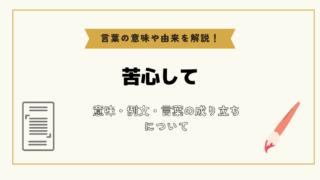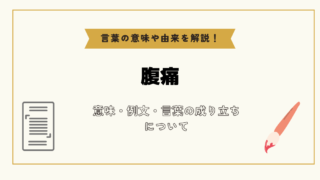Contents
「利口」という言葉の意味を解説!
利口という言葉は、賢明で知恵のある人を指す言葉です。
物事を的確に判断し、良い結果をもたらす能力を持っていることを表現します。
「利口な策を立てる」「利口に行動する」といったように、頭の良さや判断力によって望ましい結果を得ることができるという意味合いがあります。
利口な人は、知識や経験に基づいた冷静な判断ができるだけでなく、物事を論理的に考える能力も高いです。
そのため、問題解決や意思決定において重要な存在となります。
「利口」の読み方はなんと読む?
「利口」は、読み方は「りこう」となります。
日本語の発音の特徴から、最後の「ち」は「つ」に変わる場合があります。
「利口」の読み方は古くから定着しており、一般的に認知されています。
親しみやすい言葉であるため、日常会話や文章でもよく使われます。
「利口」という言葉の使い方や例文を解説!
「利口」は、主に人や動物の賢さを表現する際に使われます。
特に頭の良さや知恵のある行動に対して用いられることが多いです。
例えば、「彼は利口な手段で問題を解決した」と言うと、彼が知恵を使って問題を解決したことを意味します。
また、「利口な犬」と言うと、犬がしつけが良く、賢い様子を表現しています。
「利口」という言葉の成り立ちや由来について解説
「利口」の成り立ちは、古代中国に由来します。
当初は「利が口(こう)で出る」という意味で、知恵や判断力によって利益を得ることを表現していました。
日本に伝わった後は、「利が口」の部分が変化して「利口」となりました。
古代中国の思想や文化が日本にも影響を与えた結果、現代の意味や読み方にまで変化したのです。
「利口」という言葉の歴史
「利口」という言葉は、平安時代から存在していたことが文献によって確認されています。
古くから「利が口」の形で使われており、知恵や賢さを表現する言葉として広まりました。
江戸時代に入ると、知識や教養の重要性が高まり、「利口」という言葉も一般的に使われるようになりました。
現代においても、頭の良さや判断力を指し示すために広く用いられています。
「利口」という言葉についてまとめ
「利口」という言葉は、賢明で知恵のある人を表現するために使われる言葉です。
物事を的確に判断し、良い結果をもたらす能力を持っていることを意味します。
読み方は「りこう」となります。
日本語の発音の特徴から、最後の「ち」は「つ」に変わる場合があります。
頭の良さや知恵のある行動に対して用いられ、主に人や動物の賢さを表現する際に使われます。
古代中国に由来し、日本に伝わった後に現代の意味や読み方に変化しました。
平安時代から存在していた「利口」は、江戸時代以降ますます一般的となり、現代においても広く使われています。