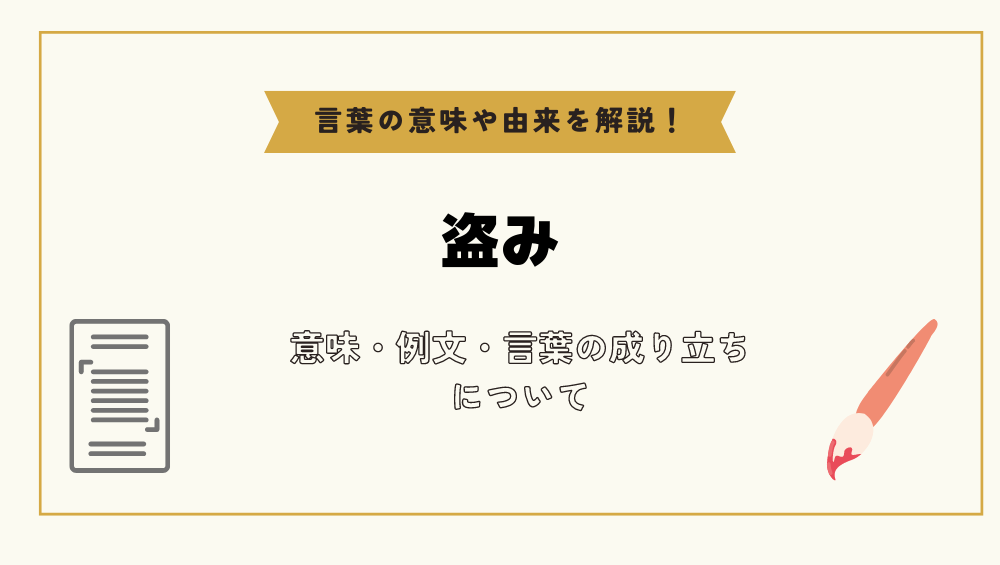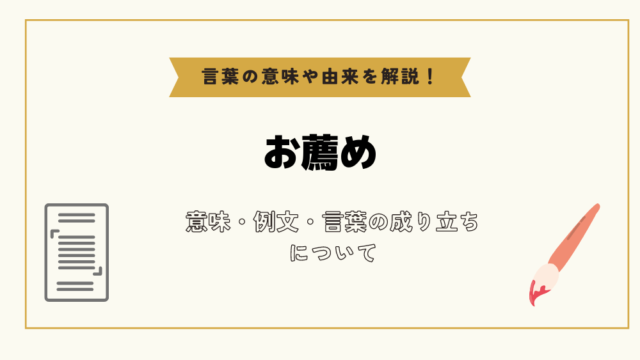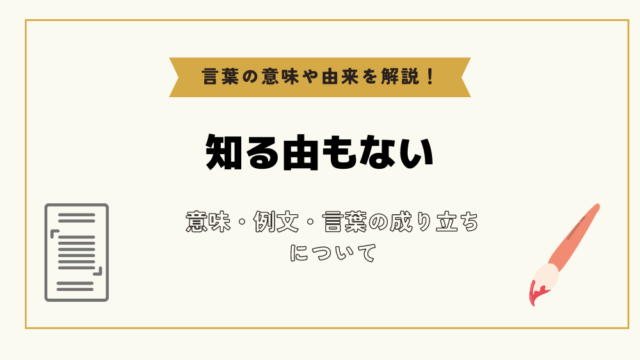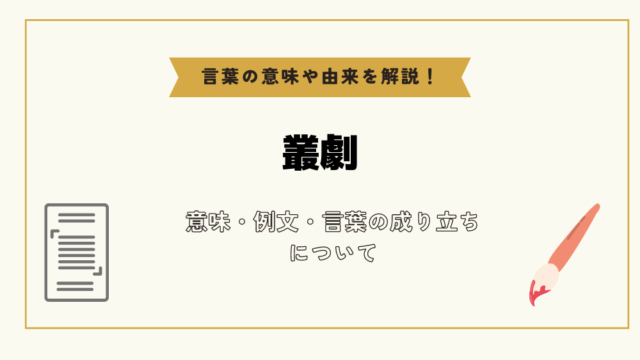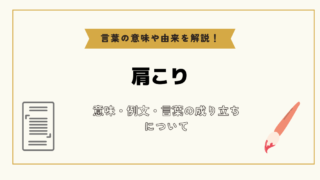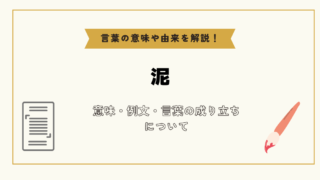Contents
「盗み」という言葉の意味を解説!
「盗み」という言葉は、他人のものをこっそりと持ち去ることを意味します。
一般的には不正な手段で他人の財産を奪うことを指しますが、場合によっては軽い冗談や遊び心を含んだ意味合いでも使われることがあります。
原義としては、他人の所有物をこっそりと奪うことを指していましたが、現代では他のものや考え方からアイデアや知識を盗み出すことも「盗み」と表現されることがあります。
「盗み」の読み方はなんと読む?
「盗み」は、「ぬすみ」と読みます。
日本語では「欺く」「奪う」という意味合いがあるため、読み方もそれに対応しています。
「盗み」という言葉の使い方や例文を解説!
「盗み」は、盗む行為や盗まれる被害を表現するために使われます。
具体的な使い方としては、「お金を盗む」「アイデアを盗む」「時間を盗む」といった表現があります。
例えば、「彼は他のチームの戦術を盗んで優勝した」というように使われることもあります。
また、「茶碗を盗む」という表現は、お茶碗を洗わずにこっそり持ち去ることを指すこともありますが、昔話や子供の遊びの一環として使われることもあります。
「盗み」という言葉の成り立ちや由来について解説
「盗み」という言葉の成り立ちや由来は、古代日本の言葉「脱」「奪ふ」と関連があります。
これらの言葉は、「他人から取り上げる」といった意味合いを持っていました。
時代の経過とともに、「脱」という言葉が「ぬすむ」に、また「奪う」が「とる」となっていき、現代の「盗み」という言葉に繋がったと言われています。
「盗み」という言葉の歴史
「盗み」という言葉は、日本の歴史とともに存在してきました。
古代には盗みや強盗が発生し、それを取り締まる法律も整備されていました。
中世に入ると、戦乱や貧困の時代として一般的に盗みが多発し、法律の範疇を超えてしまうこともありました。
近代に入ると、社会の発展や福祉の向上により盗みの発生件数は減少しましたが、未だに社会問題として存在しています。
また、現代のデジタル社会においては、インターネット上での盗みや詐欺行為も増えてきています。
「盗み」という言葉についてまとめ
「盗み」という言葉は、他人のものをこっそりと持ち去る行為を指します。
それは不正な手段で他人の財産を奪うこともありますが、時には冗談や遊び心を含んだ意味合いでも使われます。
日本の古代から現代まで存在し、社会問題としても認識されています。
インターネットの普及により、盗みの形態も変化していますが、私たちは法律や倫理に基づいて盗みを防ぐ努力をするべきです。