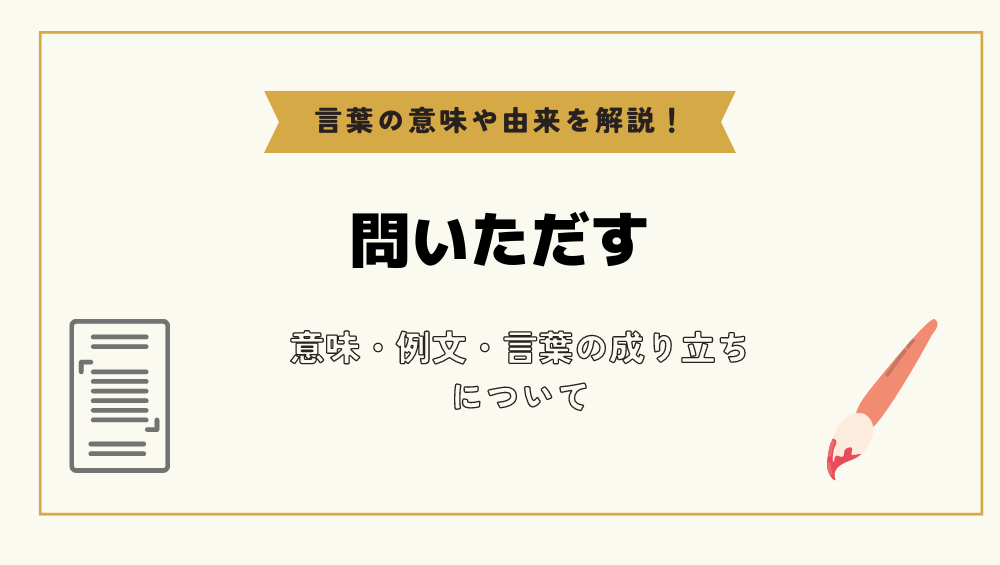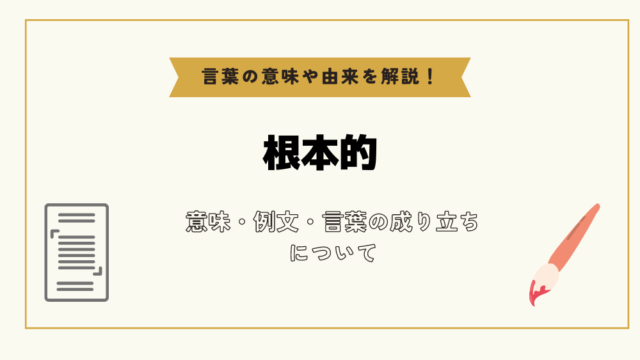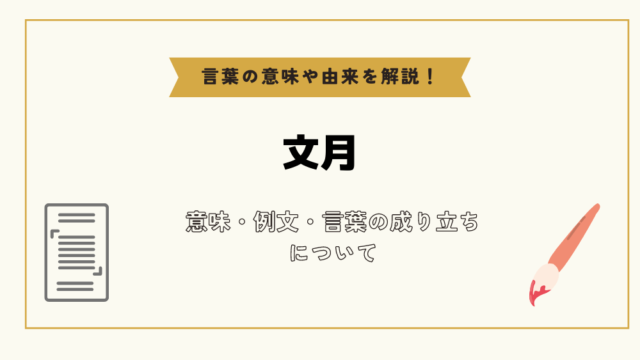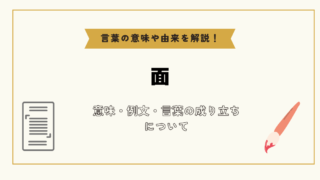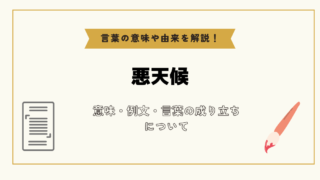Contents
「問いただす」という言葉の意味を解説!
「問いただす」という言葉は、相手に疑問や質問を直接ぶつけるという意味を持っています。
自分が何かに疑問を感じたり、理解を求めたりする際に使われる表現です。
「問い」は「質問」や「疑問」という意味を持ち、「ただす」は「立ち向かう」という意味があります。
「問いただす」という言葉の読み方はなんと読む?
「問いただす」という言葉は、「といただす」と読みます。
最後の「す」は、丁寧な言葉遣いをするための助動詞で、「対する」「向き合う」という意味も含んでいます。
ですので、「といただす」と読むことで、相手に対して真剣に向き合って質問や疑問を述べる様子が伝わります。
「問いただす」という言葉の使い方や例文を解説!
「問いただす」という言葉は、相手に対して質問や疑問を語る際に使われます。
例えば、例文をいくつか紹介します。
・「なぜそのような意見を持つのか、お答えをいただけますか?」
。
・「この問題の解決策を、皆さんと共に考えたいと思います。
ご意見をお聞かせください。
」
。
・「社内の意識改革について、上司に問いただしてみましたが、具体的な答えは得られませんでした。
」
。
このように、「問いただす」は、相手に対して自分の立場や意見を問いかける際に使う表現です。
「問いただす」という言葉の成り立ちや由来について解説
「問いただす」という言葉は、日本語の古い語彙で、主に武士や武家の間で使われていました。
日本の中世においては、君主や上位の人物に対して直接疑問や質問をぶつけることは、勇気や度胸を必要とする行為であり、その意味で武士の美徳とされました。
ですから、「問いただす」という言葉には、相手に対して自分の意見や質問を直接的にぶつけるという勇気や精神的な力強さが感じられます。
「問いただす」という言葉の歴史
「問いただす」という言葉は、古くから日本の武士や武家の間で使われてきました。
それは、上位の人物に対して直接疑問や質問をぶつける行為が勇気と度胸を必要とするものであり、武士の美徳とされていました。
しかし、時代の変遷とともに、この言葉の使用頻度は減少していきました。
現代では、一般的に使われることは少ないですが、特定の場面や形式張った表現においては、まだまだ活用されています。
「問いただす」という言葉についてまとめ
「問いただす」という言葉は、相手に対して疑問や質問を直接ぶつけるという意味を持ちます。
自分の意見や理解を求める際に使われる言葉であり、相手に真剣な取り組みを促す効果もあります。
また、この言葉には日本の武士の勇気や精神力が込められており、その歴史も長いです。