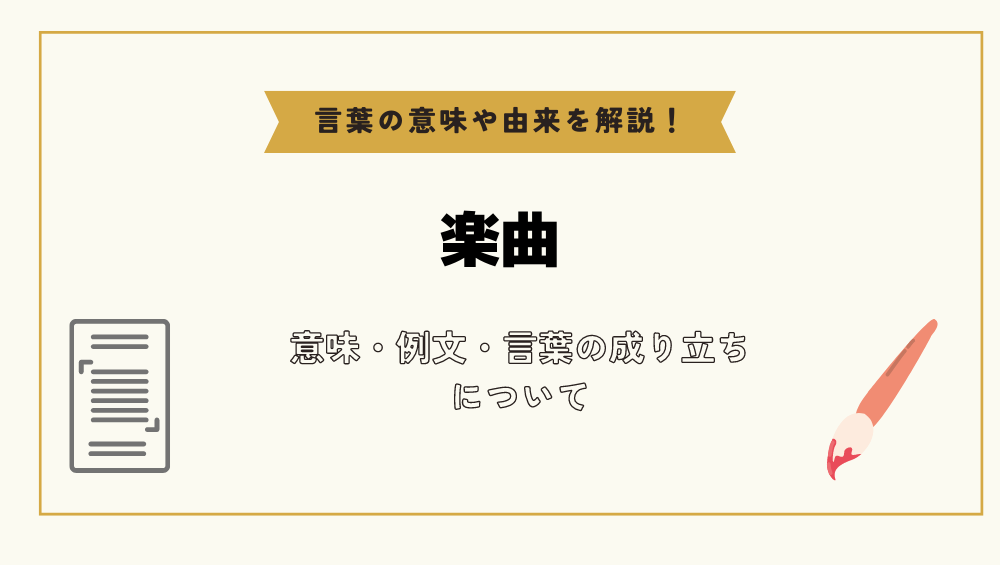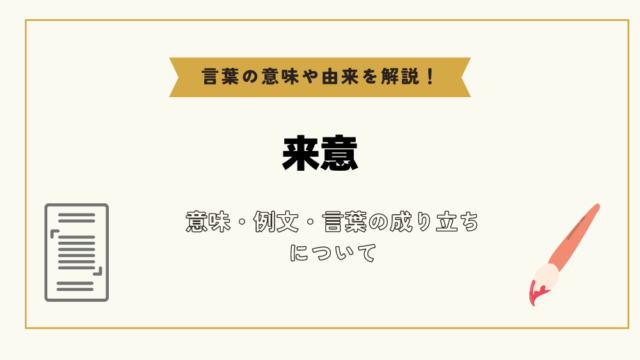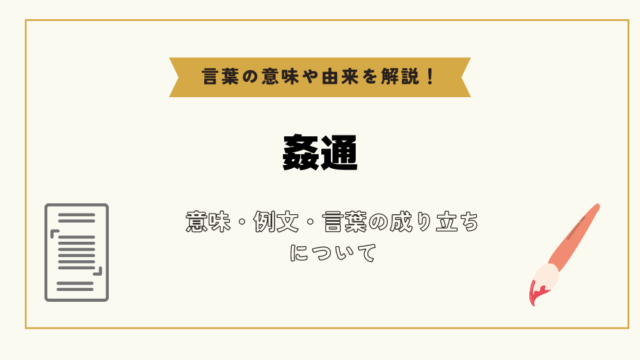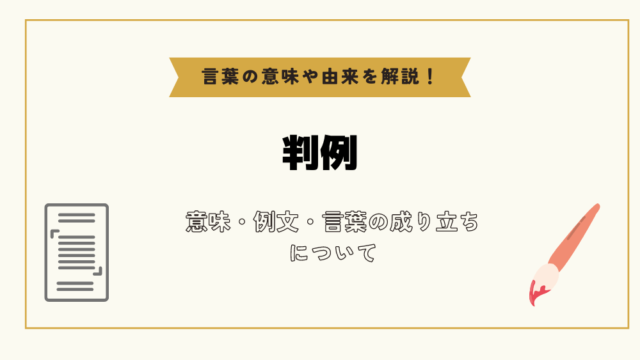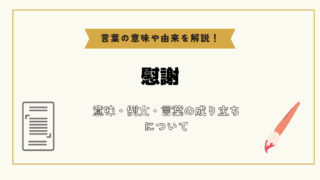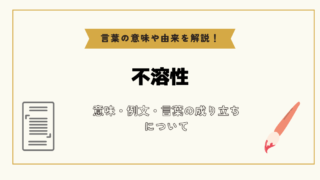Contents
「楽曲」という言葉の意味を解説!
「楽曲」という言葉は、音楽を作る際の基本的な要素のひとつです。
音楽の制作や演奏において、特定の時間の中で組み立てられたメロディーやリズム、ハーモニーなどの要素を指します。
楽曲は、その特定の時間の中で表現する目的や意図によって、さまざまなスタイルやジャンルが存在します。
クラシック音楽からポップス、ロック、ジャズ、EDMなど、様々な音楽のスタイルやジャンルに応じて、個々の楽曲が作られます。
「楽曲」という言葉の読み方はなんと読む?
「楽曲」という言葉は、「がっきょく」と読みます。
日本語の読み方においては、漢字の読み方になります。
「楽曲」という言葉の使い方や例文を解説!
「楽曲」という言葉は、音楽に関する文章や会話に頻繁に使用されます。
例えば、「彼の新しい楽曲は非常に人気があります」という風に使われます。
また、楽曲はアーティストや作曲家の創造性や表現力を示すものでもあります。
例えば、「この楽曲は彼の情熱と才能が詰まっている」というようにも使用されます。
「楽曲」という言葉の成り立ちや由来について解説
「楽曲」という言葉は、漢字の「楽」と「曲」から成り立っています。
「楽」は音楽全般を指し、「曲」は一つの旋律や調べを指します。
一つの曲がさまざまな要素を融合させて作られることから、「楽曲」という言葉が生まれたと考えられています。
「楽曲」という言葉の歴史
「楽曲」という言葉の歴史は古く、日本の伝統音楽やクラシック音楽の時代から存在しています。
古代の雅楽や能楽、そして近世の民謡や洋楽など、様々な時代や地域で楽曲が作られ、人々に愛されてきました。
現代においては、情報技術の進化により音楽の制作や配信が容易になり、さらなる多様な楽曲が生み出されるようになりました。
「楽曲」という言葉についてまとめ
「楽曲」は音楽を作る際の基本的な要素であり、特定の時間の中で組み立てられたメロディーやリズム、ハーモニーなどの要素を指します。
さまざまなスタイルやジャンルの音楽に応じて、個々の楽曲が作られることがあります。
「楽曲」という言葉は、音楽に関する文章や会話でよく使われるため、理解しておくと音楽についての表現力が広がります。
音楽の歴史や創造的な側面にも触れながら、楽曲の魅力について深く考えることができるでしょう。