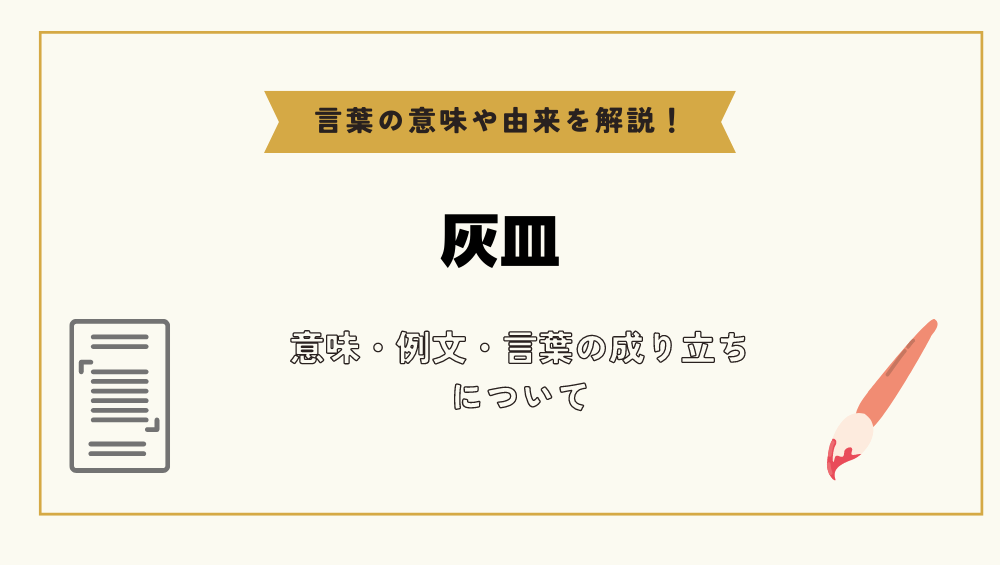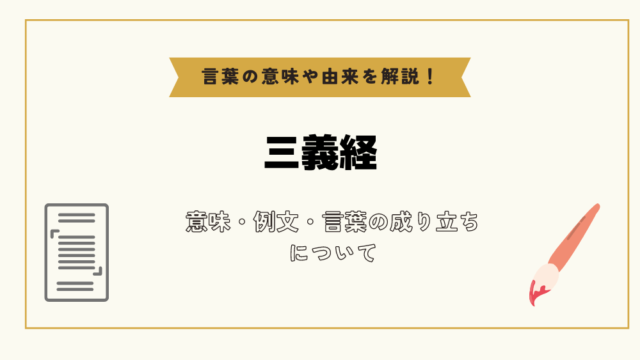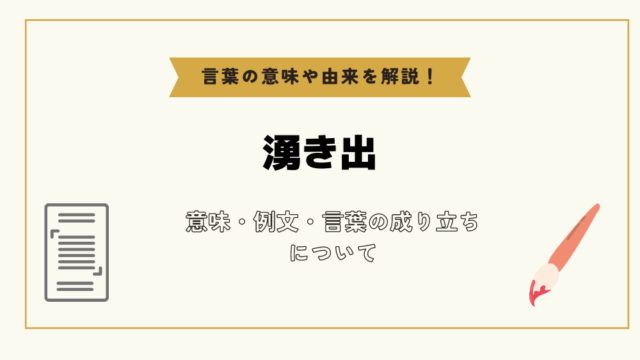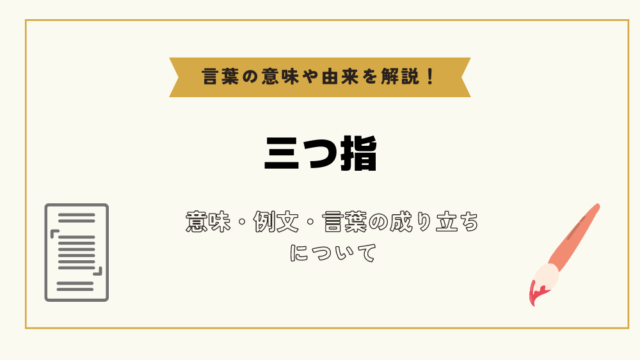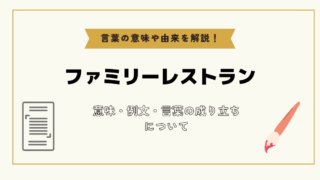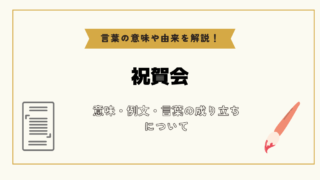Contents
「灰皿」という言葉の意味を解説!
「灰皿」とは、タバコやその他の燃える物の灰を受けるための容器です。
喫煙者がタバコの灰を捨てる場所として利用されることが多いです。
灰皿は、一般的には円盤状や浅い容器の形をしています。
底部には、灰が落ちるように穴が開いています。
また、灰を入れるためのくぼみや溝が灰皿の中に設けられており、煙草の灰を入れやすくなっています。
「灰皿」の読み方はなんと読む?
「灰皿」は、「はいざら」と読みます。
この言葉は、京都弁では「はえっさら」とも読まれることがありますが、一般的には「はいざら」という読み方が一般的です。
「灰皿」という言葉は、日本語の中に長い歴史を持つ言葉であり、多くの人が理解しています。
そのため、日常会話や文章中で使用する際には、「はいざら」と発音することが適切です。
「灰皿」という言葉の使い方や例文を解説!
「灰皿」という言葉は、喫煙者がタバコの灰を捨てるための容器を指すため、喫煙者が交流する場や喫煙所で頻繁に使用されます。
例えば、「喫茶店のテーブルには、灰皿が置かれています。
喫煙者の方は、灰皿に煙草の灰を捨ててください」というように使用することができます。
また、日本の昭和時代の映画や小説などで、喫煙者がキャラクターを演じる場面でも、「灰皿」や「灰捨て」などの言葉が頻繁に使われています。
「灰皿」という言葉の成り立ちや由来について解説
「灰皿」という言葉は、その字面からもわかるように、「灰」と「皿」の2つの言葉が組み合わさって作られています。
「灰」とは、燃えた物から残った灰のことを指し、「皿」とは、料理や食べ物を盛るために使う器具を指します。
この2つの言葉を組み合わせた「灰皿」という言葉は、一般的にはタバコの灰を受ける容器を指すようになりました。
「灰皿」という言葉の歴史
「灰皿」という言葉の起源は、おそらく明確にはわかっていませんが、それはかなり古い歴史を持っていると考えられています。
石や陶器の灰皿が紀元前の古代ギリシャやローマ時代には存在していたとされており、喫煙の習慣が広まると、それに合わせて灰皿の需要も高まっていったと考えられています。
「灰皿」という言葉についてまとめ
「灰皿」という言葉は、タバコの灰を受けるための容器を指す言葉です。
喫煙者がタバコを吸う際に灰を捨てるために使用されます。
「灰皿」は、喫煙者や喫煙所で頻繁に使用される言葉であり、日本の映画や小説でもよく登場します。
この言葉の由来や歴史ははっきりとはわかっていませんが、古代ギリシャやローマ時代には既に灰皿が存在していたと考えられています。