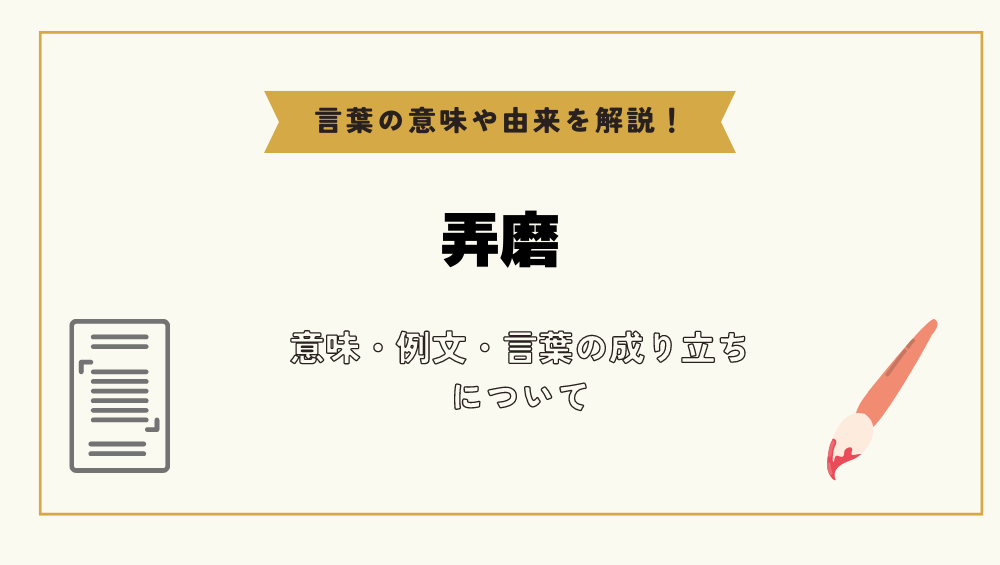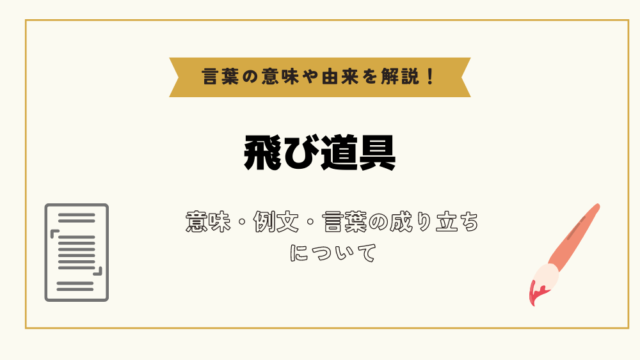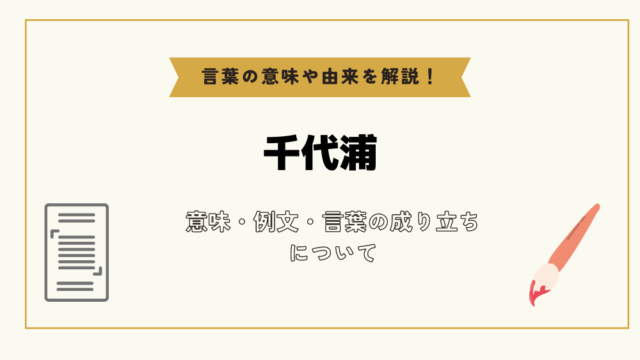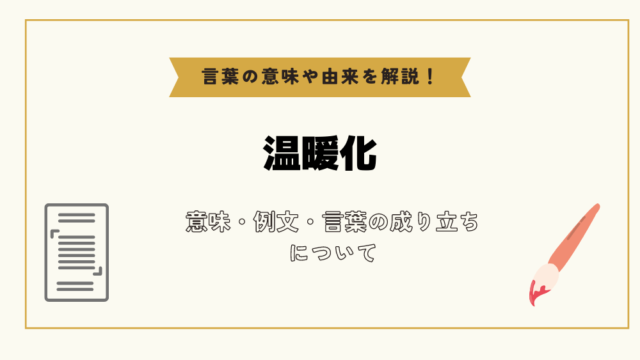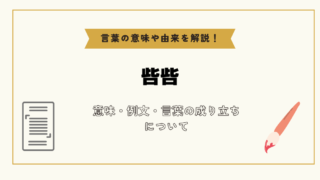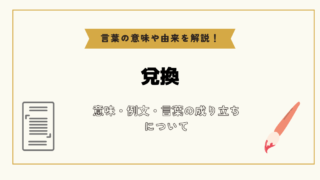Contents
「弄磨」という言葉の意味を解説!
「弄磨」とは、日本語の古語であり、その意味は「からかったりいじめたりすること」です。
この言葉は古代の文学作品や歴史書によく登場し、その時代の人々の関わり合いや心情を表しています。
弄磨は、友達同士や仲間たちの間で、軽いジョークや悪戯をしたり、からかい合ったりすることを指しています。
「弄磨」という言葉の読み方はなんと読む?
「弄磨」という言葉は、「ろうま」と読みます。
この読み方は古語として使われており、現代の日本語にはあまり使われません。
しかし、古代の文学作品や古い言葉の研究をする際には、この読み方が重要になってきます。
「弄磨」という言葉の使い方や例文を解説!
「弄磨」という言葉は、比較的古風であるため、現代の日常会話やビジネスの場で使われることはほとんどありません。
しかし、これまでの文学や歴史を学ぶことで、この言葉の使い方や例文を知ることができます。
例えば、「友人たちは花見の席で楽しく弄磨しあっていた」という文が考えられます。
「弄磨」という言葉の成り立ちや由来について解説
「弄磨」という言葉は、古代の日本語に由来します。
漢字で書くと「弄磨」と表記され、それぞれ「からかう」や「いじめる」という意味を持っています。
この言葉は、古代の人々が日常生活の中で使用していたことが分かります。
現代の日本語にはあまり使われませんが、古語の研究や文学作品の解釈においては重要な用語となっています。
「弄磨」という言葉の歴史
「弄磨」という言葉の歴史は、古代の日本までさかのぼります。
その頃の人々は、この言葉を使って友人や仲間たちとの関係やコミュニケーションを表現していました。
また、弄磨は自分が相手を思いやる気持ちを込めて行うこともありました。
その後、時代の変化とともに、この言葉は使われなくなりましたが、古代の文学や歴史書を通じてその存在が伝えられています。
「弄磨」という言葉についてまとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、「弄磨」という言葉について解説してきました。
「弄磨」とは、古代の日本語で「からかう」「いじめる」などを意味する言葉です。
また、その読み方や使い方、由来なども紹介しました。
古文の学習や文学作品の解釈においては、この言葉を理解することが重要です。
どんな時代にも友達同士の関わり合いはありましたが、その形が違っていたのですね。