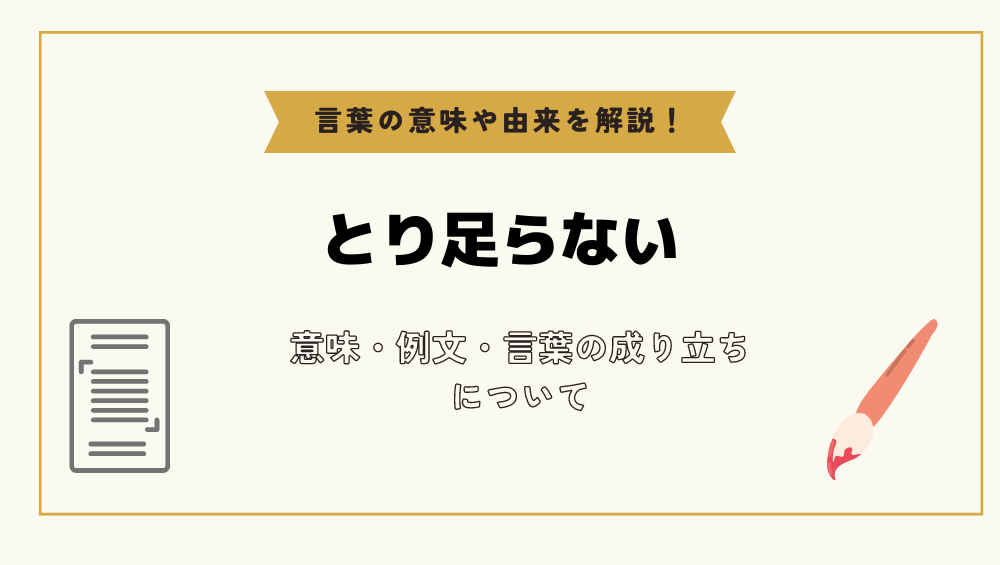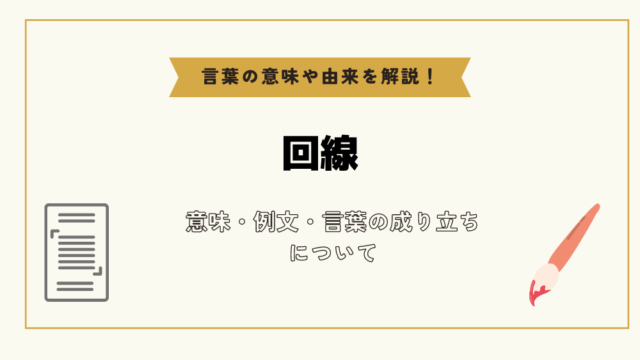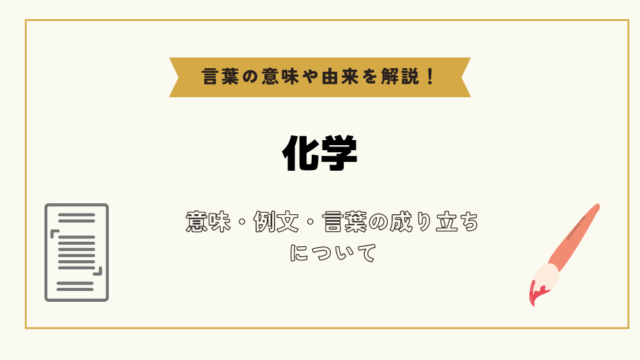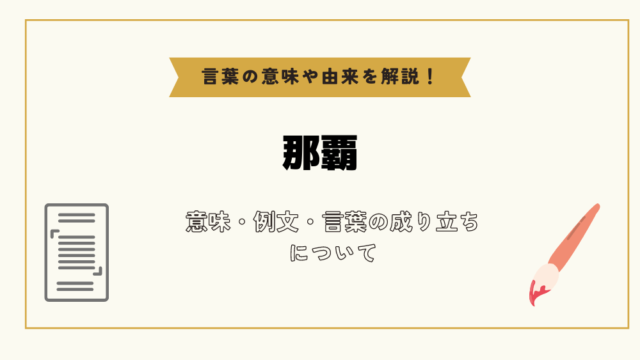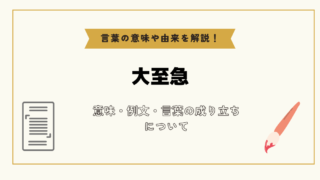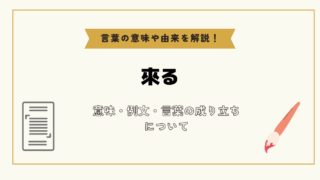Contents
「とり足らない」という言葉の意味を解説!
「とり足らない」という言葉は、物事や状況が充分でなく、十分な満足感や満足度が得られないという意味です。何かを手に入れたり、経験したりしたにもかかわらず、何かが足りないと感じることを表現する言葉として使われます。
この言葉は、人々が全体を見渡して満足感を感じることができない現代社会の状況を表しています。物質的な豊かさや成功に追い求める一方で、心の豊かさや満足感が得られない状況が増えていることを指しています。
「とり足らない」という言葉の読み方はなんと読む?
「とり足らない」という言葉は、「とりたらない」と読みます。直訳すると「取り足りない」となりますが、一般的に「とりたらない」という表現がよく使われます。
「とり足らない」という言葉の使い方や例文を解説!
「とり足らない」という言葉は、人々が物事や状況に対して充足感を得られないときに使われます。例えば、物質的な豊かさを追い求める一方で満足感が得られない場合、「お金があっても心はとり足らない」と表現することがあります。
また、仕事や勉強といった努力を重ねる中で、成果や評価が十分でないと感じる場合にも「頑張っているけど結果がとり足らない」という表現が使われます。
「とり足らない」という言葉の成り立ちや由来について解説
「とり足らない」という言葉の成り立ちや由来については明確な情報はありません。ただ、人々が満足感を感じることが難しくなっている現代社会の中で生まれた表現であると言えます。
もともとは物事や状況の不十分さや不満足感を表す言葉として使われてきましたが、近年は心の充実感を得られない社会的な問題を指し、より広い意味で用いられるようになっています。
「とり足らない」という言葉の歴史
「とり足らない」という言葉の歴史については、明確な経緯はわかりません。ただ、現代社会においては、物質的な豊かさや成功の追求により、心の満足感が得られずに人々が不満足感を抱える状況が増えてきたと言われています。
このような背景から「とり足らない」という言葉が使われるようになり、社会的な問題を表現する一つの言葉として定着しました。
「とり足らない」という言葉についてまとめ
「とり足らない」という言葉は、物事や状況が充分でなく、満足感や満足度を得られないという意味で使われます。現代社会では、物質的な豊かさに追い求める一方で、心の充実感や満足感が得られないという問題があります。
この言葉は、そのような社会的な問題を表現する一つの言葉として使われることが多くなっています。人々が物事や状況に対して充足感を得ることが難しくなっている中、心の豊かさや満足感を大切にすることが求められています。