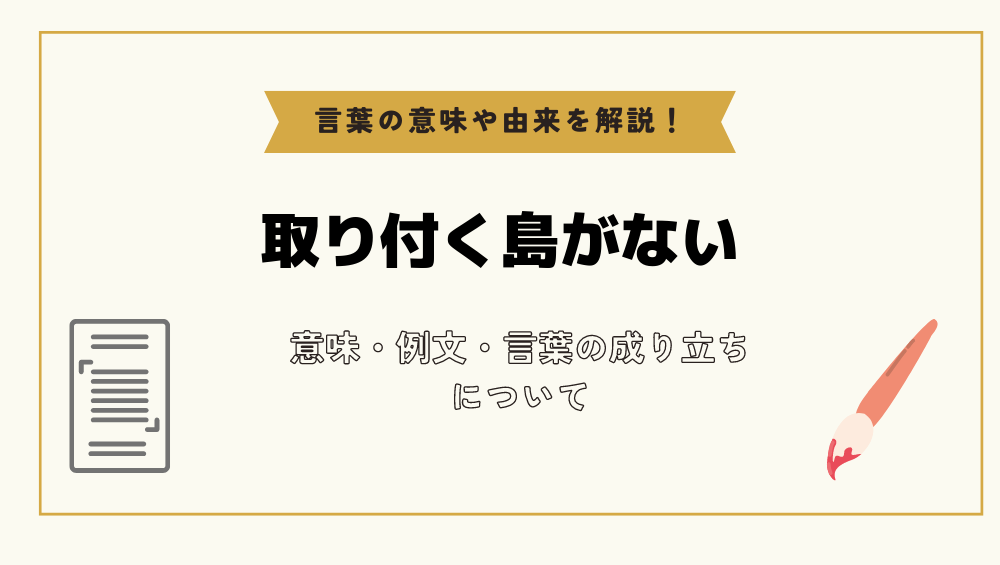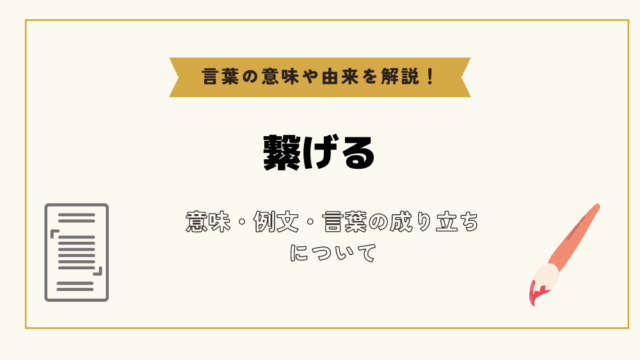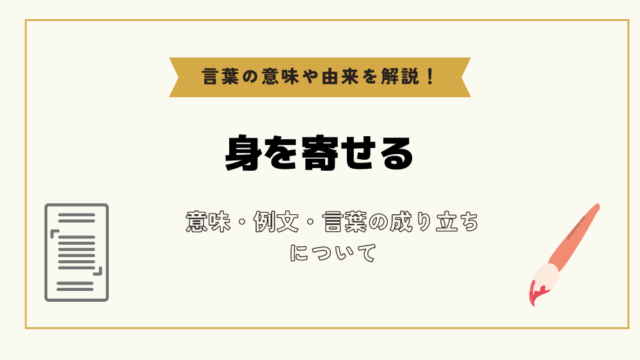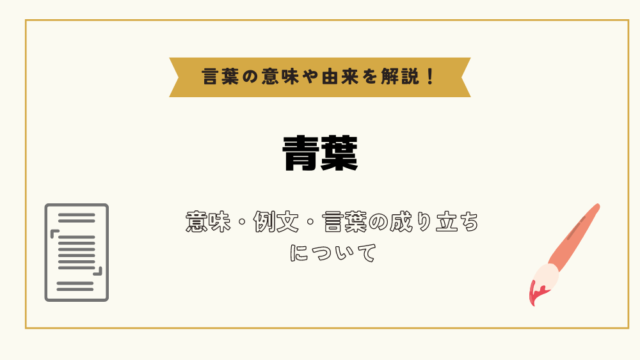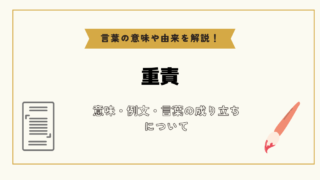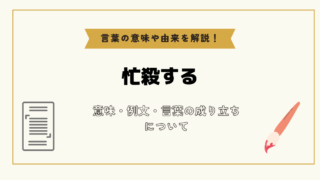Contents
「取り付く島がない」という言葉の意味を解説!
「取り付く島がない」という言葉は、何かの抵抗や傍らになるものがないという意味で使われます。
例えば、ある問題に取り組む際に、手がかりや頼りになるものがなく、進める道がほとんどない状況を指して使われることがあります。
この言葉は、困難な状況や進展の見込みがない状況を表す際にも使われます。
「取り付く島がない」の読み方はなんと読む?
「取り付く島がない」という言葉は、「とりつくしまがない」と読みます。
このような読み方をすることで、判断や意思決定の難しさや、進展の見込みがない状況を表現することができます。
「取り付く島がない」という言葉の使い方や例文を解説!
「取り付く島がない」という言葉は、さまざまな場面で使うことができます。
例えば、新しいアイデアを出そうとしても、何から手をつければいいのか分からず、取り付く島がない状態に陥ることがあります。
また、ビジネスの計画を立てる際にも、市場の需要や競合状況が不明であれば、どの方向に進むべきか判断が難しくなり、取り付く島がないと感じることがあります。
「取り付く島がない」という言葉の成り立ちや由来について解説
「取り付く島がない」という言葉は、江戸時代の語り部や講釈師の間で使われていた表現です。
当時の語り部や講釈師は、話をする際に手や周囲のものに触れることで、リズムや効果を出していました。
しかし、語り手が手元に触れるものや傍らのものがない場合、そのようなリズムや効果を出すことができず、「取り付く島がない」と感じることがあったのです。
「取り付く島がない」という言葉の歴史
「取り付く島がない」という言葉は、江戸時代から使われていた言葉です。
当時の語り部や講釈師は、口演の際に手の動きや周囲のものに触れることで、話を盛り上げる効果を出していました。
しかし、手元に触れるものや傍らのものが存在しない場合、そのような効果を発揮することができず、取り付く島がない状態になることを意味していました。
「取り付く島がない」という言葉についてまとめ
「取り付く島がない」という言葉は、進展の見込みがない状況を表現する際に使われます。
この言葉は、手がかりや頼りになるものがなく、進める道がほとんどない状況を指し、困難な状況や進展の見込みがない状況を表す際にも使用されます。
由来は江戸時代の語り部や講釈師の間で広まり、口演の際に手元や周囲のものに触れることで話を盛り上げる効果を出していたため、取り付く島がない状態を象徴していました。