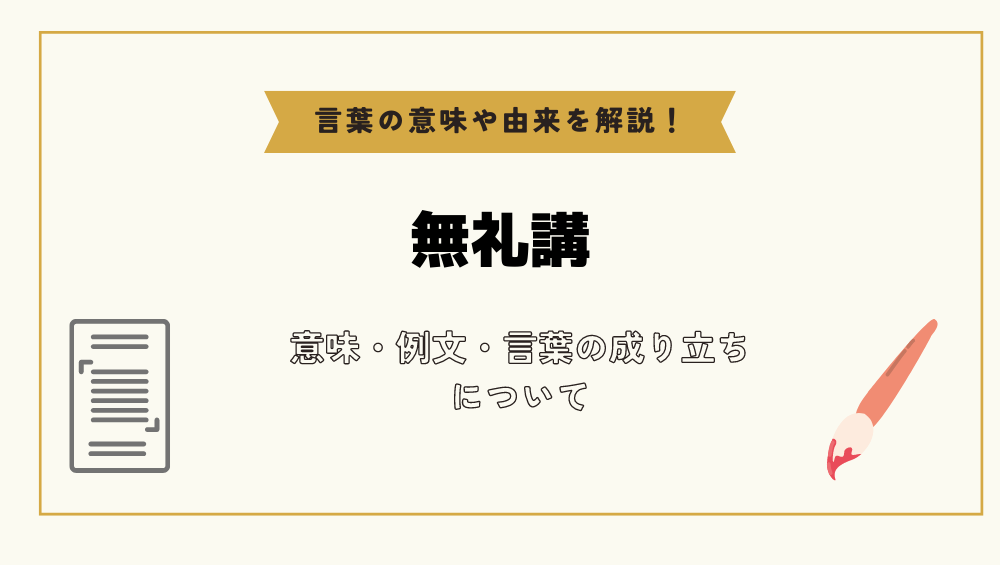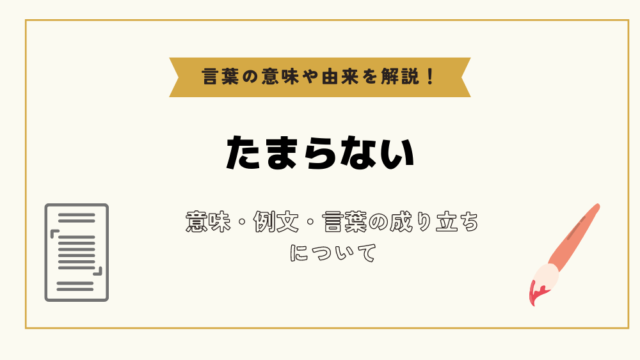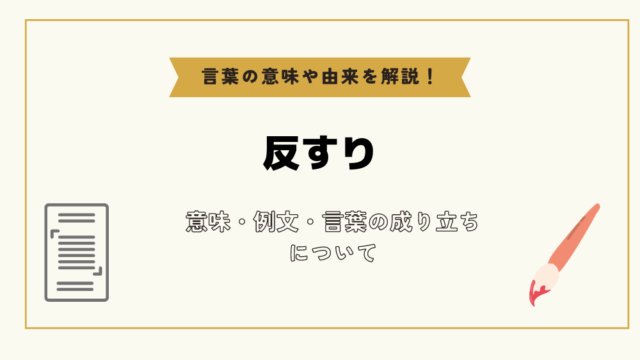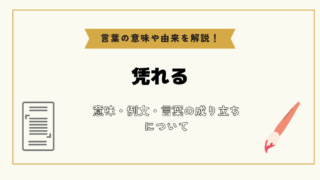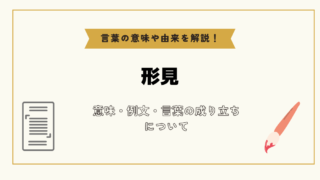Contents
「無礼講」という言葉の意味を解説!
「無礼講」とは、集まった人々が普段の礼節や作法を度外視して、自由な雰囲気で交流することを指します。
普段では言えないようなことも言い合ったり、行動の自由度が高まります。
無礼講は、会社の部署間の交流や友人同士の集まりで行われることが多いです。
多くの場合、お酒を飲みながら行われ、参加者同士がより親しみを感じることができます。
「無礼講」の読み方はなんと読む?
「無礼講」は、「ぶれいこう」と読みます。
この言葉は、漢字の「無礼」と「講」から構成されています。
日本の言葉にもよくあるように、漢字の組み合わせから読まれる形になります。
「無礼講」という言葉の使い方や例文を解説!
「無礼講」は、特定の状況や人間関係において使われる言葉です。
例えば、ある会社の新年会で「無礼講」が行われることがあります。
この場合、上司と部下が普段の上下関係を忘れ、自由に意見を言い合ったり、笑い合ったりします。
また、友人たちが集まる飲み会でも「無礼講」が行われることがあります。
この場合は、普段のスタイルや作法に縛られず、自由なトークが展開されます。
「無礼講」という言葉の成り立ちや由来について解説
「無礼講」の成り立ちは、明確にはわかっていません。
しかし、江戸時代から「講」という言葉は団体や集まりを意味する言葉として使われており、その中で様々な形態の講が行われていました。
また、無礼講は元々は仏教の宗教行事において、僧侶同士が厳粛な雰囲気を忘れて和気藹々と遊ぶことを指していたとも言われています。
「無礼講」という言葉の歴史
「無礼講」という言葉の歴史は古く、江戸時代にさかのぼります。
当時は、無礼講が寺院の僧侶の間で行われることがありました。
しかし、明治時代以降は一般市民の間でも行われるようになりました。
現在では、無礼講は年末や年始などの特別な場で行われることが多いです。
「無礼講」という言葉についてまとめ
「無礼講」とは、普段の礼節や作法を度外視して、自由な雰囲気で交流することを指します。
新年会や飲み会などの特別な場で行われることが多く、参加者同士の親しみを深める効果があります。
成り立ちや由来は明確にはわかっていませんが、江戸時代から存在していた言葉であることがわかっています。
現代でも、無礼講は広く知られており、楽しい雰囲気の中で親交を深める一助となっています。